本物は見たことがない。
が、この作品は美術の教科書や、通史的な画集なんかでもちょくちょくお目にかかる有名なもの。
逆に言えば「ああ、あれね」と思ってしまう類。
この「ああ、あれね」が美術鑑賞を阻害する一要因なのだが、なかなか修正は困難です。
いつでも虚心坦懐に物に対峙することが出来るのは達人だけだろう。修行が足りません。
そういう素人に大変良い番組です、「極上美の饗宴」は。
……NHKのまわし者みたいになっているが、まあやっぱり良く作っていると思いますよ。
メジャーからマイナーまで。取り上げる幅が広くてありがたい。
取り上げ方もけっこう突っ込んでてありがたい。
民放だとメジャー限定になってしまう。
今回面白かったのは、やはりジオラマを作ったことだな。
正直、完成したジオラマ自体はそれほど面白くなかった。期待したほどは。
だが作っている過程で、どんなふうに歪んでいるのかを細かく説明してくれていたので
それが面白かった。なるほど。同じ形の壁は一つとして無いわけなのねー。
それは作るのが難しかろう。
それから、絵自体の細部。
遠景に描かれた人が1センチにも満たないと教えられてびっくりし、
そーいえばものすごくたくさんの人が描きこんであるよなーと思いを致し、
洗濯をする人とか、家庭菜園(?)まで描いてあると聞いて、ほー、と思う。
想像力の飛翔を感じる。バベルの塔ほどの建造物を実際に建てたことがある人はいないわけだから、
その時どういうことが起こって行くのかというのは純粋に想像の世界だよね。
いやもしかすると。
番組では「ローマのコロッセオから影響を受けた」と言っていたが、
コロッセオを建てた時にも、似たようなことがあったのかもしれない。
ブリューゲル当時のローマの観光ガイドが「これを建てる時には周りに洗濯小屋とか炊事場などが
たくさん作られたんですよ」と説明している図が浮かんだ。
そうすれば降りてくるまでにまる一日かかりそうな壮大な塔の途中に、炊事場があるのは自然だ。
でないと塔のてっぺんのあたりの職人は生き延びられません。
世界の構築の楽しみ。ブリューゲルはそれを味わっていたと思う。
箱庭的世界が好きな人がいるでしょ。わたしもそうだが。
中国水墨画なんかにもあるよね。画面の中の人の暮らしが想像出来るような。
うーん。でもあれとは違うか。ブリューゲルはその小さい人たちに風刺をこめたりしているからなあ。
東洋の水墨画はむしろまったり感を大事にしているというか……
ちなみにいつも思うのだが、この「バベルの塔」と「雪中の狩人」と、同じ人が描いたとは思えない。
なんか絵の背後の精神に同質なものを感じない。
ここまでの建物を描き上げる人が、他の作品で建物に執着してないというのが不思議なんだよね。
バベルの塔をここまで凝って描く人ならば、建築は好きな主題ではないのか。
Wikiで見る分には、「ネーデルラントの諺」と「子供の遊戯」は同工の作品だ。
どちらも物づくし。清少納言が「枕草子」で物づくしをやったように。
これが「バベルの塔」となると……遠景人物で物づくしをやっていると言えないこともないが、
基本は一応聖書に題をとった――まあ宗教画とも言えないけど伝統的な画題。
そして「雪中の狩人」では大変立派な遠近法を使い、近景・中景・遠景をかちっとまとめている。
「バベルの塔」も遠近法の世界ではあるが、歪んでいるし、近景・遠景が調和的ともいいかねる。
――とにかく“違う”と感じる。
ボッティチェリあたりも前期と後期では別もんになっていますけれどね。
ブリューゲルは、「怠け者の天国」「農家の婚礼」あたりは「子供の遊戯」とかと
すらりと繋がる気がするんだよなあ。「バベルの塔」と「雪中の狩人」が異質だ。
長年の疑問である。
が、この作品は美術の教科書や、通史的な画集なんかでもちょくちょくお目にかかる有名なもの。
逆に言えば「ああ、あれね」と思ってしまう類。
この「ああ、あれね」が美術鑑賞を阻害する一要因なのだが、なかなか修正は困難です。
いつでも虚心坦懐に物に対峙することが出来るのは達人だけだろう。修行が足りません。
そういう素人に大変良い番組です、「極上美の饗宴」は。
……NHKのまわし者みたいになっているが、まあやっぱり良く作っていると思いますよ。
メジャーからマイナーまで。取り上げる幅が広くてありがたい。
取り上げ方もけっこう突っ込んでてありがたい。
民放だとメジャー限定になってしまう。
今回面白かったのは、やはりジオラマを作ったことだな。
正直、完成したジオラマ自体はそれほど面白くなかった。期待したほどは。
だが作っている過程で、どんなふうに歪んでいるのかを細かく説明してくれていたので
それが面白かった。なるほど。同じ形の壁は一つとして無いわけなのねー。
それは作るのが難しかろう。
それから、絵自体の細部。
遠景に描かれた人が1センチにも満たないと教えられてびっくりし、
そーいえばものすごくたくさんの人が描きこんであるよなーと思いを致し、
洗濯をする人とか、家庭菜園(?)まで描いてあると聞いて、ほー、と思う。
想像力の飛翔を感じる。バベルの塔ほどの建造物を実際に建てたことがある人はいないわけだから、
その時どういうことが起こって行くのかというのは純粋に想像の世界だよね。
いやもしかすると。
番組では「ローマのコロッセオから影響を受けた」と言っていたが、
コロッセオを建てた時にも、似たようなことがあったのかもしれない。
ブリューゲル当時のローマの観光ガイドが「これを建てる時には周りに洗濯小屋とか炊事場などが
たくさん作られたんですよ」と説明している図が浮かんだ。
そうすれば降りてくるまでにまる一日かかりそうな壮大な塔の途中に、炊事場があるのは自然だ。
でないと塔のてっぺんのあたりの職人は生き延びられません。
世界の構築の楽しみ。ブリューゲルはそれを味わっていたと思う。
箱庭的世界が好きな人がいるでしょ。わたしもそうだが。
中国水墨画なんかにもあるよね。画面の中の人の暮らしが想像出来るような。
うーん。でもあれとは違うか。ブリューゲルはその小さい人たちに風刺をこめたりしているからなあ。
東洋の水墨画はむしろまったり感を大事にしているというか……
ちなみにいつも思うのだが、この「バベルの塔」と「雪中の狩人」と、同じ人が描いたとは思えない。
なんか絵の背後の精神に同質なものを感じない。
ここまでの建物を描き上げる人が、他の作品で建物に執着してないというのが不思議なんだよね。
バベルの塔をここまで凝って描く人ならば、建築は好きな主題ではないのか。
Wikiで見る分には、「ネーデルラントの諺」と「子供の遊戯」は同工の作品だ。
どちらも物づくし。清少納言が「枕草子」で物づくしをやったように。
これが「バベルの塔」となると……遠景人物で物づくしをやっていると言えないこともないが、
基本は一応聖書に題をとった――まあ宗教画とも言えないけど伝統的な画題。
そして「雪中の狩人」では大変立派な遠近法を使い、近景・中景・遠景をかちっとまとめている。
「バベルの塔」も遠近法の世界ではあるが、歪んでいるし、近景・遠景が調和的ともいいかねる。
――とにかく“違う”と感じる。
ボッティチェリあたりも前期と後期では別もんになっていますけれどね。
ブリューゲルは、「怠け者の天国」「農家の婚礼」あたりは「子供の遊戯」とかと
すらりと繋がる気がするんだよなあ。「バベルの塔」と「雪中の狩人」が異質だ。
長年の疑問である。










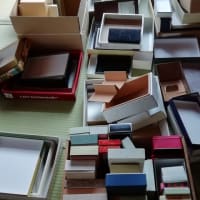














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます