これを読んだのは、とにもかくにも、群ようこが「第七官界彷徨」について、
「日本の小説はこの一作でいいとすら思ったこともある」
と書いているというのを読んだから。そこまで惚れられる小説はどんなんだろうと
思うじゃないですか。群ようこ自体を読んだことは無いにせよ、
彼女は田辺聖子と交流があり、なんとなく親しみを持っていたので。
……と書こうとしてふと疑問に思い、確認してみたら、田辺聖子と交流があるのは
鴨居羊子でした。……「鴨」や「羊」の「群」の連想だろうか。まあいいや。
多分、群ようこの言葉を読んだのはここでかなー、と思うけど。
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0424.html
だが、上記サイトの当該記事には重大な(?)間違いがありますぜ、セイゴオせんせ。
記事の真ん中あたりに「薊」という漢字があり、「(アザミ)」と振り仮名も振ってあるが、
多分はこれは蘚(コケ)の間違い。
わたしも蘚という字をコケとは読めないんだけれども、ルビはそうなっているので
(ついでに、変換すると出てくるので)多分そう。
アザミはこの話には出てこなかったと思うよ。絶対とも言い切れないが。
二助が研究しているのは、蘚の恋です。蘚の花粉というのも出てくるので、
蘚には花粉があるのか?とも思うんだけどね。苔は胞子で増えるんじゃないのか?
※※※※※※※※※※※※
尾崎翠の日本語は実に風変わりである。どういう風に風変わりかというと、
……そんなこと簡単に言えるもんですか。知りたい人は読むしかない。
代表作である「第七官界彷徨」においては、一番わかりやすい“風変わり”は
「女の子」の使い方であろう。
「いいねこの蒲団は。うちの女の子はなかなか巧いようだ。(これはすべて二助が
私に与えるなぐさめであった)僕にもひとつ作ってくれないか。そうだ、僕は
ちょうどきれいな飾り紐を二本もっている。(二助は境のふすまを開けて赤と青の
二本の紙紐をもってきた)これは昨日僕が粉末肥料を買ったとき僕の粉末肥料を
包装してあった紐だが、ちょうど肱蒲団の飾りにいいだろう。僕のを青くして
女の子のを赤くするといいね。ふさいでないで赤い肱蒲団をあてたり、それから
うんと大声で音楽をうたってもいいよ。僕は昨夜で第二鉢の論文も済んだし、
当分暢気だからね。今晩から僕はうちの女の子におたまじゃくしの講義を
聴くことにしよう」
全体の中で重要な台詞でもないが、「女の子」の使い方の例として引用してみた。
これは恋愛感情に悲しんでいる主人公をなぐさめるために、二助(次兄)が
当の主人公(=女の子)へ語りかける台詞。一度目の「女の子」はいいとして、
二度目と三度目の「女の子」は、普通ならどうしたって「お前」とか「町子」とあるべきところ。
この「第七官界彷徨」は設定としては、長兄、次兄と従兄弟の3人の男と同居する
女の子(妹)の話なのだが。この設定には意味がない。
意味がないというのは、なんというか……兄妹の話ではないということ。
だいたい、読んでても家庭の雰囲気がないし。しばしば「家族」という言葉は出てくるにせよ、
この「家族」というのも使い方が普通の日本語と違う。明確に違うのではなくて、
4分の1くらいずれている、あるいは意味が一回り大きくなっている印象。
こういう日本語は――どこかの平行世界では普通に話されているのかもしれないな、と思う。
食事をしながら30分位没頭して読んだ後、店を出てふと夜の街角を眺めた時に、
いつもの見慣れた風景が、どこか奇妙に歪んで見える。そんな力を持つ。
松田正剛の記事を読んだ後に思ったが、なるほど、昔、少女マンガを立ち読みして
店を出た後の世界の変容の感覚に少し似てるわ。だからといって、セイゴオせんせのように
少女マンガの系譜だ!と断言するつもりはないけどね。
というか、あんまり「少女マンガ」とか「乙女」とか言って欲しくない。
それを連呼されるとそれだけの話になってしまう。大事なのは少女マンガ感覚ではなく、
その風変わり感でしょ?こういう風変わり感は少女マンガでも時折表現されるけど、
アクションが少年マンガの全てではないように、風変わり感を少女マンガとイコールで
結ぶことも出来ないよ。
あんまり連呼されると、この風変わり感が合わない人が「少女マンガにはついていけない」と
したり顔で言うようになる。それは的外れな話だ。
個人的にはこの作品に「この一作でいい」とまで惚れこむことは出来なかったが。
風変わりな日本語によって縁取られた、風変わりで静謐な世界をこっそりのぞき見る。
そんな楽しみ方が出来る小説だと思う。別な世界へ旅に出よ。
※※※※※※※※※※※※
わたしはものを知らないので、尾崎翠と山尾悠子を比べることに意味があるのかどうかは
わからないが。読みながら山尾悠子を思い出していた。
ちなみに山尾悠子は、わたしが唯一「凄い」と表現したい作家。
(しかしすごく好きかというとそれは違います)
どちらも「孤高の」という気がする。寡作であること。独立峰のような作品群。
どこにも媚びず。常人には見えない、どこか別の並行世界のミニチュアを
瞬きもせずに見つめながら書いたような気がすること。
彼女たちの年代は相当に違いますけれどね。書いたものも文体も、それも相当に違う。
それでも二人を並べてみたくなるのは、やはりその特異性のゆえだろうか。
幻想文学初心者は、とりあえずこの二人は読んでおくべき。
「凄い」山尾悠子についてブログ内記事。
http://blog.goo.ne.jp/uraraka-umeko/e/94eb868a7381f50cebdc20738ca4585f











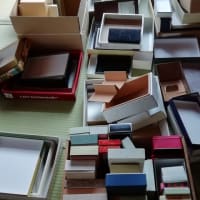














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます