昨今詩歌について書いてくれる人がめっきりいなくなったので――というのは嘘で、
単にわたしが読んでないだけ――書いてくれるのはうれしい。
北村薫は前歴が高校の国語の教師だったし、出身はミステリ作家だし、
文学への誘いとしては最適の人だと思う。
……願わくば、もう少し入門編を意識した本であるといいんだけどね。
この人、自分が好きなもんだから一歩踏み込んだ文学を取り上げていて。
これがもうちっと聞いたことがある素材だったら、興味を持つ人が増えるかもしれない。
が、書きたいことを書かせてあげたいしね。
いつか15歳くらいの年代に向けた詩歌の紹介書を書いてくれれば良しとする。
この本では冒頭のプレヴェール「朝の食事」についてのエッセイが面白かった。
3章にわたって展開される。外国語の詩の翻訳について。
プレヴェールの「朝の食事」は訳されたものを見るとたしかにシンプルな詩なんだろう。
しかしそのシンプルな詩でも5人の訳者がいれば5通りの訳があって……
それが見事に毛色が違うもんだから、その例を非常にわかりやすく
目の前に並べてくれるもんだから、面白かった。
訳者は内藤濯、小笠原豊樹、平田文也、北川冬彦、大岡信。
シンプルな詩だからこそ、一人称の選択、その頻度、分かち書きの行数など、
選択によってがらっと変わって見える。
わたしは北川冬彦のが一番好きだったかな。
最初の内藤濯訳は、
「茶碗にコーヒーをつぎました
コーヒー入りの茶碗にミルクを入れました
ミルク入りのコーヒーに砂糖を入れました」
と始まるのだが、2行目の「コーヒー入りの茶碗」という表現にひっかかったので
読めなかった。
3行目と対にさせたいからこういう表現になったのだろうが、
「コーヒーが入った茶碗」とはいえても、「コーヒー入りの茶碗」とは
いえないのではないか。コーヒー入りの茶碗だと、焼く時に陶土にコーヒーの
粉末でも混ぜ込んだ茶碗を想像してしまう。
中盤は知らない詩人/歌人のことだったけれど、終盤の藤原実方と藤原行成の話は
ちょっと面白かった。実方が落馬して死んだとされる道祖神社、その墓は
わたしが若い頃歴史散歩の一環として歩き回ったところ。
この2人の男性は田辺聖子さんの「むかし・あけぼの」にも活写されていて、
それぞれになじみ深い。
これはずいぶん前に正編が出て、今回が続編。
この装丁好きなんだよな。味わいのある植物画。
秋の木の実は北村薫が人生のこのタイミングで書く(2005年)
文学エッセイにふさわしいかもしれない。
ちなみに詩歌の「待ち伏せ」というのは、読書をしていると時々出会う、
「Aについて読んでいると(読んだ直後に)Aの関連に出会う」こと。
わたしは同じ事象を「共時性」と呼んでいる。ことは詩歌に限ったことではなく、
知識系の本でも意外なほどよく起こります。本のカミさまのお導き。
単にわたしが読んでないだけ――書いてくれるのはうれしい。
北村薫は前歴が高校の国語の教師だったし、出身はミステリ作家だし、
文学への誘いとしては最適の人だと思う。
……願わくば、もう少し入門編を意識した本であるといいんだけどね。
この人、自分が好きなもんだから一歩踏み込んだ文学を取り上げていて。
これがもうちっと聞いたことがある素材だったら、興味を持つ人が増えるかもしれない。
が、書きたいことを書かせてあげたいしね。
いつか15歳くらいの年代に向けた詩歌の紹介書を書いてくれれば良しとする。
この本では冒頭のプレヴェール「朝の食事」についてのエッセイが面白かった。
3章にわたって展開される。外国語の詩の翻訳について。
プレヴェールの「朝の食事」は訳されたものを見るとたしかにシンプルな詩なんだろう。
しかしそのシンプルな詩でも5人の訳者がいれば5通りの訳があって……
それが見事に毛色が違うもんだから、その例を非常にわかりやすく
目の前に並べてくれるもんだから、面白かった。
訳者は内藤濯、小笠原豊樹、平田文也、北川冬彦、大岡信。
シンプルな詩だからこそ、一人称の選択、その頻度、分かち書きの行数など、
選択によってがらっと変わって見える。
わたしは北川冬彦のが一番好きだったかな。
最初の内藤濯訳は、
「茶碗にコーヒーをつぎました
コーヒー入りの茶碗にミルクを入れました
ミルク入りのコーヒーに砂糖を入れました」
と始まるのだが、2行目の「コーヒー入りの茶碗」という表現にひっかかったので
読めなかった。
3行目と対にさせたいからこういう表現になったのだろうが、
「コーヒーが入った茶碗」とはいえても、「コーヒー入りの茶碗」とは
いえないのではないか。コーヒー入りの茶碗だと、焼く時に陶土にコーヒーの
粉末でも混ぜ込んだ茶碗を想像してしまう。
中盤は知らない詩人/歌人のことだったけれど、終盤の藤原実方と藤原行成の話は
ちょっと面白かった。実方が落馬して死んだとされる道祖神社、その墓は
わたしが若い頃歴史散歩の一環として歩き回ったところ。
この2人の男性は田辺聖子さんの「むかし・あけぼの」にも活写されていて、
それぞれになじみ深い。
これはずいぶん前に正編が出て、今回が続編。
この装丁好きなんだよな。味わいのある植物画。
秋の木の実は北村薫が人生のこのタイミングで書く(2005年)
文学エッセイにふさわしいかもしれない。
ちなみに詩歌の「待ち伏せ」というのは、読書をしていると時々出会う、
「Aについて読んでいると(読んだ直後に)Aの関連に出会う」こと。
わたしは同じ事象を「共時性」と呼んでいる。ことは詩歌に限ったことではなく、
知識系の本でも意外なほどよく起こります。本のカミさまのお導き。










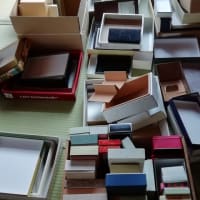














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます