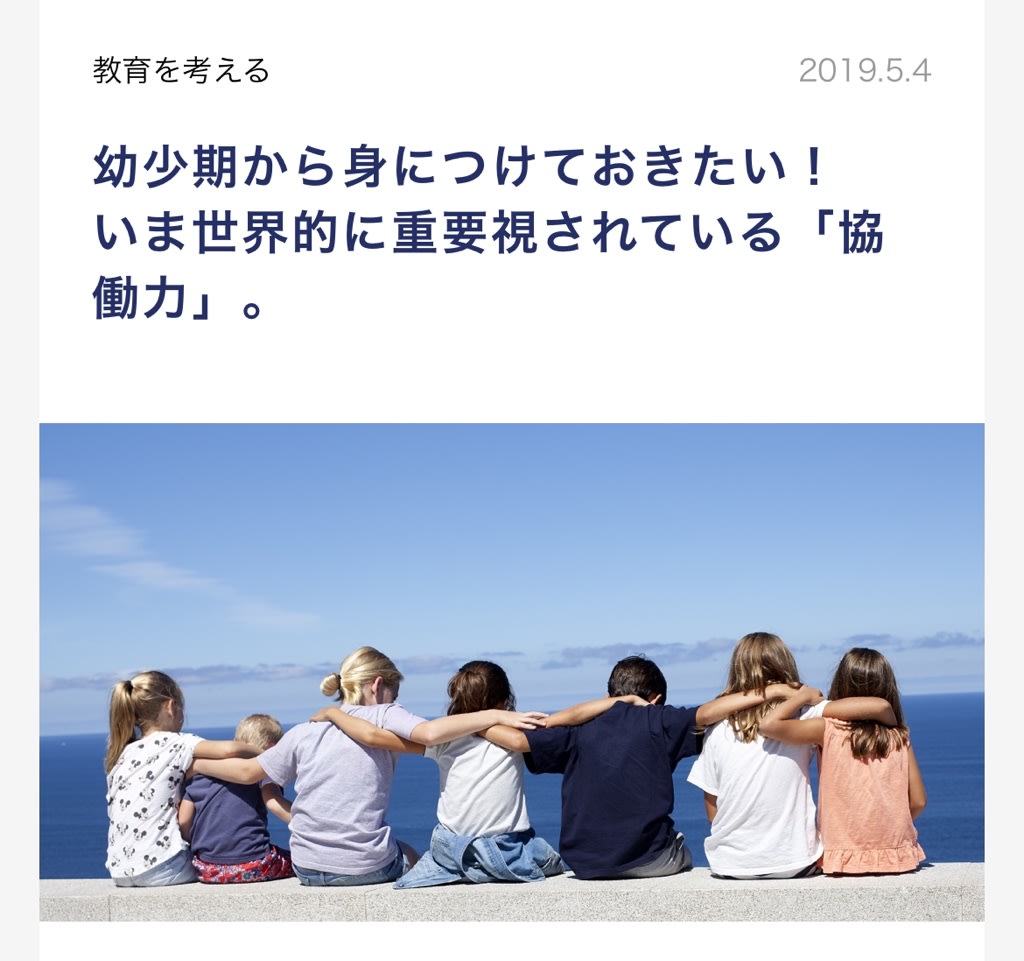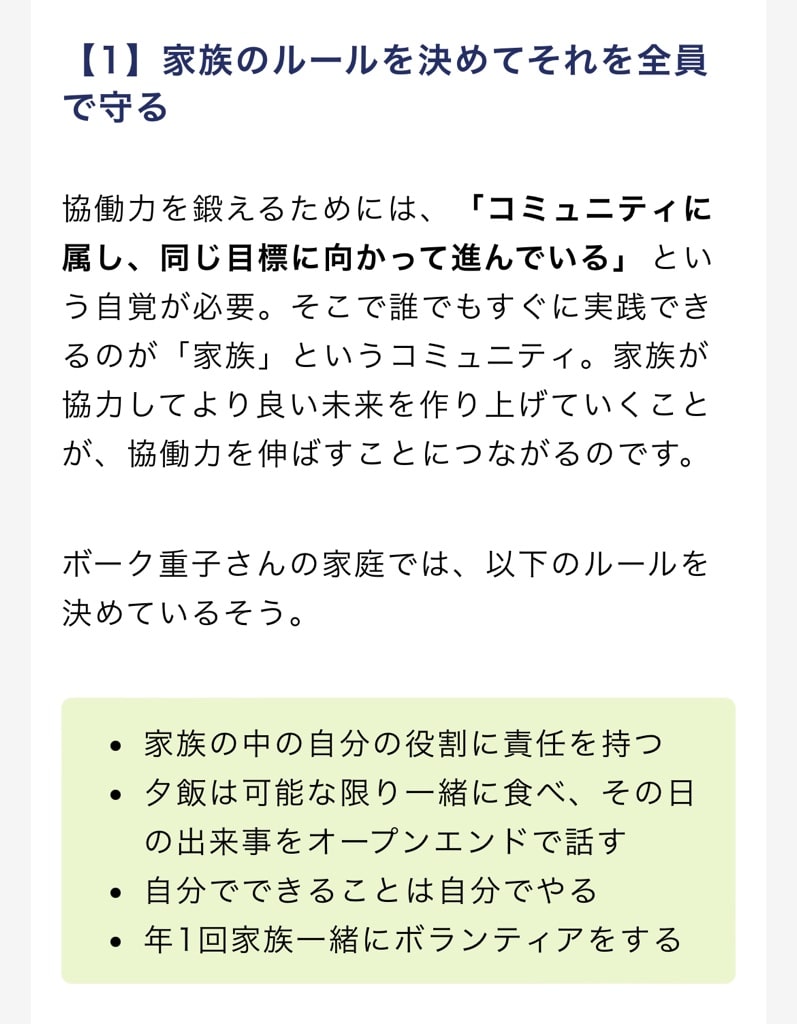農家の方に畑を借りているのですが
6月20日にさつまいも🍠の苗を
⬇️

⬇️
植えました。

⬇️
7月17日

⬇️
10月21日

⬇️

特に堆肥も農薬も使わずに
栽培しましたが、
雑草がすごく生えたので
草取りはやりました。
10月23日に畑に行きましたら
動物に掘り返された跡があり
3〜4個の芋が食い散らかして
散乱していたので!
慌てて収穫しました😂
農家の方に聞いたら
アナグマ?イノシシ?かなあ…
ということでした。
シカは芋は食べない?
芋の苗は50本植えたのですが
大体、推定で25キロぐらい
収穫できました。
収穫した芋は2週間ほどは
新聞紙にくるんで寝かせておくと
甘味が増すそうなので
寝かせてみました。
〜感想〜
◯苗の調達ができたら
芋はわりと丈夫で生命力があって
グングン成長した。
◯動物との闘いが恐怖
(最初の若いうちの葉っぱをシカに食べられた、芋をアナグマ(イノシシ)にやられた)
◯雑草との闘いに大変😢草取りに汗💦
◯政府が食糧危機になったら
芋を植えろ、というが
4ヶ月強は時間がかかるので
そんなに簡単には食べられない、
ということが分かった。