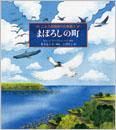氷河に覆われたスウェーデンの最高峰 ケブネカイセ山の標高は温暖化の影響で毎年低くなっている。私が初めて登った2008年は標高2,111mと言われていたのに2012年には2,104mとなっていた。このままではいずれ最高峰が隣にある北峰よりも低くなってしまうのでは?それが今年かも知れない。と心配されていた。(北峰は岩稜であるためこれ以上は低くならない)
毎年8月にストックホルム大学(タルファラ観測所)によって行われる計測結果の速報が下記Facebookで報じられている。
その結果、僅か70㎝差で何とか主峰の座を守ったようだ。
しかし来年は絶対に入れ替わるだろう。
https://www.facebook.com/pages/Tarfala-Research-Station/234870483202709
100年前に書かれたスウェーデンを代表する物語「ニルスの不思議な旅」にはケブネカイセは2,123mと紹介されている。今年は2097.5mだったので100年前から比べると25.5m低くなったと思うだろうがそう単純ではない。この100年間にスカンジナビア半島自体が氷河が融けた影響で隆起している。100年前の北峰の標高から推理すると15メートル隆起していると考えられるので実際ケブネカイセは40m以上も低くなったと考える。
この6年間でも明らかに山頂部の氷河がやせ細ってしまったように見える。
これは対岸の火事ではない。近年頻発する豪雨、局地的豪雪などによって起こる災害は全て温暖化と何らかの影響がある事を忘れてはならない。
ラップランド(スウェーデン)のイェリヴァーレに住む知人からの情報では、2月の平均気温は過去90年間で2番目に暖かかったと地元紙が伝えているそうだ。
ラップランドに近い都市ルーレオ(北極圏よりも南)では2月の平均気温が-1.5℃で、セントラル公園に展示される動物をテーマとした氷像(今年はハリネズミ)は既に撤去され、アイスロードと言われる4月上旬まで通れる道が3月6日でクローズとなったと伝えている。
(下記PDF参照)
このところ寒波に見舞われて、大量の降雪を目の前にすると地球温暖化の事は忘れそうになる。
しかしこの30年間で北極海を覆っていた氷の面積は半分にまで縮小しているのも事実。
そのことで問題になっているのは自然環境の変化ばかりかと思えば、実は・・・。
下記 国際問題研究所のサイトにに関連記事が寄せられている。
氷河で覆われたスウェーデン最高峰のケブネカイセ山は、温暖化の影響で年々その標高が低くなっている。
以前からやがてその隣のケブネカイセ北峰の方が高くなるだろうと言われていたが、とうとうそれが現実のものになろうとしている。
1968年に2,120m有った標高は、今年8月の測量では2,100mとなり、北峰との差は僅か3m高いだけになってしまったという記事がスウェーデンの新聞に紹介された。
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kebnekaise-lagre-an-nagonsin
 近年は北極海の氷が融けて大気中の水蒸気量が増えたため、北極圏でも集中豪雨などの異常気象が頻繁に起きている。
近年は北極海の氷が融けて大気中の水蒸気量が増えたため、北極圏でも集中豪雨などの異常気象が頻繁に起きている。
夏期に降水量が増えると氷河の融解も加速する。
2012年7月に私がスカンジナビア半島の北極圏内(ラップランド)を踏査中に遭遇した大嵐による大洪水もその一つだ。
また冬期の高温は北極圏内で、真冬に雨を降らせる。
2007年に起きたトナカイの大量死は、厳冬期の降雨によって融けた雪が、その後の冷え込みで再び氷りつき、トナカイのエサとなる苔が氷の下となってしまった事による餓死が原因だった。
トナカイ遊牧をして暮らしてきた先住民サーメにとっては大打撃を被った。
このように地球温暖化は、予測できない事態を次々に引き起こし我々の生活を脅かすだろう。
このような変化を察知し、将来の変化に備えることが急務となっている。
 Cunojavrre(クーノヤウレ)からスウェーデン国境までは数キロメートル。石を積み上げたケルンがあるだけだった。スウェーデン側に入るとノルウェーの急峻な山岳地帯は遠くなり残雪も少なくなる。しかしクングスレーデンに出るまでは幾つか標高の高い峠を越えなければならない。
Cunojavrre(クーノヤウレ)からスウェーデン国境までは数キロメートル。石を積み上げたケルンがあるだけだった。スウェーデン側に入るとノルウェーの急峻な山岳地帯は遠くなり残雪も少なくなる。しかしクングスレーデンに出るまでは幾つか標高の高い峠を越えなければならない。
 Unna Allakas(ウンナアラカス)小屋で管理人にその先の状況を聞く。2週間前まではここも全面雪で覆われていたらしい。
Unna Allakas(ウンナアラカス)小屋で管理人にその先の状況を聞く。2週間前まではここも全面雪で覆われていたらしい。
この先も残雪や渡渉が予想される。
 幾つかの峠や雪渓を越えて行く。遠くにAbisko(アビスコ)方面の山々が見えてくる。時折陽が差したり、雨粒が落ちてくる微妙な天候。気温は上がらない。
幾つかの峠や雪渓を越えて行く。遠くにAbisko(アビスコ)方面の山々が見えてくる。時折陽が差したり、雨粒が落ちてくる微妙な天候。気温は上がらない。
こんな雨模様で大きな川を渡るのは真っ平御免と思っているとやはり。
 標高1034㍍の凍った湖から流れ出す川の温度はどれくらい冷たいのだろう?靴を履き替え、雨合羽の裾をまくりあげて一気に渡りきる。
標高1034㍍の凍った湖から流れ出す川の温度はどれくらい冷たいのだろう?靴を履き替え、雨合羽の裾をまくりあげて一気に渡りきる。
雨が続くと雪解けも加速し、当然水量が多くなる。この先も何度渡渉しなければいけないのか分からないが、とにかく楽しい。
 峠に向かえば広大な残雪。ガスが立ち込めると方向が分からなくなる。
峠に向かえば広大な残雪。ガスが立ち込めると方向が分からなくなる。
そんなことを繰り返しながらAlesjaure(アレスヤウレ)への大きな峠をパスして、ようやくクングスレーデンに出る。
 湖畔でテントを張るが今度は蚊の大群に襲われる。Alesjaure(アレスヤウレ)小屋の前に計りが有ったのでザックを吊るしてみた。まだ27㎏近くも背負っている。Alesjaure小屋で管理人に、この先の天気情報を聞いてみるが、この先もどんどん天気は悪くなるらしい。次のTjaktja(チェクチャ)で天候が悪いようなら小屋を利用しようかと考える。標高は1,000㍍を越えてくると風雨も激しくなり、寒さも増してくる。(*前述したが中部日本に換算すると標高3,000㍍前後プラスの気象状況と考えると良い)
湖畔でテントを張るが今度は蚊の大群に襲われる。Alesjaure(アレスヤウレ)小屋の前に計りが有ったのでザックを吊るしてみた。まだ27㎏近くも背負っている。Alesjaure小屋で管理人に、この先の天気情報を聞いてみるが、この先もどんどん天気は悪くなるらしい。次のTjaktja(チェクチャ)で天候が悪いようなら小屋を利用しようかと考える。標高は1,000㍍を越えてくると風雨も激しくなり、寒さも増してくる。(*前述したが中部日本に換算すると標高3,000㍍前後プラスの気象状況と考えると良い)
 Tjaktja(チェクチャ)小屋には小さな小屋で、20ベッド定員のところ28人入っているので、今日は泊まれないよ!と管理人が外にいるみんなに言っている。この先天気も悪くなるからヘリを呼んでやろうか?と笑っている。実際小さい子供連れの家族がヘリで飛んで行った。私はテントがあるから別に構わないよと言ってテント場に向かう。
Tjaktja(チェクチャ)小屋には小さな小屋で、20ベッド定員のところ28人入っているので、今日は泊まれないよ!と管理人が外にいるみんなに言っている。この先天気も悪くなるからヘリを呼んでやろうか?と笑っている。実際小さい子供連れの家族がヘリで飛んで行った。私はテントがあるから別に構わないよと言ってテント場に向かう。
 日本では登山者安全のために、宿泊を拒否したら大変な問題になるのに、ここでは基本的に小屋は無いもの。という前提で行動することの方が正しい。夜にかけて気圧は底なしに下がっていき、強風でテントが曲がりそうだ。
日本では登山者安全のために、宿泊を拒否したら大変な問題になるのに、ここでは基本的に小屋は無いもの。という前提で行動することの方が正しい。夜にかけて気圧は底なしに下がっていき、強風でテントが曲がりそうだ。
 翌朝隣でテントを張っていたプラハの2人に大丈夫だったか尋ねると、昨夜の強風でテントのフライシートが裂けてしまったらしい。相変わらず雨は降り続いている。雪解け水も氾濫気味で、川を渡ろうとすると、スノーブリッジかなり怪しい。Tjaktja(チェクチャ)峠から振り返ればどこが川か分からないくらい一面水浸しだ。峠の避難小屋で一休みしようと中に入ると、1人のスウェーデン人女性が倒れている。
翌朝隣でテントを張っていたプラハの2人に大丈夫だったか尋ねると、昨夜の強風でテントのフライシートが裂けてしまったらしい。相変わらず雨は降り続いている。雪解け水も氾濫気味で、川を渡ろうとすると、スノーブリッジかなり怪しい。Tjaktja(チェクチャ)峠から振り返ればどこが川か分からないくらい一面水浸しだ。峠の避難小屋で一休みしようと中に入ると、1人のスウェーデン人女性が倒れている。
 昨夜小屋の軒先で言葉を交わしたグループの1人だった。彼らはあの暴風雨の中を峠の先を目指して前夜に出て行ったのだった。気温は5℃前後、朝を待って、仲間の2人が小屋に緊急無線でヘリを要請しに駆け下り、程なくして悪天候の中を救急ヘリがやって来た。かろうじて峠は視界が有って良かった。(この時ケブネカイセ上部では60~70㌢の新雪が積もったらしい)
昨夜小屋の軒先で言葉を交わしたグループの1人だった。彼らはあの暴風雨の中を峠の先を目指して前夜に出て行ったのだった。気温は5℃前後、朝を待って、仲間の2人が小屋に緊急無線でヘリを要請しに駆け下り、程なくして悪天候の中を救急ヘリがやって来た。かろうじて峠は視界が有って良かった。(この時ケブネカイセ上部では60~70㌢の新雪が積もったらしい)
峠から先はSalka(セルカ)小屋まで氾濫しそうな川を幾つも渡り、何とか無事小屋までたどり着いた。ここは比較的大きな施設。ずぶ濡れの靴やザックを乾かしたかったので、最初から小屋泊まりの予定でだった。小屋に着くと小屋のクルーが衛星携帯で話をしている。荷物を片付けたりしていると回りが何やらおかしな雰囲気。ここから先の川が大増水し、幾つか橋が流され、明日以降天気が回復しても、この先は進めないのだという。唯一の移動手段はヘリ脱出。グループ単位でヘリに割り勘で分乗する手配が始まった。行き先はケブネカイセマウンテンステーションかニッカルオクタ。何日か待って水が引いたら歩くことも可能だろうが、日程がそれを許さないし、その先の状況も不明。ゴールに設定していたRitsem(リッセム)まで66㎞手前で今回のトレッキングはあえなく終了。あっけない幕切れだった。
 翌朝雨は止んでいるが6:00現在気温6℃、すごく寒い。ヘリの順番を待ち、割り勘でケブネカイゼで飛んでゆっくりと体を休め、Ritsem(リッセム)で会う約束をしていたスウェーデン人の知人のもとへは、Kiruna(キルナ)からバスを乗り継いで期日に向かった。
翌朝雨は止んでいるが6:00現在気温6℃、すごく寒い。ヘリの順番を待ち、割り勘でケブネカイゼで飛んでゆっくりと体を休め、Ritsem(リッセム)で会う約束をしていたスウェーデン人の知人のもとへは、Kiruna(キルナ)からバスを乗り継いで期日に向かった。
 振り返れば、当初予定していた国境山岳地帯は、現地の雪の状況判断で早めにスウェーデン側に回避し、雨と増水、低温は慎重な行動で切り抜けることが出来た。計画通り行かない事も想定内だったし、ヘリ移動もやむなしだった。イレギュラーこそ旅の楽しさで、充分満足な第4次北極圏遠征だった。
振り返れば、当初予定していた国境山岳地帯は、現地の雪の状況判断で早めにスウェーデン側に回避し、雨と増水、低温は慎重な行動で切り抜けることが出来た。計画通り行かない事も想定内だったし、ヘリ移動もやむなしだった。イレギュラーこそ旅の楽しさで、充分満足な第4次北極圏遠征だった。
2010年のトレッキングで国境を越える際一緒だったチェコの2人が今回も一緒に行こう!ということでメールで連絡を取りながら日程を調整していた。
キッチンで遅い夕食をとりながら、彼らが到着するまでの3日間の下見の結果Kattratからのルートから入ると報告した。
7/10 昨日の下見通りのルートでいよいよ本格的にトレッキング開始。
反対側から2人の女性と犬1匹がやって来た。どこから来たのか?と聞くと昨日Kattratから入りBaisfjord(Narvik)側に行こうとしたが雪が多く危険で引き返して来たのだという。私の下見通りの結果だった。
 Hunddals(ハンダルス)小屋まで行くと6人のボーイスカウトの集団がやって来た。長い棒は川を渡ったり雪の上を歩いたり、テントの支柱にしたりするのだという。高校生ぐらいの若者たちが何日もトレッキングしている姿に、この国のたくましさを感じる。
Hunddals(ハンダルス)小屋まで行くと6人のボーイスカウトの集団がやって来た。長い棒は川を渡ったり雪の上を歩いたり、テントの支柱にしたりするのだという。高校生ぐらいの若者たちが何日もトレッキングしている姿に、この国のたくましさを感じる。
 ここまでは前日に下見していたが、いよいよ標高を上げて山岳地帯に突入である。朝良かった天気も予報通り下り坂に向かっているようだ。今週の天気予報は全部雨だったので期待はしていないが寒さが予想される。それにしてもノルウェーの山は険しく雄大だ。
ここまでは前日に下見していたが、いよいよ標高を上げて山岳地帯に突入である。朝良かった天気も予報通り下り坂に向かっているようだ。今週の天気予報は全部雨だったので期待はしていないが寒さが予想される。それにしてもノルウェーの山は険しく雄大だ。
 天気は晴れたり曇ったりを繰り返す中、マップと時折雪の中から現れるマーキングを見ながら歩く。標高が800㍍を超えてくると周囲の湖は大半が氷結し、残雪からて流れ出す水は、行く手の大きな障害となる。マップのルートとマーキングは一致していない。とにかく渡れそうなところを捜しながら時には氷のように冷たい川をサンダルに履き替えて渡る。
天気は晴れたり曇ったりを繰り返す中、マップと時折雪の中から現れるマーキングを見ながら歩く。標高が800㍍を超えてくると周囲の湖は大半が氷結し、残雪からて流れ出す水は、行く手の大きな障害となる。マップのルートとマーキングは一致していない。とにかく渡れそうなところを捜しながら時には氷のように冷たい川をサンダルに履き替えて渡る。
 この日はOallavaggi(オワラバッギ)のシェルターに泊まる。小さいながら薪ストーブも有りぬくぬくと過ごす。
この日はOallavaggi(オワラバッギ)のシェルターに泊まる。小さいながら薪ストーブも有りぬくぬくと過ごす。
深夜0時、沈まない太陽が対岸の山肌を照らし、湖面にその姿を映す。ダイナミックな北極圏山岳地帯の白夜の風景である。
 翌日は雨のスタート。腕時計の気圧計は昨夜から下がりっぱなし。凍結した湖のほとりを次のCunojavrre(クーノヤウレ)を目指す。
翌日は雨のスタート。腕時計の気圧計は昨夜から下がりっぱなし。凍結した湖のほとりを次のCunojavrre(クーノヤウレ)を目指す。
ノルウェーの山小屋はスウェーデンと違いドアに頑丈な鍵が掛けられている。
小屋を使用するにはあらかじめどちらかのノルウエーツーリスト協会の案内所で合鍵を手に入れる必要がある。前日にNarvik駅の中にあるツーリストインフォメーションにて100クローネで手に入れていた。(この鍵はまたどこかのカウンターで返却すれば100クローネは返却される)
せっかくだからこの鍵でノルウェーの山小屋を楽しんでみたい。各小屋の使用料は、その都度クレジットカード番号と必要事項を用紙に記入して、備付けのBOXに投函する。この辺も常に管理人が常駐するスウェーデン方式とは違う。
背後にはまだまだ大量の残雪を残す山と氷結した湖。ノルウェーの山はまだ人が入ることを拒んでいるかのよう。
 Cunojavrre(クーノヤウレ)小屋前には真新しい標識が立っている。ロゴマークのNTOは90年の歴史を持つNarvik og Omegn Turistforeningの略である。
Cunojavrre(クーノヤウレ)小屋前には真新しい標識が立っている。ロゴマークのNTOは90年の歴史を持つNarvik og Omegn Turistforeningの略である。
ここでスウェーデンの国境に最接近。当初はここから国境伝いに南下しRitsemを目指す予定だった。しかし次の拠点Caihnavaggi(カイナヴァッギ)からさらに標高は上がり1,000㍍以上となる。(北極圏のラップランドでの標高は、例えば北アに換算すればプラス2,500~3,000㍍を加算した気象条件と考えてよい。)2日間を歩き終えて、このあと数十㎞もこれ以上厳しい条件、予想される悪天候の中を歩くことは不可能と判断し、プラハの2人も同意した。そこで、スウェーデン側に出てクングスレーデンを歩くことにした。国境を越えてからも大きな峠を越さなければクングスレーデンに出られないが、このまま進むよりはましである。
簡単に進めると思ったクングスレーデンにも大きな試練が待ち受ける。次回に続く。
7/7 スウェーデン最北の都市Kiruna(キルナ)まで飛行機で行き、その先は列車を使って、ノルウェーのNarvik(ナルビック)を目指した。今回は国境山岳地帯は残雪が多いと聞いていたので、入山口を決めていなかった。
初日は国境のリゾート地Riksgransen(リクスグランセン)で途中下車して周辺調査をする。晴れているのに大変寒く、後方の湖は2週間前まで凍結していたそうだ。
 入山口は隣駅のKatterjakk(カッターヤック)からだが、ここはスキー場の一部で小屋のすぐ後ろ斜面から雪がつながっている。
入山口は隣駅のKatterjakk(カッターヤック)からだが、ここはスキー場の一部で小屋のすぐ後ろ斜面から雪がつながっている。
Unna Allakass(ウナアルカス)まで30㌔のポールがあるが、全般的に標高の高い所を縫うように歩くルートなのでチョッと厳しいと思った。
 夕方の列車を待ち、Narvikに行きユースホステルにベースを置く。
夕方の列車を待ち、Narvikに行きユースホステルにベースを置く。
翌日はノルウェー側の入山口Beisfjord(ベイスフヨルド)側の踏査に出かける。
この計画が大失敗。バスは日曜日で走らない。てくてく往復30キロ以上徒歩となる。
 山に入ると目の前に立ちはだかる岩山。谷は深く切れ込み上部には、巨大な雪庇の尾根が見える。岩肌はとても滑りやすそうだしスノーブリッジも多数有るだろう。途中山道を犬の散歩に来ていたおじさんが居たので、状況を聞いてみた。毎年このルートを歩いているそうだが、今年は残雪が多く、まだ山に入ってないと言う。このルートも諦めた方が良さそうである。
山に入ると目の前に立ちはだかる岩山。谷は深く切れ込み上部には、巨大な雪庇の尾根が見える。岩肌はとても滑りやすそうだしスノーブリッジも多数有るだろう。途中山道を犬の散歩に来ていたおじさんが居たので、状況を聞いてみた。毎年このルートを歩いているそうだが、今年は残雪が多く、まだ山に入ってないと言う。このルートも諦めた方が良さそうである。
 翌日は最後の候補地Katterat(カテラート)からのルートを踏査する。
翌日は最後の候補地Katterat(カテラート)からのルートを踏査する。
Narvikから列車でスウェーデン国境手前まで戻る。この日も天気は良いのに駅の外壁に取り付けてある寒暖計で見てみると、AM11時で気温10℃と寒い。
 こちらのルートは快適。最初の10キロはダブルトラックのルートである。
こちらのルートは快適。最初の10キロはダブルトラックのルートである。
昨日Beisfjord側から見た山々を反対側から眺める。
その先は雪が深そうだが、3日間の現地踏査の結果、Katteratルートで国境山岳地帯に入ることに決定。
ここまではうそみたいに穏やかな天候に恵まれた。この時は、その後とんでもないことが起こることも知らずに・・・。次回へ続く
という情報が届いた。
2007年には北欧は異常な暖冬で2月に雨が降り、その後大地が凍ったためにトナカイが数千頭餓死するという事態を引き起こした。
心配でさっそくサーメ人の友人パーレにラップランドの情報を聞いてみたらトナカイは大丈夫との事で一安心。しかし今シーズンは2ヶ月遅く昨年12月に雪が降り始めたり、先週は-40℃、今日は-12℃で暖かく、寒暖差が激しいということだった。
上の図は今日の北半球のジェット気流の流れだが、時計の6時方向がグリーンランドから大西洋。大きくえぐりこみように気流の蛇行が見られるのが今シーズンの特徴。そのせいか真反対にある日本には寒気が流れ易くなっている。
この流れはメキシコ湾流に似ている。メキシコ湾流は世界の気象に影響を与えるのでは?と最近研究されている。
ジェット気流もメキシコ湾流型になると世界に異常気象をもたらすのかも?