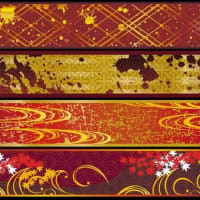琉球時代の交易品として人気のあった夜光貝をご存じでしょうか?
熱帯から亜熱帯域のインドから 太平洋区のサンゴ礁域に生息する大型の巻貝です。日本近海では屋久島・種子島以南のあたたかい海域に生息しています。生息域は水深30m以浅の比較的浅い水路や岩のくぼみであり、砂泥質の海底にはいないようです。基本的に夜行性のようで、重厚な殻の裏側に真珠層があって、研ぎ出すと美しい煌めきが出るので、それもあって「夜光貝」と呼ばれているのかと思っておりましたら、どうもそれは違うようで、もともとの名前の由来は、屋久島から献上されたことから「ヤクガイ(屋久貝)」と呼称されていたようです。それが転じてヤコウガイになったとか。貝の真珠層の美しさから、夜光貝の字を当てたのかもしれませんね。名前から暗闇で光ると思われがちですが、貝自体が発光することはありません。
貝の肉は刺身や煮物として食用にされますが、その外側の貝殻は磨けば美しい真珠層が出てきます。それがこちらです。

右の貝は表面を削る前の状態。左は研いだあとに出てきた真珠層です。
こんなに美しい真珠層がゴツゴツした表面の下にあるなんて、ちょっと驚きですね。これを発見した昔の人は凄いですね。
ちなみにこの貝は、沖永良部島の海で捕れたものです。知り合いの方が、私の勉強の為にとご自分で海に潜って獲られたものを、わざわざ送ってくださいました。実物を目にするとやはり実感が沸くし、美しさが伝わります。大変感謝です!
そしてこの夜光貝の真珠層を加工したものが、琉球時代の交易で大変な人気だったようです。夜光貝の殻を使った美しい螺鈿(らでん)漆器などを作って輸出していました。夜光貝は屋久島より南でしか採れない琉球の特産品で、琉球王国の螺鈿は非常に美しいことから、中国などで人気が高かったようです。
その作品がこちらです。

浦添市美術館のパンフレットより
真珠層の部分を薄く切って、それを図柄にカットして漆に張り付けて美しい模様を作っていたようです。非常に手間がかかりそうな工程ですが、高級感がありますのできっと良い値で取引されていたのではと思います。
他にも髪飾りやアクセサリーに加工されていました。
琉球時代の交易品の材料であった夜光貝。沖永良部島でも捕れますので、遥か昔から島の収益の品の一つだったのでしょう。まさしく海の恵み、海からの宝ですね。
ちなみに、美しく輝く夜光貝の中にライトを入れれば、幻想的な光を放つランプになります。昔の人たちもロウソクなどを入れて使っていたかもしれませんね。