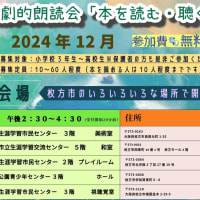「ほどく、ゆるめる」という意味のようです。
実はたびたびお名前を出している岩井俊二監督の作品に「undo」というものがあって、その内容からいくと縛るの様な気がしていました。
転じて作品創造における制限事項の逆のよい効果について書こうかと思っていましたが、違っていたのでむしろ身体論に近くなるかな、と思っています。
僕がよく思うのは、演劇とはいえスポーツと全く同じで、身体的なトレーニングが必要だということです。
もっと詳しく言うと、日常生活でやっていることを意図的にやるのが演技だから、自分の身体を自由に動かせることが重要になってきます。
立つことや座ることを実際に細分化してよく視ていくと、実に複雑な動きです。
どこかを怪我するととてもそのことが良く分かったりします。
足の親指をどこかにぶつけただけでも、歩くのがとたんに難しくなったりしますよね。
ですから、スポーツでの良い状態、というのは演劇でも良い状態で、例えばスラムダンクで出てきた表現ですが、「熱しすぎず冷めすぎず、ほどよい興奮状態」というのを保てることが大事です。
もうちょっと演劇寄りの言葉で表現すると緊張しすぎず、リラックスしすぎず、という状態です。
実際には、舞台上に上がると普通誰でも若干緊張します。
と、いうことは身体も硬くなっているわけで、そうすると自分の思うように、脳が命令するとおりに、演出が言うように、演出の言葉で自分の脳裏に描かれたイメージどおりには、なかなか身体が言うことを聞きません。つまり動かせません。
それで、ワークショップなどでは、最初にストレッチをやったり身体をほぐしたり暖めたりするアップ作業をやります。
ひょっとして演劇の稽古場の風景などを撮った写真を(最近はアイドルが出ている舞台も多いですしね)見てみて、なんでみんなジャージなんだろう、と不思議に思われた方がいるかもしれません。
あれは、動きやすい服装の方が身体に緊張を強いないからです。
そして最初にやるそうしたアップのためでしょうね。
実際ストレッチで始まる稽古場は多いでしょうし、僕も稽古時間の最初の30分は基本的にアップの時間にしています。
この間、少しだけお邪魔した高校の演劇部ではストレッチをみんなでしていました。
1,2,3,4とまるで運動部のようにされていました。
ちなみに、ぼくがよくやるのは「脱力」というワークと「わかめ体操」というワークです。
どちらもペアワークですが「脱力」は片方が仰向けに寝転がります。
そしてもう片方が腕や足を持ち上げて、身体の力が十分に抜けているかを確認していきます。
物理的な重力に反するというアクションを抜いてやれば、身体に入れている力を抜きやすくなるからです。
「わかめ体操」は、一方がわかめになり、もう一方が波になります。
わかめは波に触れられることで波に揺られていきます。
まあ、これらは実際にやったほうがわかりやすいので説明を大雑把にしましたが、
要は、「脱力」の立ったバージョンです。
身体を緩めすぎると立ってはいられないので、軽やかに自由に動ける身体の状態になることが目的です。
もちろんこのとき、アクションとリアクションの関係に波とわかめはなっているので、単純なワークではなくて演劇の下地作りにもなっています。
「脱力」も人間の身体の造りを知ってもらう目的もあります。
外側と内側と両方で。
これらのワークをやるときに意外に大切なのは、事前に心も少しほぐしておくことです。
実際にいきなりこれらのことをやれって言われると、少し面食らうと思います。
演劇をすると思ってきたのに、何で?ってなりますし、そもそも他の人に身体を触られる、また触るという行為自体が緊張しますよね。
なので、シアターゲームをやったり、なんだか少し話をしてくだけた雰囲気を作ってからそれに臨みます。
まあ、どうやったら人の心がほぐれるかって言うのは、なかなか百発百中の理論はないですけども。
心と身体って結びついてるんだなあ、といつもこのワークをするときには思います。
最近の「演出家の眼」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事