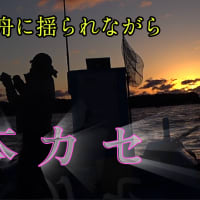論語を現代語訳してみました。
子罕 第九
《原文》
子曰、後生可畏。焉知來者之不如今也。四十五十而無聞焉、斯亦不足畏也已。
《翻訳》
子 曰〔のたま〕わく、後生〔こうせい〕 畏〔おそ〕る可〔べ〕し。焉〔いずく〕んぞ来者〔らいしゃ〕の今に如〔し〕かざるを知らんや。四十・五十にして聞こゆること無きは、斯〔こ〕れ亦〔また〕 畏るるに足たらざるなり。
《現代語訳》
孔先生がさらに、次のように仰られました。
〈顔回の志しをこの私が引き継ぎ、そして私の志しを、弟子のうちの誰かが引き継いていくのだから、〉これから世に立とうとする人を侮〔あなど〕ってはならぬな。
そして、どうしてこれから世に立とうとする若者が、いまの現役の者たちよりも劣っているなどといえようか。
そんなことよりもだ、〈現役の者で〉よわい四十・五十となってなお、謙虚にして、〈声なき声に〉耳を傾けようとしないのであれば、これまた畏るるに足りぬわな、と。
〈つづく〉
《雑感コーナー》 以上、ご覧いただき有難う御座います。
この語句も、かなり有名な語句のひとつですが、『後生』に関しては、世の中すべての「これから世に立とうとする人」ではなく、孔子はあくまで、自分の志しを引き継いでくれるであろう弟子たちに対して述べたことばとして訳してみました。
とくに、孔子が抱えた弟子というのは、子路や顔路(顔回の父)などの古参の弟子とは、年もそれほど離れていませんでしたが、それ以外の多くの弟子というのは、30才から40才ほども年の離れた若者が中心だったようです。
ですから、孔子からいえば息子や孫同然ともいえる弟子ばかりでしたから、そのような中には、孔子死後、自分よりも優れた弟子が出てくるかもわからない、という意味合いも込められていたのかもしれませんし、また、そうした期待をも込めた、弟子たちに対する孔子からの叱咤激励のことばだったのかもしれません。
そして、そんな若い弟子たちが四十・五十になったとき、そのまた若い弟子たちに対しては謙虚な心でその話に耳をかたむけること、さらには民との交わりのなかでは貧しくとも心豊かに暮らしている人であったり、苦悩に絶えないでいる人、また、自然界においては水の流れや風のささやきや小動物などのさえずりなど、こういった「声なき声にも耳を傾けるように…」と伝えたかったのかもしれません。
※ 孔先生とは、孔子のことで、名は孔丘〔こうきゅう〕といい、子は、先生という意味
※ 原文・翻訳の出典は、加地伸行大阪大学名誉教授の『論語 増補版 全訳註』より
※ 現代語訳は、同出典本と伊與田學先生の『論語 一日一言』を主として参考