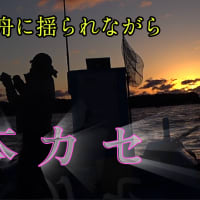論語を現代語訳してみました。
子罕 第九
《原文》
子謂顔淵。曰、惜乎。吾見其進也、未見其止也。
《翻訳》
子 顔淵〔がんえん〕を謂〔い〕う。曰〔のたま〕わく、惜〔お〕しいかな。吾〔われ〕 其〔そ〕の進むを見るも、未〔いま〕だ其の止〔や〕むを見ざりき、と。
《現代語訳》
孔先生はまた、〈川の流れを目で追われながら、〉次のように仰られました。
まこと顔回の死は、口惜しいかぎりだ。
私は、彼が志すものに向かって慢心する姿をこの目にしたが、〈死んでなお、その志しは私に引き継がれ、〉彼はいまだ、立ち止まることがないのだよ、と。
〈つづく〉
《雑感コーナー》 以上、ご覧いただき有難う御座います。
所詮は、自分の解釈でしかないことは重々承知しておるのですが、なんとも切ない気持ちになってしまいました。
さて、今回の語句を訳するにあたっては、高齢となった孔子は、その身に大道を得たことによって、純粋に死というものを意識しだしたのだと思われます。そして、死ねばその肉体(魄)は朽ち果てますが、しかし "志し(魂)" だけは引き継がれていくと強く感じるようになっていったのではないでしょうか。
今回の語句を語訳していて、改めて弟子の存在とは何なのか?ということを考えさせられます。
※ 孔先生とは、孔子のことで、名は孔丘〔こうきゅう〕といい、子は、先生という意味
※ 原文・翻訳の出典は、加地伸行大阪大学名誉教授の『論語 増補版 全訳註』より
※ 現代語訳は、同出典本と伊與田學先生の『論語 一日一言』を主として参考