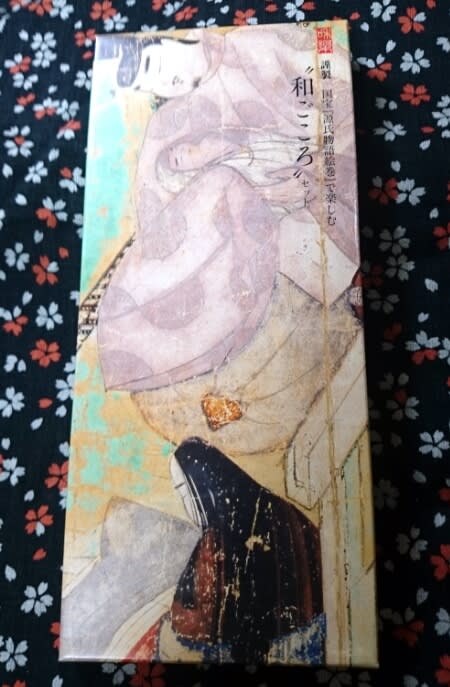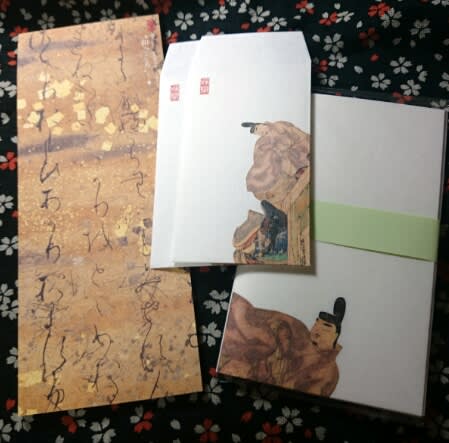百人一首に関する本のご紹介です。

先日、
西東社から発売された本
小学生おもしろ学習シリーズ
「まんが百人一首大辞典」を読みました。
※西東社
⇒
http://www.seitosha.co.jp/
⇒
http://www.seitosha.co.jp/2_3974.html

 小学生おもしろ学習シリーズ まんが 百人一首大辞典
小学生おもしろ学習シリーズ まんが 百人一首大辞典
シリーズ名にある通り、小学生を対象にされている本です。
小学生が最初に出会う百人一首の本として素晴らしいと思います。
監修は、同志社女子大学教授で
小倉百人一首殿堂「時雨殿」の館長でも
いらっしゃる吉海直人先生。

大人も楽しめる一冊です。
私も小学生の時にこんな本に出会いたかったです!
暗唱のコツも書かれていて便利です。
定価1,000円(税別)と良心的。
オールカラーの漫画で見開きページで
歌と作者について紹介されています。
漫画は6人の漫画家さんによって描かれています。
百人一首の歌人たちがそれぞれ美麗な絵の漫画で楽しめます。
6人の漫画家さんのうちの
お一人がTwitterでフォローさせていただいている
ROUTE175(@route175 )さん こと 藤岡ひろみさんでもあります。
本の途中にある『平安王朝新聞』のページも
勉強になりおもしろいです。
小学生おもしろ学習シリーズ 「まんが 百人一首大辞典」を読む前、
実は「百人一首」に関する本ってすでに出尽くしているのでは?
という感もあったのですが、こういうアプローチもあるのですね。
楽しく読ませていただきました。



⇒
webサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』
⇒
webサイト『花橘亭~源氏物語を楽しむ~』
⇒
Twitter
⇒
Instagram
<コメントをくださる方は
掲示板へ。>
 web拍手ボタン
web拍手ボタン
☆チェック!:
Amazon/源氏物語の関連本
 京都市下京区にある風俗博物館のこと。
京都市下京区にある風俗博物館のこと。



 着装体験。
着装体験。

 web拍手ボタン
web拍手ボタン





























 女房の身嗜み・髪について
女房の身嗜み・髪について






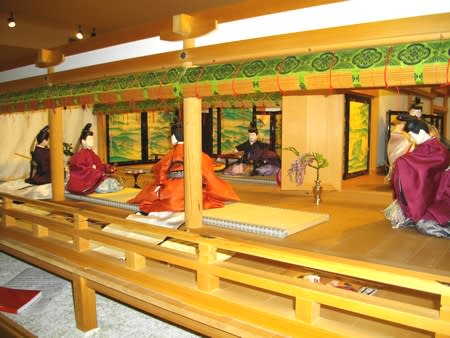

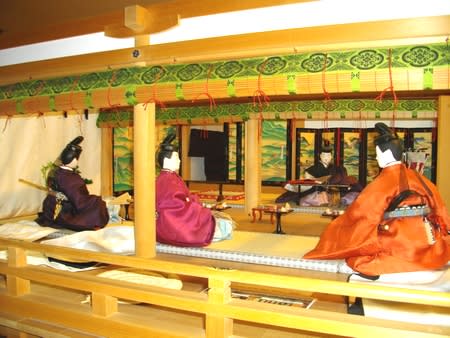


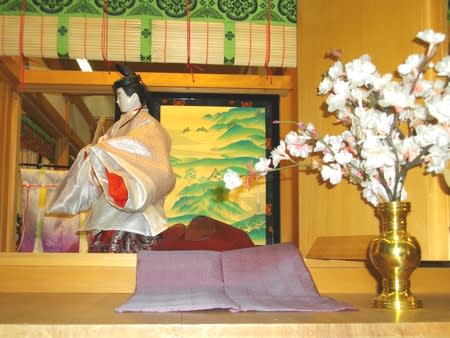
























 春鶯囀(しゅんのうでん)
春鶯囀(しゅんのうでん)





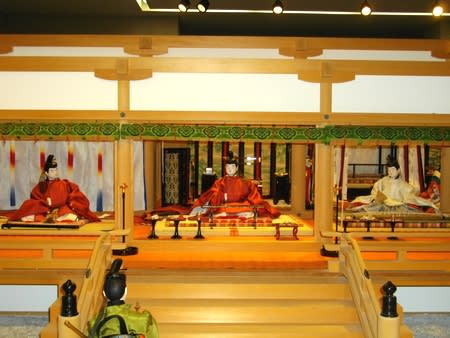


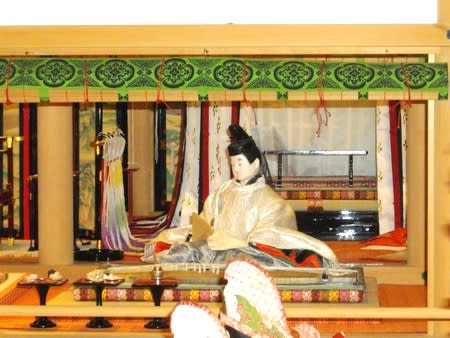


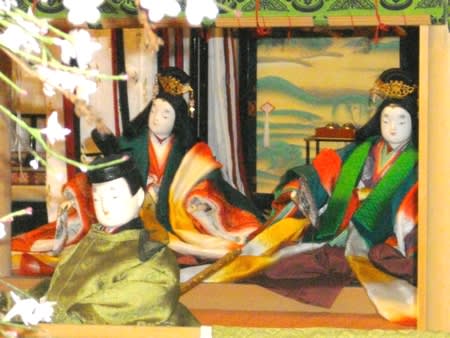
 百人一首に関する本のご紹介です。
百人一首に関する本のご紹介です。