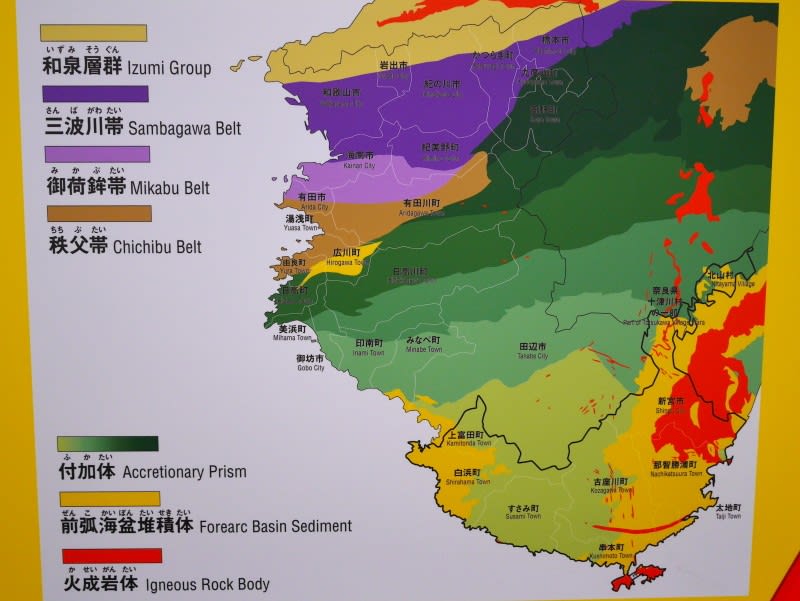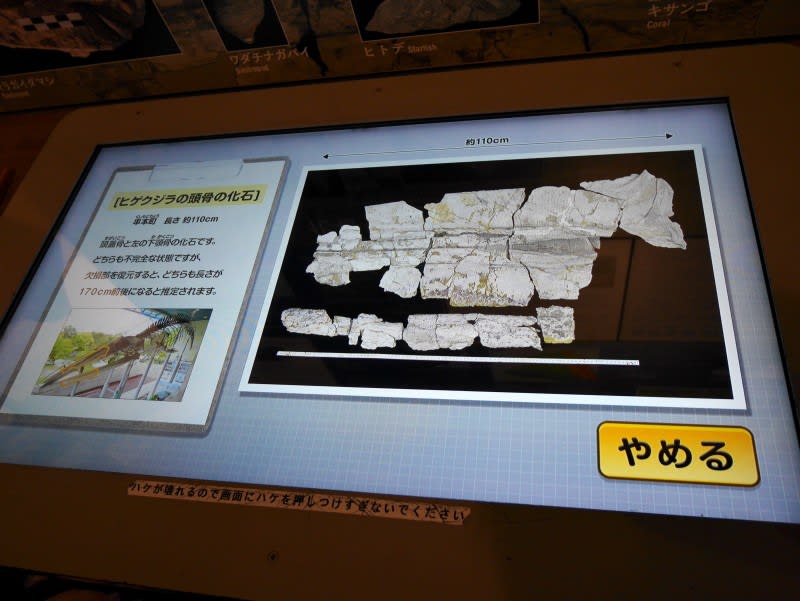今月から使いだした望遠コンデジで、まずは広角・・

手前の船をアップ・・

右端の船と奥の橋・・

デジタルズームも使って、換算2000mm?
軽くて楽しい。。

いつもの干潟で・・・謎の黄色い粘液状のもの・・・なんだこれ?

低潮線近くの石の上に点在していた。アメリカフジツボらしき残骸の周りにも少しだけついていたり・・

ナミマガシワの近くの単独フジツボの残骸には塗装のように周りについてたり・・

拡大すると・・どうも卵塊か卵のうという感じ。。
1週間、図鑑やネットを探しているものの、未だ不明。
ウミウシ・巻貝・ゴカイ・ヒラムシ等々・・・徘徊性だと思うのですが・・・(通い詰めて、何が出てくるかを見るにも小さすぎるか。。)

イボニシもホットスポット的に集結していて・・

近くには多くの卵塊が産み付けられている・・
色は似ているけど、粘液状な卵のうは、ゴカイ・ウロコムシ・イソメ系か・・?

アゴハゼか・・? 春は稚魚も多い季節。

フサギンポの仲間か? ハゼやギンポの仲間も、さっぱり区別がつかない。

たくさんいるのを・・

拡大・・ボラだった。。

干潟を歩くと、多くの稚魚たちは海の方へ逃げるけど、引き潮時に心配になるくらい浅い所に留まるハゼ科も写真での同定不能。
黒いのはチチブなどのダボハゼ系?とか・・(写真のはミミズハゼか?)

細長いのは、ミミズハゼの仲間?とか・・

マハゼっぽい色合いのは、一旦全部、ヒメハゼにしたくなるけど・・何なんだろうか???

この感じのは、もぅ、全部、アゴハゼ・・と決めつけている・・我ながら無茶苦茶だと思う。。
きっと、名前も知らないような種や、外来種もたくさん混じっているんだろうなぁ・・と思う。
自分の無知さはさておき、こんな何でもあり的に、どこからでも次々と稚魚が出てくるのが、海の豊かさだと思う。
透明な水にきれいな魚が泳ぐ水族館では味わえない感覚だ・・

タカノケフサイソガニ・・だと思う。この干潟では結構多数派。

写真が微妙だけど・・イソガニか・・?
少ない水分からより多くの酸素を取り込むためとかいうけど・・・単純に泡ぶくぶくのカニを見ると嬉しい。

とても分かり難いけど・・・真ん中のカニのハサミの破片に、ヤドカリが入っていた。

アオサギ・・・干潟の生き物の最大の敵か・・?

ミドリイガイ・・随分と少なくなったように感じる。

コツブムシの仲間・・ここで見るのは地味な色合いのばかり。キラキラと輝く系を見たい・・

見慣れないイトカケガイの仲間と思われる貝殻に入るユビナガホンヤドカリ・・
こんな貝が棲んでいると嬉しいけど・・外来種のような気がする。。

タテジマイソギンチャク・・干上がった時は、体の中に水を貯めているので、微妙な形のも結構いる。

イソギンチャクは、クラゲを逆さまにしたようななもの、と紹介されるけど・・・こいつは、そのままクラゲに見えるぞ。。
どうでもいい話ですが・・・スマホの機種変から、いろいろと悩ましい日々を過ごしております。
公財)水産無脊椎動物研究所のツイッターにリツイートされていた、 『磯の生き物図鑑』の新刊が来月中旬に発売されるらしい・・・個人的に一押しの図鑑なので、従来よりも100種増はとても楽しみだ。
以上、本日もご覧いただき、ありがとうございました。