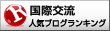◯『般若心経』の流布
敦煌の石窟寺院から発見された、石板に彫られた般若心経があります。これに「この経は玄奘三蔵がインドへ行く途中、益州の空恵寺で天然痘にかかったインド僧から看病のお礼に教えてもらった」とあります。また「この経は旅に利益がある」と書いてあります。玄奘はインドへ旅立つとき十六人の仲間の僧侶がいましたが、中国へ帰ってきたのは彼ただ一人でした。艱難に出会ったときは般若心経を唱えて乗り切ったのです。だから「旅にご利益のある経文」です。当時に比べ、安全に旅ができる今日ではそのように考える人はないでしょう。
禅の道場では般若心経を一日に6~7回、朝の勤行や食事のときなどで唱えます。この経文はどのような内容が書いてあるかというような講義はありません。その理由は「自我を捨てるための経典」だからです。理屈抜きに唱える、それが禅の立場です。
法隆寺(現在東京国立博物館所蔵)にインドからもたらされた世界で最も古い写本の般若心経が残されています。これはインドの僧侶が6世紀の初めごろ書写し、インドから中国・梁に禅を伝えたボダイ・ダルマが中国にもたらし、その後、遣隋使船で7世紀初め日本にもたらされました。私たちが唱えている玄奘三蔵翻訳の般若心経は最初に題名があります。しかしこのサンスクリット本に題名はありません。題名すら省かれている経典です。それは何を意味するのか。「自我を捨てるための経典」だからです。
◯『大般若経』
『大般若経』は600巻、20万頌、文字数にして数百万字にも及びます。その中の第578巻は「理趣文」と呼ばれ、密教の流れを汲む経典です。禅は800年前までは密教寺院の中にありましたので、現在も禅宗各寺院では正月に世界平和と檀信徒の健康、五穀豊穣を祈って「大般若祈祷会」を催しています。そのなかに次のような言葉があります。
諸法は皆これ因縁によって生ず。因縁によって生じるが故に自性なし。自性なきが故に去来なし。去来なきが故に畢竟空なり。畢竟空が故にこれを般若波羅蜜と名づける。
「ここに存在しているすべてのものは、因(たね)とそれをとりもつ縁によって生じる。それだから自分のものは何もない。自分というものはないので、去来するという事はない。去来する事はないので、究極の空である。究極の空だから般若波羅蜜と名付ける」
「般若」は自我を捨てることだと、前項で述べました。そのことについて仏陀は度々、弟子たちにこのようなたとえを説かれました。
「川が増水していて向こう岸に渡れなかったとしよう。ある人は上手にイカダを作って、これで増水した川を渡ったのち、このイカダを担いで歩くだろうか。その人はそのイカダを捨てるであろう。たとえばそのように、正しく説かれた法も捨てなければならない。いうまでもなく非法はなおさらのことである」『中阿含経』55『大般若経』577より
『金剛経』に「ブッダは常に弟子たちにこの話をした」とあります。このたとえは「空」の教えとしてよく理解できます。ブッダは「これを信じなさい」などとは説かずに「捨てよ」と説かれました。これは仏教の大きな特徴であり、とりわけ禅宗の基本的な教えだといえます。

●坐禅会 毎週土曜日午前6:25~8:00 久留米市宮の陣町大杜1577-1圓通寺
初心者歓迎 参加費無料 詳細は電話でお問い合わせください。℡0942-34-0350
初回参加者は6:15までに来てください。
●学校やクラブなど団体研修 坐禅申し込み随時うけたまわります。出張も致します。
費用はご希望に応じます。宿泊はありません。出張講座もいたします。