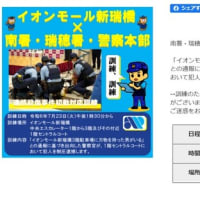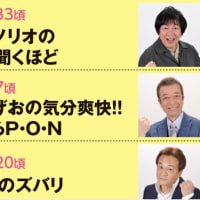分煙の議論をしたいならまず受動喫煙の害を認識しよう
アピタル・酒井健司2016年9月5日 朝日新聞より
世界中の複数の集団において、家庭や職場で他人の吸った煙にさらされる人は、そうでない人と比較して、肺がんになりやすいことは、以前から知られています。今回の報告では、メタ解析(メタアナリシス)という手法を使って、日本人においても確かに受動喫煙が肺がんを増やすことが示されました。
肺がんを増やす程度(「相対リスク」)も約1.3倍という、世界のほかの集団の研究と整合性のある結果です。喫煙の害に関する多くの証拠の山に、また一つ証拠が追加された、というわけです。受動喫煙が肺がんのリスクであることについて、専門家の間で議論はありません。
私はたばこを吸いませんし、たばこの煙は好きではありません。しかし、受動喫煙を絶対に避けているわけではありません。たばこを吸う友人とお酒を飲むことだってあります。受動喫煙の害よりも、友人との楽しい時間のほうが私にとって大切です。そもそも、ときたま受ける受動喫煙の害よりアルコールの害が大きいでしょう。
私の健康ではなく、友人自身の健康のためにたばこを止めて欲しいのですが、それは友人が自分の責任において決めることです。たとえ有害であってもたばこを吸い続けるという選択の自由はあります。これは個人の価値観の問題です。
しかしながら、受動喫煙となると話が違ってきます。私のように「たまの受動喫煙は許容する」という人ばかりではありません。たとえ小さくても肺がんリスクが気になる人もいるでしょうし、あるいは気管支喘息(ぜんそく)などの急性の健康被害が生じる人もいるでしょう。健康被害はともかくとしてたばこの臭いが嫌いな人だっています。害を承知でたばこを吸うかどうかは自分の責任で決めていいとしても、他人に害を与えることは慎まなければなりません。公共の場所では、受動喫煙が起こらないよう喫煙は制限されるべきです。煙は漂ってきますので、屋内での分煙は意味がありません。
ただ、例外なく屋内の全面禁煙化をすべきかどうかは議論があってもいいと思います。たとえば、居酒屋は必ずしも公共の場所とは言えません。たばこを吸いながらお酒を飲みたい人もいます。受動喫煙が嫌な人は「喫煙可」の居酒屋に行かなければいいわけです(ただし、居酒屋の従業員に対して配慮は必要です)。
いずれにせよ、受動喫煙には害があるという認識が共有された上で議論されるべきです。しかし、JT(日本たばこ産業株式会社)は、今回のがんセンターの報告に対して、「疫学研究だけの結果をもって喫煙との因果関係を結論付けられるものではありません」と述べています。
( https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/opinion/fsc_report/20160831.html )
はっきり言えば、JTの見解は現代医学の常識から外れています。会社の方針として、
なるべく喫煙の害を小さく見積もりたいのかもしれませんが、
複数のメタ解析が示しているのに受動喫煙の害を認めないのは無理があります。
そろそろ、受動喫煙の害を認めた上で、どのように
分煙をすべきかという議論を行う段階だと思います。
<アピタル:内科医・酒井健司の医心電信・その他>
http://www.asahi.com/apital/healthguide/sakai/
(アピタル・酒井健司)
アピタル・酒井健司2016年9月5日 朝日新聞より
世界中の複数の集団において、家庭や職場で他人の吸った煙にさらされる人は、そうでない人と比較して、肺がんになりやすいことは、以前から知られています。今回の報告では、メタ解析(メタアナリシス)という手法を使って、日本人においても確かに受動喫煙が肺がんを増やすことが示されました。
肺がんを増やす程度(「相対リスク」)も約1.3倍という、世界のほかの集団の研究と整合性のある結果です。喫煙の害に関する多くの証拠の山に、また一つ証拠が追加された、というわけです。受動喫煙が肺がんのリスクであることについて、専門家の間で議論はありません。
私はたばこを吸いませんし、たばこの煙は好きではありません。しかし、受動喫煙を絶対に避けているわけではありません。たばこを吸う友人とお酒を飲むことだってあります。受動喫煙の害よりも、友人との楽しい時間のほうが私にとって大切です。そもそも、ときたま受ける受動喫煙の害よりアルコールの害が大きいでしょう。
私の健康ではなく、友人自身の健康のためにたばこを止めて欲しいのですが、それは友人が自分の責任において決めることです。たとえ有害であってもたばこを吸い続けるという選択の自由はあります。これは個人の価値観の問題です。
しかしながら、受動喫煙となると話が違ってきます。私のように「たまの受動喫煙は許容する」という人ばかりではありません。たとえ小さくても肺がんリスクが気になる人もいるでしょうし、あるいは気管支喘息(ぜんそく)などの急性の健康被害が生じる人もいるでしょう。健康被害はともかくとしてたばこの臭いが嫌いな人だっています。害を承知でたばこを吸うかどうかは自分の責任で決めていいとしても、他人に害を与えることは慎まなければなりません。公共の場所では、受動喫煙が起こらないよう喫煙は制限されるべきです。煙は漂ってきますので、屋内での分煙は意味がありません。
ただ、例外なく屋内の全面禁煙化をすべきかどうかは議論があってもいいと思います。たとえば、居酒屋は必ずしも公共の場所とは言えません。たばこを吸いながらお酒を飲みたい人もいます。受動喫煙が嫌な人は「喫煙可」の居酒屋に行かなければいいわけです(ただし、居酒屋の従業員に対して配慮は必要です)。
いずれにせよ、受動喫煙には害があるという認識が共有された上で議論されるべきです。しかし、JT(日本たばこ産業株式会社)は、今回のがんセンターの報告に対して、「疫学研究だけの結果をもって喫煙との因果関係を結論付けられるものではありません」と述べています。
( https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/opinion/fsc_report/20160831.html )
はっきり言えば、JTの見解は現代医学の常識から外れています。会社の方針として、
なるべく喫煙の害を小さく見積もりたいのかもしれませんが、
複数のメタ解析が示しているのに受動喫煙の害を認めないのは無理があります。
そろそろ、受動喫煙の害を認めた上で、どのように
分煙をすべきかという議論を行う段階だと思います。
<アピタル:内科医・酒井健司の医心電信・その他>
http://www.asahi.com/apital/healthguide/sakai/
(アピタル・酒井健司)