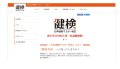受動喫煙防止 「最低レベル」脱出図れ
静岡新聞社説より
Mヨミ週間ダイジェスト社説一気読み
【18日】受動喫煙防止 「最低レベル」脱出図れ
厚生労働省の有識者による検討会は喫煙の健康影響に関する報告書
(たばこ白書)をまとめた。受動喫煙の危険性を強調し、
公共施設や飲食店など不特定多数が利用する屋内の全面禁煙を提言する。
受動喫煙に起因する死者は、年間約1万5千人と推計されている。
これは交通事故死者の3倍以上の数字だ。日本の受動喫煙防止対策は
世界保健機関(WHO)の判定で「最低レベル」。WHOと
国際オリンピック委員会(IOC)が推進する「たばこのない五輪」に
呼応して、近年の五輪開催都市は屋内禁煙を法や条例で定めている。
2020年東京五輪を控えた日本も法規制実現への議論を急ぐべきだ。
白書は、データの分析から喫煙と病気との因果関係を「十分ある」
「示唆している」など4段階に分けた。受動喫煙では、肺がんだけでなく、
心筋梗塞や脳卒中、小児ぜんそく、乳幼児突然死症候群などとの
因果関係が「十分ある」と判定された。
国内では健康増進法や労働安全衛生法の一部改正で受動喫煙防止が
努力義務となり、学校や病院、官公庁の禁煙化は進む。だが飲食店などは
自主性に任され、喫煙室を設けても煙の漏れは防げず、清掃や接客で
従業員が受動喫煙するリスクが残されている。防止に向けて条例を定めた
自治体は神奈川県や兵庫県など一部に限られる。白書は「喫煙室を
設置することなく屋内の100%禁煙化を目指すべき」と提言した。
14年までに先進国を含めた49カ国は屋内全面禁煙とする罰則付きの
法規制を施行済みという。もはや世界の大勢であるという認識を持つべきだ。
東京都は前知事が屋内での全面禁煙対策を盛り込んだ条例制定に
積極的な意向を示したが結局、見送った。屋内全面禁煙が進まない理由には、
飲食店などに「売り上げが減る」といった懸念が根強いためとみられている。
しかし白書は、国際的な研究成果から
「全面禁煙化によるマイナスの経済影響は認められない」とした。
静岡県が県内の飲食店や宿泊施設などを対象にした13年の調査では、
受動喫煙防止の対策実施後の利用客や売り上げへの影響は、
62%が「変わらない」と答えた。「増えた」は2・7%、
「減少した」は6・5%だった。対策導入の理由はサービス向上が
トップで、健康への悪影響などが続く。
喫煙の健康影響は、医療財政にも大きく関わる。がんなど
治療期間が長期にわたる疾病患者を減らすことができれば
医療費負担の軽減につながるはずだ。
そうした意味からも受動喫煙対策の強化を考えたい。