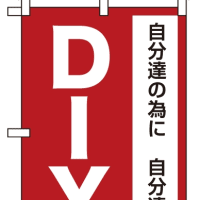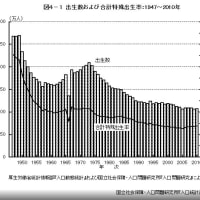ミャンマーにおける反政府運動の象徴的存在として有名なアウン・サン・スー・チーと日本との繋がりは、意外に知られていないのではないだろうか。スー・チーは、インド大使に任命された母・キンチーと共にデリーに居住し、デリー大学で学んだ。その後、英国のオックスフォード大学やロンドン大学に留学し、オックスフォード大学での後輩にあたる英国人のマイケル・アリスと結婚している。インド、ミャンマーとも英国の旧植民地であり、こうした経歴を見れば、英国と非常に関係が深いことがわかるスー・チー氏だが、実は、1985年から86年にかけて、京都大学東南アジア研究センターに研究員として在籍している。その目的は、日本との関係を無くしては語ることができない父、アウン・サンの調査・研究のためであった。
「ビルマ独立の父」として今もミャンマー国民に尊敬されているアウン・サンが民族運動に直接関わるようになったのは、当時、学生運動が盛んだったラングーン大学(現ヤンゴン大学)に入学してから3年程たった1935年以降のようである。アウン・サンが大学の自治会が発行する機関誌の編集長だった時、この機関誌に掲載された一つの記事が当時の学長を暗に批判したものだったことから大学側はその記事の執筆者を探し出そうとした。しかし、アウン・サンは「報道の倫理」を理由に決してその名を明かさなかった。そのため、大学側はアウン・サンに3年間の停学処分を下したが、それは、アウン・サンの先輩であり自治会の委員長であったウー・ヌ(後のビルマ初代首相)に対する退学処分をきっかけに始まっていた学生ストライキの火に油を注ぐこととなった。このストライキは学長の辞任、処分の停止や様々な大学改革の実現を勝ち取っただけでなく、全ビルマ学生同盟(ABSU)という全国的な学生組織の結成や、学生運動と民族運動が直接合流する契機となった。学生リーダとして広く名を知られることとなったアウン・サン氏は、後に、ラングーン大学の自治会とABSU両方の委員長に就任する。そして、1938年10月には、民族・反英運動を展開していたタキン党に、ウー・ヌと共に入党。ビルマの独立のために本格的に活動を展開することとなる。
アウン・サンは、入党後間もない1938年11月に、いきなり、事実上の党内ナンバー2である書記長に抜擢される。翌39年9月にドイツのポーランド侵攻により第二次世界大戦がヨーロッパで勃発すると、アウン・サンらは反植民地運動を推し進める好機ととらえ、他の政治勢力と共に統一戦線「自由ブロック」を結成、アウン・サンはその書記長にも選ばれた。こうした独立運動に対し、イギリス官憲や、ビルマ(1937年に英領インドから分離して英国の直轄植民地となった)当局は取り締まりを強化。自由ブロック議長のバー・モウ(直轄植民地ビルマの初代首相(1937年4月~39年2月))を始めとする幹部を次々に投獄した。そのため、逮捕を逃れたアウン・サンらは、地下に潜って活動を続けた。
「自由ブロック」は反英運動として大規模な集会やデモを繰り返す一方、リアリストのアウン・サンらは、独立を勝ち取るためには外部からの支援を得ることが不可欠であるとも考えていた。スー・チーによるアウン・サンの伝記によれば、アウン・サンは「民族主義者がゲリラ活動を展開するには武器を手に入れることが必要だ」と強く主張したという。ビルマに隣接する大国と言えば中国とインドであり、自然の成り行きとして、アウン・サンらは、先ず、中国国民党、中国共産党、そしてインド国民会議派から武器の援助を得ようと接触を試みた。しかし、当時の中国国民党政府は日本と戦っている最中であり、米英から援助を受けている立場にあった。また、ビルマと同様に独立運動を展開していたインド国民会議派に、アウン・サンらの運動を支援する余裕はなかった。そのため、中国共産党との接触を図るべく、スー・チーによれば「地下活動を身をもって実践していた唯一の人間だった」アウン・サンは、同志のタキン党員ラ・ミャインと共に、1940年8月、ビルマを密出国し、中国のアモイに向かった。
アモイの共同租界地に到着したアウン・サンらは、中国共産党との接触を試みるが、不成功に終わる。代わりに、アウン・サンらに接触してきたのは日本の憲兵隊であった。そして、二人は、当初の計画にはなかった日本行きを決意し、「面田紋二」(アウン・サン)、「糸田貞一」(ラ・ミャイン)という偽名で、1940年11月、東京・羽田空港に到着。そこで、鈴木敬司・陸軍大佐の出迎えを受けた。鈴木敬司こそ、アモイ租界地の憲兵隊にアウン・サンらを探し出すよう要請した人物であり、当時は「日緬協会書記兼読売新聞記者・南益世(みなみ・ますよ)」という偽名の下、ビルマでの工作活動を展開していたのであった。
(続く)
※この原稿は、榛葉賀津也参議院議員の政策秘書時代に書いたものです。敬称略。
お読み下さり、ありがとうございます。