ネタ切れという事もあって、かつて主宰していた鉄道廃線跡関連のホームページで示していた調査方針等をほぼそのまま再掲する。
2011年04月20日の記事では、鉄道廃線跡の魅力としてノスタルジーとお宝探しと書いたが、たしかに鉄道廃線跡調査を始めた頃はそのように考えていたが、鉄道工事のアルバイトを経て、単に好きだからというだけではなくなってしまった…。(以下、当時のホームページより)

私が跡地をまわる際に心がけているのは、既に人々から忘れ去られて歴史の中に埋もれている橋梁・トンネル・停車場といった構造物を、感情移入する事なく徹底的に調査する事である。
その理由として、まず、鉄道は自然を切り開いて建設したものであり、どの構造物をとっても作業に従事した先人達の血と汗と涙が染み込んでいるからだ。
殊に、北海道の旧国鉄路線の場合、現役の路線も含めてほとんどは囚人労働もしくはタコ部屋労働といった強制労働によって開通している。
(石北本線の常紋トンネル掘削工事の際には人柱が埋められ、トンネル断面改築の際に、人骨が出てきた)
私は、アルバイトながら鉄道工事に従事した経験があるので、どうしても風景より先人達が築きあげた鉄道構造物に目が行ってしまうのである。
厳しい気候に耐え、縁の下の力持ちとして列車の運行を影ながら支えてきた構造物を、間近で見てさわると、仮に鉄道の廃止が仕方なかったとしても、せめて労働者の血と汗と涙の結晶を何らかの形で記録してやらなければ、工事に従事した労働者の苦労が報われないような気がしてならない。
また、鉄路は多くの構造物で結ばれ、どれかが欠けても鉄路として成り立たなくなるものであり、すなわち、鉄道が廃止になるという事は、単純に線路と駅がなくなるだけでなく、路線を構成していたあらゆるものがなくなるという事なのである。
だから、先人達の血と汗と涙の結晶である橋梁・トンネル・停車場といった構造物を徹底的に調査して現状を記録している。
皆さんが廃線跡地に残されている鉄道構造物を見て、先人達の苦労をいくらかでも偲んでいただければ、幸いである。
ただ、廃止路線の楽しみ方はこれだけではなく、例えば、若き頃に乗った廃止路線の記憶を追い求めて沿線を旅してみたり、線路の跡をトレッキングして、廃止路線の旅を疑似体験してみるのも、立派な楽しみ方だ。
かくいう私も、廃止路線を歩く旅は、もともとはどうしても乗りたかった路線の旅を疑似体験する事から始まったのだから…。
たまたま、鉄道工事に従事する機会を得たから、今の所はみんなの目に触れる機会が少ない鉄道構造物を中心にとりあげているだけであり、最終的には、「住民」と「地域」の視線から、廃止路線を見つめたいと考えている。
鉄道は本来、その地域と住民と密接に関わりあって存在するものであり、地域と住民を切り離してしまって鉄道を見つめても、その鉄道の本当の姿が見えてこないような気がするので、私はなるべく時間と機会があったら地元の人と話して、その人にとっての鉄道の想い出を尋ねるようにしている。
私が撮影した跡地の写真の多くは、「記録」としての観点から撮影しており、風景写真と呼べるようなものはほとんどないし、撮影アングルも半ば固定化されてしまっていて変化に乏しい。
記録性を高める為に、私はなるべく構造物の名称(できればデータも)を携帯用の黒板に記入し、黒板を入れて撮影するようにしており、また、寸法を容易に推定できるように、なるべくピンポールと呼ばれる赤と白のダンダラ模様の棒を立てて撮影している。
従って、このホームページで掲載している鉄道跡地の写真には、黒板かピンポールが写っているものも含まれている。
美しい風景写真を期待してご覧になった皆様には申し訳ないが、記録としての観点から写真を撮影している事をご理解して頂きたい。
2011年04月20日の記事では、鉄道廃線跡の魅力としてノスタルジーとお宝探しと書いたが、たしかに鉄道廃線跡調査を始めた頃はそのように考えていたが、鉄道工事のアルバイトを経て、単に好きだからというだけではなくなってしまった…。(以下、当時のホームページより)

私が跡地をまわる際に心がけているのは、既に人々から忘れ去られて歴史の中に埋もれている橋梁・トンネル・停車場といった構造物を、感情移入する事なく徹底的に調査する事である。
その理由として、まず、鉄道は自然を切り開いて建設したものであり、どの構造物をとっても作業に従事した先人達の血と汗と涙が染み込んでいるからだ。
殊に、北海道の旧国鉄路線の場合、現役の路線も含めてほとんどは囚人労働もしくはタコ部屋労働といった強制労働によって開通している。
(石北本線の常紋トンネル掘削工事の際には人柱が埋められ、トンネル断面改築の際に、人骨が出てきた)
私は、アルバイトながら鉄道工事に従事した経験があるので、どうしても風景より先人達が築きあげた鉄道構造物に目が行ってしまうのである。
厳しい気候に耐え、縁の下の力持ちとして列車の運行を影ながら支えてきた構造物を、間近で見てさわると、仮に鉄道の廃止が仕方なかったとしても、せめて労働者の血と汗と涙の結晶を何らかの形で記録してやらなければ、工事に従事した労働者の苦労が報われないような気がしてならない。
また、鉄路は多くの構造物で結ばれ、どれかが欠けても鉄路として成り立たなくなるものであり、すなわち、鉄道が廃止になるという事は、単純に線路と駅がなくなるだけでなく、路線を構成していたあらゆるものがなくなるという事なのである。
だから、先人達の血と汗と涙の結晶である橋梁・トンネル・停車場といった構造物を徹底的に調査して現状を記録している。
皆さんが廃線跡地に残されている鉄道構造物を見て、先人達の苦労をいくらかでも偲んでいただければ、幸いである。
ただ、廃止路線の楽しみ方はこれだけではなく、例えば、若き頃に乗った廃止路線の記憶を追い求めて沿線を旅してみたり、線路の跡をトレッキングして、廃止路線の旅を疑似体験してみるのも、立派な楽しみ方だ。
かくいう私も、廃止路線を歩く旅は、もともとはどうしても乗りたかった路線の旅を疑似体験する事から始まったのだから…。
たまたま、鉄道工事に従事する機会を得たから、今の所はみんなの目に触れる機会が少ない鉄道構造物を中心にとりあげているだけであり、最終的には、「住民」と「地域」の視線から、廃止路線を見つめたいと考えている。
鉄道は本来、その地域と住民と密接に関わりあって存在するものであり、地域と住民を切り離してしまって鉄道を見つめても、その鉄道の本当の姿が見えてこないような気がするので、私はなるべく時間と機会があったら地元の人と話して、その人にとっての鉄道の想い出を尋ねるようにしている。
私が撮影した跡地の写真の多くは、「記録」としての観点から撮影しており、風景写真と呼べるようなものはほとんどないし、撮影アングルも半ば固定化されてしまっていて変化に乏しい。
記録性を高める為に、私はなるべく構造物の名称(できればデータも)を携帯用の黒板に記入し、黒板を入れて撮影するようにしており、また、寸法を容易に推定できるように、なるべくピンポールと呼ばれる赤と白のダンダラ模様の棒を立てて撮影している。
従って、このホームページで掲載している鉄道跡地の写真には、黒板かピンポールが写っているものも含まれている。
美しい風景写真を期待してご覧になった皆様には申し訳ないが、記録としての観点から写真を撮影している事をご理解して頂きたい。












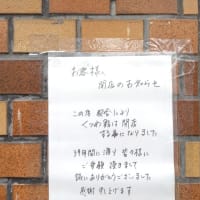







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます