(1974/ジャック・クレイトン監督/ロバート・レッドフォード、サム・ウォーターストン、ミア・ファロー、ブルース・ダーン、カレン・ブラック、スコット・ウィルソン、ロイス・チャイルズ、パッツィ・ケンジット/141分)
<通俗的メロドラマに終始した感がある>というallcinemaの解説どおりの印象だったらどうしよう、いやそれよりもただの退屈しか感じなかったらどうしようと、久しぶりの再会を前にネガティヴにもなっていたのですが、観終わってみれば合格点の見応えに安堵しました。序盤の掴みが弱いのはかつて知ったるナンタラのせいもあるのでしょうがないとして、とにかく全体を面白く観れたのはひとえにレッドフォードの熱演のおかげでしょう。内に秘めた情熱をあれほど感じさせる役って、レッドフォードには珍しいんじゃないでしょうかね。いつもどこか冷めた役が多いですから。
8年ぶりにかつての恋人に会う為に必死で生きてきた男。金持ちの娘は金持ちとしか結婚しないと言う恋人に見合う大金持ちになろうと、違法な事にも手を出したであろう男。実はその陰で、ストイックに人生設計し、貧しい親にも僅かながらの仕送りをしてきた中西部の田舎町出身のひたむきな男。それら原作どおりの主人公の全てを体現したレッドフォードの演技がこの映画の最大の見所でありましょう。
 監督はジャック・クレイトン。英国出身の当時53歳。
監督はジャック・クレイトン。英国出身の当時53歳。
1958年に作った「年上の女」が有名で、その他ゴーゴリの「外套 (1955)」とか、ヘンリー・ジェームズの「回転 (1961)」とか文芸物の映画化が得意な監督というのが当時からのイメージで、ネットで調べると「年上の女」もジョン・ブレインと云う作家の原作小説がありました。
で、「The Great Gatsby」ですよ。
当時は封切りと相前後して原作小説を買いまして(レッドフォードとミアが寄り添う画像が表紙を飾っていたもんです)繰り返し読みましたね。これもネットで調べると<Modern Libraryの発表した英語で書かれた20世紀最高の小説では2位にランクされている>と書かれていました。書いたのはヘミングウェイと同世代(つまり“失われた世代”)のF・スコット・フィッツジェラルド。村上春樹が大好きな作家で、数年前に村上自身の翻訳本が出版されましたが、僕は名訳とされる野崎孝氏の新潮社版が好きなので、村上版は未読です。
因みに「年上の女」は翌年のアカデミー賞の主要6部門にノミネートされて、フランスのシモーヌ・シニョレが主演女優賞を獲ったのでした。
さて、映画は原作をほぼ忠実になぞっているので、序盤のあらすじは原作のウィキを引用したいと思います。あしからず。
<1922年のアメリカ。中西部出身のニック・キャラウェイは、イェール大学を卒業後ほどなくして戦争に従軍し、休戦ののち故郷へと帰ってきた。しかしそこに孤独感を覚えた彼は証券会社で働くことを口実に、ニューヨーク郊外のロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくる。隣の大邸宅に住んでいる人物は毎夜豪華なパーティーを開いている。青みを帯びた庭園には男たちや女たちが蛾のように集まって、ささやきやシャンパンや星明かりの下を行き交った。その屋敷の主がジェイ・ギャツビーという人物であると知り、興味を持つ。ある日、ニックはギャツビーのパーティーに招かれる。しかし、そのパーティーの参加者のほとんどがギャツビーについて正確なことを知らず、彼の過去に関して悪意を含んだ噂ばかりを耳にする。やがてニックはギャツビーが5年もの間胸に秘めていたある野望を知ることになる>
ニックが主人公のように書かれていますが、実際、原作はニックが語り手となっている一人称小説なので、こうなってるんですね。映画も最初と最後にニックのモノローグを入れて原作らしさを出そうとしています。
ギャツビーの野望というのは、かつて愛を育んだのに戦争に行っている間に人妻になってしまったデイジーを取り戻すこと。ウィキでは5年となっていますが、映画では8ぶりの再会となっていました。又、パーティーが毎夜開かれているとなっていますが、映画は2週間に一度と言っていた様な・・・。
脚色したのは「ゴッドファーザー (1972)」などのフランシス・フォード・コッポラ。大ヒット作を監督した後にこの脚本を書いたわけですから、コッポラにとっても魅力的な原作だったんでしょうね。
ニックに扮するのは、サム・ウォーターストン。原作ではデイジーとは“また従姉妹”と書かれていますが、映画では“いとこ”になっていました。後に傑作「キリング・フィールド」のジャーナリスト役で再会した時は嬉しかったですな。
デイジーの夫トム・ブキャナン役はブルース・ダーン。ヒッチコックの「ファミリー・プロット」とかハル・アシュビーの「帰郷」とか、この頃のアメリカ映画には欠かせない俳優で、「ジュラシック・パーク」のローラ・ダーンが彼の娘だというのは大分後になって知りました。
デイジーの親友でプロゴルファーだというジョーダン・ベイカーには、綺麗な顔に似合わぬセクシーな低い声のロイス・チャイルズ。79年のボンドガールですね。
トムの愛人役で終盤で交通事故で死んでしまう奔放な人妻マートル役がカレン・ブラック。彼女もこの頃のアメリカ映画には欠かせない女優で、この後「ファミリー・プロット」でブルース・ダーンと再共演しました。
マートルの亭主でしがないカーガレージのオーナーがスコット・ウィルソン。「冷血(1967)」のヒコックです。
当時、デイジー役がミア・ファローだったことには賛否両論ありました。というか否の方が多かったですね。確かに原作の背景から考えるデイジーのゴージャスさは無い様な気はするのですが、最終的な人間性の表現としてはデイジーに合ってない事もない、とそんな事を当時思ったのを覚えております。
原作に忠実な脚本で2時間を超える今作は、人間関係も、プロットも難しいところは無いのですが、宣伝文句のようなロマンチックなムードを期待したら最後に裏切られますのでご用心を。ニック語るところの<浪漫的心情>たっぷりな男の純情と、ある種の金持ちの人間性の薄っぺらさと卑しさを描いた作品で、原作小説はニックというギャツビーと同じ中西部出身の男の目を通して語られているので、幾分かのアイロニーと哀愁が感じられて味わい深いのですが、映画はそこまでニックの心情を描ききってないので虚しさだけが残る印象でした。

<通俗的メロドラマに終始した感がある>というallcinemaの解説どおりの印象だったらどうしよう、いやそれよりもただの退屈しか感じなかったらどうしようと、久しぶりの再会を前にネガティヴにもなっていたのですが、観終わってみれば合格点の見応えに安堵しました。序盤の掴みが弱いのはかつて知ったるナンタラのせいもあるのでしょうがないとして、とにかく全体を面白く観れたのはひとえにレッドフォードの熱演のおかげでしょう。内に秘めた情熱をあれほど感じさせる役って、レッドフォードには珍しいんじゃないでしょうかね。いつもどこか冷めた役が多いですから。
8年ぶりにかつての恋人に会う為に必死で生きてきた男。金持ちの娘は金持ちとしか結婚しないと言う恋人に見合う大金持ちになろうと、違法な事にも手を出したであろう男。実はその陰で、ストイックに人生設計し、貧しい親にも僅かながらの仕送りをしてきた中西部の田舎町出身のひたむきな男。それら原作どおりの主人公の全てを体現したレッドフォードの演技がこの映画の最大の見所でありましょう。
*
 監督はジャック・クレイトン。英国出身の当時53歳。
監督はジャック・クレイトン。英国出身の当時53歳。1958年に作った「年上の女」が有名で、その他ゴーゴリの「外套 (1955)」とか、ヘンリー・ジェームズの「回転 (1961)」とか文芸物の映画化が得意な監督というのが当時からのイメージで、ネットで調べると「年上の女」もジョン・ブレインと云う作家の原作小説がありました。
で、「The Great Gatsby」ですよ。
当時は封切りと相前後して原作小説を買いまして(レッドフォードとミアが寄り添う画像が表紙を飾っていたもんです)繰り返し読みましたね。これもネットで調べると<Modern Libraryの発表した英語で書かれた20世紀最高の小説では2位にランクされている>と書かれていました。書いたのはヘミングウェイと同世代(つまり“失われた世代”)のF・スコット・フィッツジェラルド。村上春樹が大好きな作家で、数年前に村上自身の翻訳本が出版されましたが、僕は名訳とされる野崎孝氏の新潮社版が好きなので、村上版は未読です。
因みに「年上の女」は翌年のアカデミー賞の主要6部門にノミネートされて、フランスのシモーヌ・シニョレが主演女優賞を獲ったのでした。
さて、映画は原作をほぼ忠実になぞっているので、序盤のあらすじは原作のウィキを引用したいと思います。あしからず。
<1922年のアメリカ。中西部出身のニック・キャラウェイは、イェール大学を卒業後ほどなくして戦争に従軍し、休戦ののち故郷へと帰ってきた。しかしそこに孤独感を覚えた彼は証券会社で働くことを口実に、ニューヨーク郊外のロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくる。隣の大邸宅に住んでいる人物は毎夜豪華なパーティーを開いている。青みを帯びた庭園には男たちや女たちが蛾のように集まって、ささやきやシャンパンや星明かりの下を行き交った。その屋敷の主がジェイ・ギャツビーという人物であると知り、興味を持つ。ある日、ニックはギャツビーのパーティーに招かれる。しかし、そのパーティーの参加者のほとんどがギャツビーについて正確なことを知らず、彼の過去に関して悪意を含んだ噂ばかりを耳にする。やがてニックはギャツビーが5年もの間胸に秘めていたある野望を知ることになる>
ニックが主人公のように書かれていますが、実際、原作はニックが語り手となっている一人称小説なので、こうなってるんですね。映画も最初と最後にニックのモノローグを入れて原作らしさを出そうとしています。
ギャツビーの野望というのは、かつて愛を育んだのに戦争に行っている間に人妻になってしまったデイジーを取り戻すこと。ウィキでは5年となっていますが、映画では8ぶりの再会となっていました。又、パーティーが毎夜開かれているとなっていますが、映画は2週間に一度と言っていた様な・・・。
脚色したのは「ゴッドファーザー (1972)」などのフランシス・フォード・コッポラ。大ヒット作を監督した後にこの脚本を書いたわけですから、コッポラにとっても魅力的な原作だったんでしょうね。
ニックに扮するのは、サム・ウォーターストン。原作ではデイジーとは“また従姉妹”と書かれていますが、映画では“いとこ”になっていました。後に傑作「キリング・フィールド」のジャーナリスト役で再会した時は嬉しかったですな。
デイジーの夫トム・ブキャナン役はブルース・ダーン。ヒッチコックの「ファミリー・プロット」とかハル・アシュビーの「帰郷」とか、この頃のアメリカ映画には欠かせない俳優で、「ジュラシック・パーク」のローラ・ダーンが彼の娘だというのは大分後になって知りました。
デイジーの親友でプロゴルファーだというジョーダン・ベイカーには、綺麗な顔に似合わぬセクシーな低い声のロイス・チャイルズ。79年のボンドガールですね。
トムの愛人役で終盤で交通事故で死んでしまう奔放な人妻マートル役がカレン・ブラック。彼女もこの頃のアメリカ映画には欠かせない女優で、この後「ファミリー・プロット」でブルース・ダーンと再共演しました。
マートルの亭主でしがないカーガレージのオーナーがスコット・ウィルソン。「冷血(1967)」のヒコックです。
当時、デイジー役がミア・ファローだったことには賛否両論ありました。というか否の方が多かったですね。確かに原作の背景から考えるデイジーのゴージャスさは無い様な気はするのですが、最終的な人間性の表現としてはデイジーに合ってない事もない、とそんな事を当時思ったのを覚えております。
原作に忠実な脚本で2時間を超える今作は、人間関係も、プロットも難しいところは無いのですが、宣伝文句のようなロマンチックなムードを期待したら最後に裏切られますのでご用心を。ニック語るところの<浪漫的心情>たっぷりな男の純情と、ある種の金持ちの人間性の薄っぺらさと卑しさを描いた作品で、原作小説はニックというギャツビーと同じ中西部出身の男の目を通して語られているので、幾分かのアイロニーと哀愁が感じられて味わい深いのですが、映画はそこまでニックの心情を描ききってないので虚しさだけが残る印象でした。

・お薦め度【★★★=一見の価値あり】 


















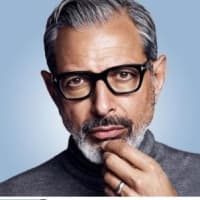





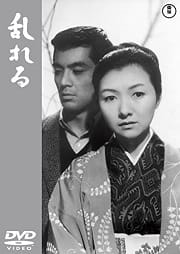

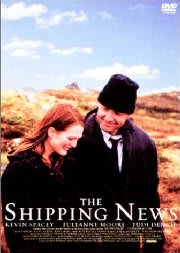







1970年代のアメリカ映画界は、1930年代へのノスタルジーを込めた作品がブームになっていましたが、この「華麗なるギャツビー」という映画は、更に時代を遡った、頽廃の花咲く1920年代の"成金文化"を背景として描いています。
この映画の原作は、"失われた世代"の作家と言われる、F・スコット・フィッツジェラルドで、彼は第一次世界大戦の勝利で成金の国になったアメリカという国をバックに、金にまかせて狂乱のごとく、浮かれ騒ぐ、アメリカの消費者たちの精神的な混乱をテーマにした小説を、この原作以外にも数多く書いています。
彼の小説はそれまでにも幾つか映画化されていて、例えば、1954年の「雨の朝巴里に死す」(リチャード・ブルックス監督)は、退廃的でデカダンな日々を送り、深酒に酔いしれる新進作家が、そのような荒んだ日々の中にも、エリザベス・テイラー演じる美貌の女に果たせぬ思いを寄せるという内容の作品でした。
内容的にはややメロドラマ調の映画でしたが、酒でも飲まなければいられない、男の心の奥底のロマンティシズムといったものが、テーマとなっていました。このように、F・スコット・フィツジェラルド自身が、かなり破滅的な人生を送り、酒に溺れて、晩年は不遇のうちに亡くなったそうです。その破滅的な生きざまは、日本の作家で言えば、太宰治や坂口安吾などの無頼派の作家と共通するものがあるように思います。
映画「華麗なるギャツビー」は、ある男の生きざまの悲哀を、"男心は純情"という思いの込められた作品で、原題の「THE GREAT GATSBY」の中の"GREAT"はアメリカの俗語で、"いかす"という感じで使われているそうですが、ギャツビーの短い悲劇の生涯は、まさにその表現がぴったりします。
ニューヨーク郊外のロングアイランドの湖畔に豪邸を構える、若いギャツビーの素性は明らかではない。
夜な夜な催される豪華なパーティ。
そこでは楽団の派手な演奏と共に、数多くの男女が集まっては飲み、食い、踊り、騒ぐといった饗宴が繰り広げられていました。
ところが、この邸の主人は、ほとんどこの饗宴には顔を出さず、部屋にこもり、何かの思いに耐えているようで、彼の素性は謎に包まれていて、このパーテイに招かれる上流階級の人々も、陰では彼を密輸や麻薬といったもので成り上がった暗い過去を持つ成金じゃないかと噂します。
しかし、ギャツビーは表面的には一分のすきもないくらいの美青年であり、その笑顔は爽やかでさえあり、こんな主人公を、当時のアメリカ映画界で人気、実力共にNo.1であったロバート・レッドフォードが「追憶」そして「スティング」で見せた魅力的な微笑というものが、この映画ではその微笑の裏に"暗い翳り"を秘めた男を、惚れぼれする程の良い男っぷりで演じていて、まさにミスター・ハリウッドという形容がぴったりするくらいで、当時、ゲーリー・クーパーの再来と言われていた事が納得出来ます。
ギャツビーが人生を賭けてまで愛した女性デイジー役のミア・ファローは、はっきり言ってミス・キャストで、魔性を秘めた魅惑的な女性デイジーのイメージにはほど遠く、当時、他にデイジー役を演じる女優がいなかったのかと残念でなりません。
昔であれば、エリザベス・テイラーが演じていた役どころで、リズだったら魔性の魅力を秘めたデイジーを余すところなく演じていただろうと思います。
この邸の対岸には、彼の初恋の女性デイジー(ミア・ファロー)が、シカゴの大財閥トム(ブルース・ダーン)の妻として贅沢な、そして倦怠の日々を送っています。
戦争にも行かなかった夫のトムは、浮気癖があり、こともあろうに近くの貧しい自動車修理屋の人妻(カレン・ブラック)との情事を楽しんでいます。
そして、その夫(スコット・ウィルソン)は、真面目一方の気弱な男として描かれています。
貧富の差が対照的なこの二組の夫婦、そしてギャツビーの過去と現在。
そして、未来を見透かすように立っているのが、街道筋の大きな眼鏡の立看板であり、この立看板というものが、"神を象徴する役割"をこの映画で果たしていると思います。
このあたりをさりげなく見せる、ジャック・クレイトン監督の演出のうまさが光っています。
そして、トムとデイジー夫妻の知人であり、ギャツビーの隣人でもあるニック(サム・ウォーターストン)も、この映画の舞台回しというか、狂言回しとして、"冷静な観察者"として、実にうまく描いていると思います。
このニックを介してギャツビーは、やっと恋い焦がれた、初恋の女性デイジーと再会する事が出来ますが、戦争から帰るまでどうして待っていてくれなかったのかと詰問する彼に答えて、「金持の娘は貧乏人とは結婚できないのよ」と言うまでに、デイジーは上流社会の生き方が身にしみて育った、いわば"砂糖菓子"のような女でした。
原作の小説の中で、「その声までが金持らしい娘」と書かれていますが、甘やかされて、わがままな反面、繊細な感情のひらめく魅力的な女、天真爛漫な華やかさと功利に長けた計算とが一体となったような、矛盾に満ちた女------女とは本来、このような"魔性"を秘めたものなのかも知れませんが、しかし、映画を観ている間中、こんな女に何故惚れてしまうのか、と言いたくなる感情を抑えきれませんでした。
そして、デイジーとの間に愛情が取り戻され、ギャツビーが一生を賭けた恋が成就するかと思われたが、その破局は一気に訪れます。
暑いニューヨークのホテルでのギャツビーとトムとの確執、対決は、デイジーを錯乱させ、彼女の運転するギャツビーの黄色いロールス・ロイスは、自動車修理屋の妻を轢き殺してしまいます。
キャツビーはデイジーをかばって彼女を夫のもとに送り届けますが、翌日、この自動車修理屋は妻の浮気相手のトムを殺そうと迫りますが、トムにギャツビーが犯人であると吹き込まれて、ギャツビーをそのプールで射殺して自殺します。
結局、女を思い詰めた二人の男が同時に死んだのです。
大邸宅も巨大な財産も、そして命さえも、男はただ一人の女に捧げて悔いはないかのようです。
この映画でのロマンティシズム、恋にそして人生に破れて死んでいった男の姿は、まことに哀しく憐れでもあります。
そして、生き残ったデイジーは、ケロリとして夫とよりを戻し、何事もなかったかのように、陽気に旅立って行きます。
女の軽薄さを示すこのラストで、死んでいった男の哀しさ、憐れさが、余計に我々、観る者の心に迫ります。
この映画での"冷静な観察者"であるニックが言うように、軽薄なトムとデイジー夫妻は、それぞれ身勝手な事をやって、その始末は誠実な他人の死によってあがなわれ、彼らの豪奢な生活は守られたのです。
うわべだけの薄っぺらな上流階級の人々より、どれだけギャツビーの方が人間的に優れているか----、虚像と実像の違いを原作者のF・スコット・フィッツジェラルドと脚色のフランシス・フォード・コッポラと監督のジャック・クレイトンは、ニックの目を通して、痛憤の思いで描いていると思います。
フランス戦線での勲功章だけは、ギャツビーに残された唯一の確かな履歴であり、また、古い日記に書かれた少年の日の決意といったものが、彼の本質を切なく語っていると思います。
一、発声練習、二、勉強、三、毎週の貯金三ドル、四、禁煙、五、親孝行--------。
この映画は、ギャツビーという一人の人間を通して、アメリカの純情に熱い懐旧の涙を注いでいる、切なくも哀しい人間ドラマであり、単なるラブロマンスの映画ではないのです。