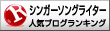千の風になって。
去年(2006年)の紅白で歌われた歌詞なので、御存知の方は多いだろう。
私がこの詩を初めて知ったのは、とある地方の空港で、だった。
その時、私は自分の乗る飛行機の搭乗時間を空港の待ち合い室で待っていた。
座っている椅子は一番前の椅子だった。
目の前に大きなモニターがあった。
搭乗時間まではまだ間があるので、ぼんやりと、見るとはなしにそのモニターを見ていた。
すると。
いきなり、この詩のテロップが流れ始めた。
映像と共に。
詩の出だしのインパクトにまず引きこまれた。
で、引きこまれたまま画面を見続けた。
詩が進むにつれ、ジ~~~~~~ンと熱いものがこみ上げてきた。
な、なんなんだ、この詩は・・・。
この世には、こんな詩もあるのか。
凄い。素晴らしすぎる。切なすぎる。
メロディもなにも聞こえないのに、その詩の言葉だけで泣きそうになった。
身近な人の死・・という辛い出来事を体験したことのある人がこの詩を読んだら、その感動はまたひとしおであろう。
例えば、私自身がそうだった。
人によっては、号泣することだろう。それほどの感動が、ある。
詩というものは、良い言葉というものは、こんなにも力を持っているのか。
改めて、言葉の力というものを感じた。
こんな詩が書けたら、どんなに素晴らしいだろう。
でも、非才な私なんかには、とてもこんな詩は書けないだろう。
どんな人がこの詩を書いたのだろう。きっと、相当名のある詩人に違いない。
そう、作詞家ではなく、詩人であろう。
そう思い、ネットであれこれ調べてみた。
すると・・。
以下のことが分かった。
この詩の原詩が書かれたのは1932年らしいということ。
長い間この詩は作者不詳とされていたが、最近、この詩はメアリー・フライという女性の作品であることが分かったということ。
メアリーはアメリカ人ではあるが、元々はドイツ系ユダヤ人で、ヒットラーの時代にドイツからアメリカに渡ったらしい。
なにより驚くべきことは、この原詩は彼女が子供の頃に書いた詩である!という事実だった。
そうか・・・子供がこの詩を書いたのか。
子供の持つ純粋な心でなければ、ここまで美しく切なく、無垢な詩は書けないのかもしれない。
メアリーはその後も詩人であり続けたようだが、ついにこの詩を越える詩は書けなかったらしい。
でも、それがなんだ。それがどうした。
世の中、これほどの詩を1作品も書けずにいなくなっていく詩人が溢れているではないか。
こんな世紀の名詩を1作品世に残しただけでも、その人は偉大な詩人だ。
できればこの詩を引用したいのだが、ちょっと調べたところ、引用するには色々手続きが必要なようで、そういうのは面倒くさいのでやめておく。
原詩を色んな方が訳しているが、その中では新井満さんの訳が有名のようだ。
絶品である。
その訳詩は新井満さんのHPにある。
アドレスを記しておくので、行って、トップページの右上の方にある「◆「千の風になって」 関連ページはこちらへ」の「こちら」の文字をクリック。
で、「千の風になって 詳細」の項目の「詳細」の文字をクリックしてみてほしい。
言葉だけで人の心を動かしてしまう「詩」がそこにある。
新井満さんのHP → http://www.twin.ne.jp/~m_nacht/
この詩にメロディを付けて「歌」となったバージョンが歌われた去年の紅白以来、この詩は改めて注目を浴びているようだ。
メロディが付くことで、この詩が1人でも多くの「愛する人を失った人たち」に届くのなら、それはそれで「歌」としての功績でもある。
世には様々なメロディが溢れているが、この詩を載せたメロディは幸せものであるし、かつまたその使命は大きい。
だが、この曲を聴いた人は、一度メロディを頭から外して、まずは詩だけを味わってみてほしい。
朗読などしてみたら、なおさらこの詩の良さが染みるだろう。
へたしたら、どんなメロディも歌詞負けしてしまいそうであるし、なまじメロディなど必要としなくても、この詩は「歌」である。そんじょそこらの歌よりも、よっぽど。
私のような非才な「歌作りが好きな人間」では、恐れ多くてメロディなど乗っけられない。
私の作るメロディなど、受け付けてくれない・・そんな崇高さを持っている。
でも、あえてメロディをつける「勇気ある行動」をした新井満さんには心から拍手を送りたい。
「千の風になって」。
千の歌になって、大きな空を吹きわたれ。
そして、何千・・何億もの人の心に吹きわたれ。
去年(2006年)の紅白で歌われた歌詞なので、御存知の方は多いだろう。
私がこの詩を初めて知ったのは、とある地方の空港で、だった。
その時、私は自分の乗る飛行機の搭乗時間を空港の待ち合い室で待っていた。
座っている椅子は一番前の椅子だった。
目の前に大きなモニターがあった。
搭乗時間まではまだ間があるので、ぼんやりと、見るとはなしにそのモニターを見ていた。
すると。
いきなり、この詩のテロップが流れ始めた。
映像と共に。
詩の出だしのインパクトにまず引きこまれた。
で、引きこまれたまま画面を見続けた。
詩が進むにつれ、ジ~~~~~~ンと熱いものがこみ上げてきた。
な、なんなんだ、この詩は・・・。
この世には、こんな詩もあるのか。
凄い。素晴らしすぎる。切なすぎる。
メロディもなにも聞こえないのに、その詩の言葉だけで泣きそうになった。
身近な人の死・・という辛い出来事を体験したことのある人がこの詩を読んだら、その感動はまたひとしおであろう。
例えば、私自身がそうだった。
人によっては、号泣することだろう。それほどの感動が、ある。
詩というものは、良い言葉というものは、こんなにも力を持っているのか。
改めて、言葉の力というものを感じた。
こんな詩が書けたら、どんなに素晴らしいだろう。
でも、非才な私なんかには、とてもこんな詩は書けないだろう。
どんな人がこの詩を書いたのだろう。きっと、相当名のある詩人に違いない。
そう、作詞家ではなく、詩人であろう。
そう思い、ネットであれこれ調べてみた。
すると・・。
以下のことが分かった。
この詩の原詩が書かれたのは1932年らしいということ。
長い間この詩は作者不詳とされていたが、最近、この詩はメアリー・フライという女性の作品であることが分かったということ。
メアリーはアメリカ人ではあるが、元々はドイツ系ユダヤ人で、ヒットラーの時代にドイツからアメリカに渡ったらしい。
なにより驚くべきことは、この原詩は彼女が子供の頃に書いた詩である!という事実だった。
そうか・・・子供がこの詩を書いたのか。
子供の持つ純粋な心でなければ、ここまで美しく切なく、無垢な詩は書けないのかもしれない。
メアリーはその後も詩人であり続けたようだが、ついにこの詩を越える詩は書けなかったらしい。
でも、それがなんだ。それがどうした。
世の中、これほどの詩を1作品も書けずにいなくなっていく詩人が溢れているではないか。
こんな世紀の名詩を1作品世に残しただけでも、その人は偉大な詩人だ。
できればこの詩を引用したいのだが、ちょっと調べたところ、引用するには色々手続きが必要なようで、そういうのは面倒くさいのでやめておく。
原詩を色んな方が訳しているが、その中では新井満さんの訳が有名のようだ。
絶品である。
その訳詩は新井満さんのHPにある。
アドレスを記しておくので、行って、トップページの右上の方にある「◆「千の風になって」 関連ページはこちらへ」の「こちら」の文字をクリック。
で、「千の風になって 詳細」の項目の「詳細」の文字をクリックしてみてほしい。
言葉だけで人の心を動かしてしまう「詩」がそこにある。
新井満さんのHP → http://www.twin.ne.jp/~m_nacht/
この詩にメロディを付けて「歌」となったバージョンが歌われた去年の紅白以来、この詩は改めて注目を浴びているようだ。
メロディが付くことで、この詩が1人でも多くの「愛する人を失った人たち」に届くのなら、それはそれで「歌」としての功績でもある。
世には様々なメロディが溢れているが、この詩を載せたメロディは幸せものであるし、かつまたその使命は大きい。
だが、この曲を聴いた人は、一度メロディを頭から外して、まずは詩だけを味わってみてほしい。
朗読などしてみたら、なおさらこの詩の良さが染みるだろう。
へたしたら、どんなメロディも歌詞負けしてしまいそうであるし、なまじメロディなど必要としなくても、この詩は「歌」である。そんじょそこらの歌よりも、よっぽど。
私のような非才な「歌作りが好きな人間」では、恐れ多くてメロディなど乗っけられない。
私の作るメロディなど、受け付けてくれない・・そんな崇高さを持っている。
でも、あえてメロディをつける「勇気ある行動」をした新井満さんには心から拍手を送りたい。
「千の風になって」。
千の歌になって、大きな空を吹きわたれ。
そして、何千・・何億もの人の心に吹きわたれ。