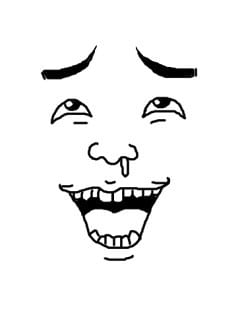
信じるか信じないかの問題ではない。あるんだから仕方ない。
死語の世界~~! ←故・丹波哲郎さん風に。
ここでは「死後」ではなく、あくまでも「死語」のことである。
今回とりあげる死語は「あんぽんたん」である。
これは主に、人を非難したり揶揄したりする時に使われてた言葉である。
意味合いとしては「アホ」とか「バカ」「まぬけ」というニュアンスの言葉。
私が子供の頃にはたまに耳にすることがあった言葉だが、すでにその頃であっても、主流は「バカ」という言葉であった。
今では、あまり耳にすることはなくなった。
ということは一過性の言葉だったのかな・・・と思って調べてみたのだが、調べてみて少しビックリ。
「あんぽんたん」という言葉は江戸時代にもあった言葉で、江戸時代に書かれた随筆にすでにこの言葉は出てきているそうな。なにげに歴史のある言葉だった・・・ということになる。
そう、人に歴史があるように、あんぽんたんにも歴史あり。
江戸時代からあった言葉だなんて、ちょっと意外。いやあ、何事も調べてみないとわからないものではある。
江戸時代にすでにあった言葉である・・・ということも少し驚いたが、それ以上に「あんぽんたん」に漢字の「当て字」があることは意外であった。
漢字では「安本丹」と書くらしい。
なんでもそれは「反魂丹」や「萬金丹」をもじった呼び方だったようだ。ちなみに「反魂丹」というのは伝承家庭薬の名称だったり、中国では死者を蘇らせる霊薬の名称だったそうな。
また「萬金丹」にしても薬の名前である。
反魂丹や萬金丹と安本丹では、だいぶ内容が違うような気がするが・・(笑)。
「あんぽんたん」というのは元々は「あほんだら」という言葉が転じた言葉である・・・という説もネットで見つけることもできた。
まあ、なんにせよ、人を揶揄したりバカにするような言葉であることは間違いないのだろう。
そういう言葉は過去から今にいたるまでたくさんの言葉があった。
例えば
「バカ」「アホ」「まぬけ」「とんま」「おたんこなす」「スカタン」「とんちんかん」「たわけ」「うつけ」「おたんちん」「パープリン」「すっとこどっこい」・・その他、多数ある。
「あんぽんたん」が歴史のある言葉であるということは、大昔から他人をコケにするような言葉はあったということで、人をバカにする言葉にも歴史がある・・ということか。
それは今も昔も変わらないのだね。
ただ「あんぽんたん」という言葉は、「バカ」という言葉に比べると、いくぶん「愛嬌」がある語感は感じていた。「バカ」のほうが語調としてキツイ感じがする。
そこには、そう言われる相手を幾分「許している」部分も感じるのだが。少なくても「バカ」よりは。
もっとも「バカ」にも色んなニュアンスはあるけどね。
時には褒め言葉になることもある。
そのへんが、言葉の使い方として幅が広い気はする。
ちなみに・・・上記であげた、「あんぽんたん」の同義語にも少し触れておく。
「バカ」「アホ」「とんま」「まぬけ」は、相手を非難する言葉として、けっこう強い口調を感じる。
あ、でも「バカ」や「アホ」は、関東と関西で、非難の強さには差があるようには思うが。
「おたんこなす」という言葉は個人的には「あんぽんたん」に近い語感を感じている。
相手を非難しておきながらも、どこかに軽く許している・・というニュアンスで。
「おたんこなす」は私は子供時代にもあまり使ったことはなかったと思う。
印象的だったのは、「ゲゲゲの鬼太郎」の中で、ねずみ男が使っていたシーンがあったと思うが、記憶違いだろうか。
ちなみに、語源にはやはり「茄子」が絡んでいるようではある。ただし、あまり良い意味合いではない。なので、人を揶揄する時に使われる言葉になったのだろう。
「スカタン」もまた私は相手を非難する時に使ったことはない。昔、赤塚不二夫さんと長谷邦夫さんの漫画に「しびれのスカタン」というギャグ漫画があったのを思い出すぐらいだ。
「たわけ」は、昔、白土三平さんの忍者漫画によく出てきてた言葉というイメージが私の中にある。
「バカ」と同じぐらいの、語調の強い「非難言葉」に思える。
忍者漫画などに出てきてたぐらいだから、日本では古い時代からあった言葉なのかもしれない。
「うつけ」は、私にとっては時代劇用語のひとつのように思えるのは、織田信長が若い頃に「うつけ」と呼ばれていたのが有名だからであろう。ともかく「たわけ」同様に「古い時代の非難言葉」というイメージがある。
「おたんちん」は私は使った覚えはない。「おたんこなす」に通じる響きだからかな。
「パープリン」は、小林よしのりさんのギャグ「東大一直線」に出てきた言葉というイメージがあるが、合っているだろうか。その作品には同義語として「パーペキ」という言葉もあったような。
「すっとこどっこい」は、口語では使わなかったが、文章では使った覚えがある。
このブログでも過去に使ったことがあるかもしれない。
「あんぽんたん」同様に、相手を揶揄しながらも、どこか愛嬌も感じるし、許容している語感を感じる。少なくても「バカ」「まぬけ」などよりは、柔らかい感じ。
まあ、あれこれ書いてきたが、なんにせよ歴史上の古い時代から人を揶揄したり非難したりする言葉があることから、日々の営みの中で、どの時代でも人は何か妙なことを言ったり、したりした時に、相手を非難したり揶揄したりしてきているということだね。
そのへん、やはり今も昔も変わらない。
きっと、未来も。
なお、「あんぽんたん」に話を戻せば、その名称が商品名に使われたり、店の名前に使っている店もあるようだ。
ということは、今では「あんぽんたん」には、愛きょうみたいなニュアンスが強まってきているのかもしれない。
そういう意味では、完全な「死語」にまではなっていないのかもしれない。
元々は軽い悪口言葉だったのに、商品名や店の名前に使われるようになったというのは、少し不思議な気もする。
もしかして、あんぽんたんは出世した?












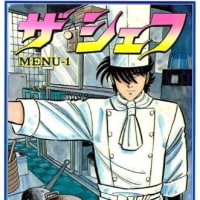















今、気付いて、あわててこうしてレスを書いてます。
アンポンタンは今ではあまり耳にしなくなりましたよね。まあ、言葉としては「バカ」のほうが字数が少ないし、言いやすいというのもあるのでしょう。
でも確かにバカよりは、柔らかい語感はありますよね。
アホの3段活用、面白い!(笑)
ならば、パー、パーペキ、パープリンは、パーの3段活用になったりして。
そう、アンポンタンという言葉は、けっこう古い時期から広まっていたようなんです。
やはり、アンポンタンに歴史あり!
なんか漠然と京都あたりの言葉かな〜なんて思ってましたね。柔らかいけど、ちょっと毒がある…。
あほ、あんぽんたん、あほんだら、あほの三段活用かな(笑)。
まあ、京都限定ではないにしろ、関西地方発祥は間違いないとは思うのですが、けっこう早い時期に全国区になってた言葉なんですね。