
クリーム。
この記事で取り上げる「クリーム」は、語感はおいしそうであっても、決して食べ物ではない。
ロックバンドである。活躍したのは、1960年代の後半。
確か活動時期は2年間ぐらいだったのではないか。
なんといっても、あのエリック・クラプトンが在籍したことで知られているブルース・ロックバンド、それがクリームだ。
そう、確かにクラプトンが在籍したことで有名ではあるが、クラプトン以外の2人のメンバーもすごかった。
当時、最強メンバーと呼ばれたのだ。
ギターがエリック・クラプトン。
ベースがジャック・ブルース。
ドラムがジンジャー・ベイカー。
このたった3人編成のバンドだった。
ある意味、ロックバンドとしては、必要最低人数だったかもしれない。
最少人数の編成で、どこまでやれるか・・・そのテーマに挑戦していたのではないか。
それまでのバンドというと、ギターは2人、そしてベース、ドラムという編成が多く、それにキーボードが加わったり、ボーカルに専念するボーカリストが加わったりするバンドもある・・・そんな編成が多かったと思う。
ギターが2人いるのは、一人がリードギターを担当し、もう一人がリズムギターを担当するのが一般的だった。わかりやすい例がビートルズ。
ストーンズなどは、ギター2人、ベース、ドラム、そしてボーカルに専念するボーカリストがいる編成。
そんな中でクリームはベースとドラムのほかにはギターが1人いるだけ。
最少の編成だったから、一人一人にかかる負担は多いはずなので、メンバー全員がかなりの力量がないとできないだろう。
でも、クリームは当時最強チームと呼ばれたぐらい、名手の集まりだった。だからできたのだろう。
私がクリームを聞くようになったきっかけは、やはりエリック・クラプトンだった。
エリックは当時「ギターの神様」とも呼ばれていたし、若いころのエリックはルックスも実にかっこよかった。
映画スターのようなかっこよさがあった。
神様とも呼ばれたギターの腕前、そして映画スターのようなカッコよさ。
そんなエリックを私が知ったのは、ビートルズ。
ビートルズのホワイトアルバムに入っていたジョージハリスンの曲「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」で、リードギターを弾いていたのがエリックだったからだ。エリックはジョージと友人だったから、ジョージがその曲のレコーディングの時にエリックにゲスト参加してもらったのだ。
最初それを知らなかった私は、ジョージってなんてギターがうまいんだろう・・・と思ったのだが、ビートルズ関連の本を読んでいたか、あるいはラジオからの情報を聞いたかで、その曲でリードを弾いてたのがエリックであったことを知って、一気にエリックへの関心が膨らんだ。
おそらく、当時はそういう経緯でエリックのことを知ったファンは多かったのではないか。
ネットとかは無い時代だったし、得られる情報は今より少なかったはずだったから。
で、エリックのことを調べたら、エリックが在籍していたクリームというバンドのことを知った。
エリックのギター目当てで、クリームのベストアルバムを買って聞いてみたら、聞けば聞くほどクリームのことを好きになった。
毎日聴いていた。
ビートルズのポップな曲を聴きなれていた私の感性では、最初にクリームのアルバムを聴いた時は、その楽曲の方向性の違いにとまどった覚えがある。
クリームの楽曲はビートルズみたいな親しみやすいポップな曲じゃなかったからだ。
クリームはジャンルで言えば、ブルースロックだった。
最初はとまどったが、新鮮にも思えた。
ビートルズのポップさとは違った、「渋さ」に。
ビートルズには、初期にはアイドル的な親しみやすい要素があったが、クリームにはそんな要素は皆無だった。
何度も聴いていくと、その「渋さ」は最高にカッコよく思えていった。
で、すっかりクリームというバンドに私ははまってしまったのだ。
だが・・・悲しいかな、私がクリームにはまった頃は、とうにクリームは解散していた。
話によると、確かにクリームは名手の集まりだったが、それだけにエゴも強かったという。
ドラム・ベース・ギター・・それぞれが戦いあっているような感じだった。
エリックが華麗なギターワークを披露すれば、ジャックのベースは動きまくるし、ジンジャーのドラムはおかずが入りまくる・・・そんな感じに聴こえた。
ファンとしては、聴いててスリリングでわくわくしたのだが、そんな環境で演奏するのにエリックは疲れてしまったらしかった。
解散後、エリックはクリームのことを聞かれ「もうクリームみたいな、曲芸みたいな演奏はしたくない」・・そんな趣旨のことをインタビューで語っていたことがあった。
それぞれがスーパーミュージシャンであったがゆえに、短命で終わってしまったのだろう。
クリームの音楽性を先ほど私は「渋い」と表現したが、かっこよさもあったし、よく聴くとメロディにポップさを感じる曲もあったし、洗練された要素も感じた。
キャッチーなリフも多数。
「ストレンジブルー」の落ち着いた渋さ。
「アイ・フィール・フリー」の洗練されたメロディ。
エリックがジョージハリスンと共作した「バッジ」はクリーム解散後もエリックの定番レパートリーにもなり続けた。
「クロスロード」のギターソロはロックギター史上に残る名演と言われている。
イントロが印象的な「ホワイトルーム」は今でもテレビで流れることもある。
「アイム・ソー・グラッド」のスリリングさ。
「トップ・オブ・ザ・ワールド」の、ブルースフィーリング。
「英雄ユリシーズ」のかっこいいコード進行。
「政治家」の印象的なリフ。
個人的に「荒れ果てた街」などは、かつてこのブログでこの曲をピンポイントで取り上げたこともあるぐらい好きな曲。そのコード進行といい、ギターソロといい。
そして、なんといっても必殺「サンシャインラブ」のあまりも有名なリフは、その後数多くのバンド(プロ、アマ問わず)の定番カバー曲、ロックの教科書的な存在の楽曲になった。
そのほかそのほか。
いやはや、魅力的な曲や演奏の多いこと、多いこと。
こうしてランダムに曲をあげていると、いかに自分がクリームから影響を受けたかを実感する。
インスピレーションはたくさんもらった。
2年たらずの短い活動期間に、濃密な成果を残したバンドだったと思う。
今世紀に入って、クリームは再結成されてコンサートを行ったことがあった。
だがそれは日本ではない。
2005年にロンドンとニューヨークで再結成コンサートが実現し、そのどちらかの様子がDVDになり、私は購入した。
エリックのギターの音色が、昔のクリームの頃のような音色ではなかったけど、おなじみの曲がオリジナルメンバーで再現されたのは嬉しかった。
実は、その後も再結成の話は出た・・らしいのだが、エリックはその噂を否定した。
「友達でもない彼らと、また一緒にやるわけがない」という趣旨の、けっこう辛辣な言葉で・・。
なんでも、ジンジャーがエリックを怒らせた・・・という噂だが、真偽のほどはわからない。
もっとも、クリームというバンドが誕生した当時でも、ジャックとジンジャーは元々険悪な関係だったらしいとも聞くが。
ただ、2005年に再結成した時、エリックはインタビューで「長年音楽活動をしてきて、私の仲間にはもう死んでしまった奴もいる。だが、クリームのメンバー3人は、まだ健在。だから、やろうと思えばクリームはやれるわけだ。ならば、やっておこうと思った。」という趣旨のことを語っていたのに・・。
その後、彼らに何があったのだろう・・。
言えるのは、エリック、ジャック、ジンジャー、そのそれぞれの3人は、それぞれの楽器分野で後世の演奏家に多大な影響を与えたという事実はゆるぎないということ。
スーパープレイヤー同士が集まって組むバンドのことを、「スーパーバンド」と呼ぶが、クリームはその「スーパーバンド」の草分けであった。
2014年、ベースのジャック・ブルースは、この世を去ってしまった。
更に2019年にはドラムのジンジャーベイカーも、この世を去ってしまった。
メンバー同士の関係修復もかなわぬことになってしまった。
もう、永遠にクリーム再結成の可能性はなくなった。
スーパーバンドというのは、結成の時はよくても、長続きさせるのは、やはり難しいのだろうね。
だからこそ・・3人が健在のうちに、一度でいいからクリームの来日公演を・・・見てみたかった。
再結成コンサートをやった2005年にもしクリームが日本にも来てくれていたら、私は絶対に行ったと思う。
大の親日家のエリックだからこそ、私は当時密かに期待したんだけどなあ。
エリックは単独では、もう何回も来日公演をしてきている。
なんでも、武道館でコンサートをやった回数では、エリックは最多クラスだという。
日本国内の日本人アーティストをさしおいて、外国人アーティストであるエリックが最多クラスらしい。
エリックはもう若くない。だから武道館での公演回数の記録は今後誰かに破られていくのかもしれない。
だがエリックが同一ミュージシャンによる武道館での公演回数が最多クラスである事実は変わらない。
まさに親日家。
だから、クリームの再結成の時には期待したのだが…。
ちなみに、私が初めて買ったエレキは、SGのコピーモデルだった。
なぜ、ストラトでもなきゃ、レスポールでもなく、テレキャスでもなく、SGだったかというと・・クリームの影響だった。 エリックは当時もいろんなエレキを弾いていたけど、私のイメージではクリームはSGだったから。
なぜなら、エリックだけでなく、ジャックもクリーム時代にはSGシェイプのベースを弾いていたからだ。
https://www.youtube.com/watch?v=HbqQL0J_Vr0










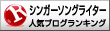

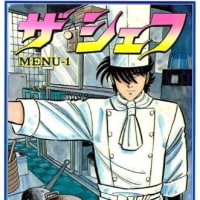















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます