後藤です。
先日行われたコアレクチャーをご紹介します。
題して「麻酔科医視点での心臓血管手術①」
今年度より入職の西村先生に発表してもらいました。
人工心肺の目的を以下の3つに分けて説明してもらいました。
①循環の確立
②臓器の保護
③無血視野の確保
ダイジェストでお届けします。参考にしてください。
—————————————————————————————————————————
①循環の確立
送血管どこから入れる?
上行大動脈:順行性、頭部に近い、送血量が安定しており、選択されやすい
その他(総大腿動脈、腋窩・鎖骨下動脈など):血管性状が不良、低侵襲手術の場合
脱血方法でECMOとの違い?
ほとんどがECMO同様に落差脱血法
違いは貯血槽があること(貯血槽を陰圧にする吸引脱血法もある)
②臓器の保護
最優先で守りたい臓器は?
心臓と脳
心保護はどうやって行う?
主たる方法は心筋保護液による電気的心停止(高K)
手段は2通り:大動脈遮断後の上行大動脈からの心筋保護液の投与
、低体温循環停止後に上行大動脈切開し直接冠動脈に心筋保護液を投与
脳保護:体温管理、pH管理、選択的脳還流と逆行性脳還流
評価するパラメータとしてNIRSなど
③無血視野の確保
おおまかな術野を知った後に、開心術では右心系と左心系で分けて考える
右心系の流入血管:SVC、IVC、冠静脈洞、テベシウス血管
基本的にSVC、IVCそれぞれにカニュレーション必要(2本脱血)
左心系の流入血管:肺静脈、(気管支静脈、テベシウス血管)
肺循環の停止と左室ベント回路で無血視野を得られる
右房からの脱血のみで良い(1本脱血)
—————————————————————————————————————————
西村先生は北海道から異動された、経験豊富な麻酔科 & 集中治療医です。
自身の経験も踏まえながら、初学者や手術室に関わりが少ないスタッフに、わかりやすく説明してもらいました。
たくさん質問も出ましたね。
周術期管理をする上で、背景知識を深めることは大切ですね。
今年度はコアレクチャーの紹介や文献紹介などもしていこうと思いますので、チェックしてみてください。












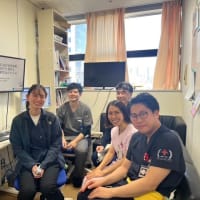









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます