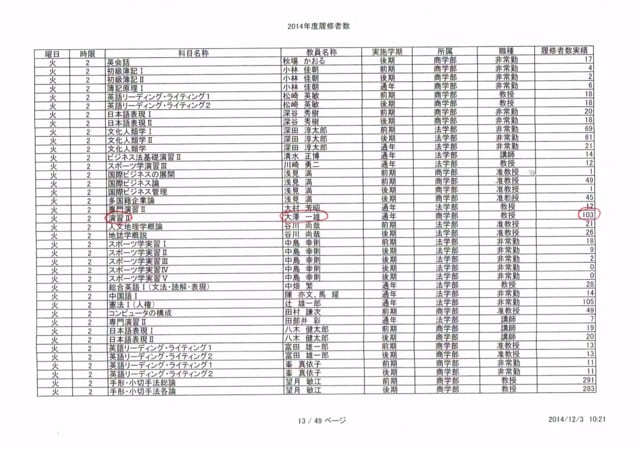連絡先:mkoskirr@gmail.com
■授業内容に質的違いがあるのだとさ!
被告(=学校法人中央学院)の第2準備書面は、これまた前代未聞の珍論奇論を繰り
出して、非常勤講師と専任教員の巨大な賃金格差を正当化している。
こう書かれている。
「授業内容においても、専任教員と非常勤講師には相違がある」(被告第2準備書面
3頁)。
ここでの「相違」とは、明らかに質的相違のことである。
この主張を読むとき、たいていの者は、被告(=学校法人中央学院≒中央学院
大学)が、専任教員の方が非常勤講師よりも学問的業績が優れていると主張して
いるのだ、と予想する。
ところが中央学院大学はいつものように、この予想を見事にくつがえしてくれる。
業績のことをいっているのではないのである。
それもそうだろう。第三者機関である「大学基準協会」が2015年に中央学院
大学に対して行った評価(認証評価結果)では、中央学院大学の専任教員の研究が
不活発であることが、次のように指摘されており、専任教員の研究業績が、非常勤
講師の研究業績よりも優れているなどとの主張は、できるはずがないからである。
「教員の教育・研究活動については、過去5年間の研究
業績がない場合(=者)も見られ、
科学研究費補助金等外部資金への申請もほとんどなく、全体的に研究活動は
不活発である。より実効性のある取り組みを実施し、教員の研究活動を
活性化させその成果を教育に結び付けられる仕組みを作ることが必要である」
(3頁)(https://www.cgu.ac.jp/Portals/0/data0/jikotenken/pdf/20080325hyouka.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27)
同じような指摘は、この7年前の2008年の認証評価結果においても指摘されて
いる。
要するに中央学院大学の専任教員の研究活動は、何度このような指摘を受けても、
概して不活発なままであり、それでも降格、解雇、減給、警告等の処分を受けること
がないのである。
中には、定年までの数十年間に、論文らしきものが数点の
者もいたし、10年以上、学問的業績がゼロの者もいるのである。
では、「授業内容の(質的)相違」とは、何のことを言っているのであろうか?
■専任教員はFDを行っているからだとさ!
中央学院大学がいう「授業内容の(質的)相違」とは、専任教員だけがFDを行っている
ことをいっているのである。
その箇所を引用しておこう。
「専任教員は、全員がFD委員会の活動に参加する義務がある。FD(=Faculty
Development)とは、教員が授業の内容や方法を改善し向上させるために行う
組織的取り組みをいう。具体的には授業評価アンケートの実施と分析、模擬
授業や事例に基づく研究会などである。アンケートは非常勤講師なども対象に
なるが、模擬授業や研究会は専任教員のみの参加である。
このように専任教員の行う教育は、制度的に
能力向上の保障がされているのである」(被告第2準備書面2頁)。
大学関係者の間では、この「エフディー」という言葉はかなり浸透してきた。
被告第2準備書面が説明するように、この語はFaculty Development
(ファカルティ・ディヴェロップメント)のことで、教員が授業の内容や方法を
改善するために組織的取り組みを行うことをいう。
簡単に言うと、授業を改善するための、主として技術的工夫を、個人的にでは
なく組織的に行うことが、FDである。
さて、裁判で主張するのだから、さぞかし中央学院大学は立派なFDを行っていると、
誰もが思うことであろう。ところが中央学院大学は、またもやこれをくつがえして
くれる。
そもそも中央学院大学が行っているFDは、大学を評価する第三者機関である「大学
基準協会」が中央学院大学に対して行った「認証評価結果 2015」の7頁で、次の
ようにさんざんな評価を受けている。
「授業内容・方法の改善を図るための組織的な研修・研究に関しては、<中略>
検討を行っている。しかし、学生による授業評価アンケートが実施されている
ものの、組織的に活用されておらず、そのほかには、年に2回程度の講演を
中心としたものであり、その結果を改善に結び付けているとは判断できない。
いずれにしても、
ファカルティ・ディヴェロップメント(FD)活動については、初歩的な段階に
ありその取り組みの姿勢もきわめて消極的であるため、改善が望まれる」(https://www.cgu.ac.jp/Portals/0/data0/jikotenken/pdf/20080325hyouka.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27)。
大学基準協会の指摘を整理すると、こうである。
① 中央学院大学では、授業評価アンケートをやってはいるが、アンケートの結果は
組織的に活用されていない。
② FDといいながら、やっていることは、年2回程度の単なる「講演会」にすぎない。
だからFDは授業の改善には結びついていない。
③ 中央学院大学のFDは初歩的なものにすぎず、取り組み姿勢は消極的で、改善が
望まれる。
第三者機関にこれほど酷評(こくひょう)されているのに、裁判で、FDを立派に
やっているとよくも堂々と主張できるものだと、ただただ感心し、またあきれてしまう。
■中央学院大学の行っているFD――FDとは無縁なものが大半!
2015年度の「商学部長年次報告」が、これまでのFDの内容を明らかにしている。
その内容を見てみると、大学基準協会の指摘のとおり、大半はFDとは無関係である
ことがわかる。
次のようなものまでFDとされており、笑ってしまう(なお、出席は義務とされて
いながら、専任教員のFDへの出席率は悪い)。
① 地域リーダーとの教育懇談会 我孫子市商工会会長、我孫子市国際交流協会
会長との懇談
② 大学の経営品質のあり方を考える 講演者:<株>アイビー代表取締役
③ 第4回アドバイザリーボード 久寺家まちづくり協議会会長、
久寺家自治会会長、
久寺家マンション自治会長、
久寺家三菱自治会会長、
久寺家二丁目自治会長
④ 学校法人中央学院の財政問題と第二次財政安定化協議会について
常務理事・三友宏、学長・椎名市郎
地域の町内会長等との懇談会や、大学や学校法人の財政の「窮状」の説明が、
なぜFDに化(ば)けてしまうのか、と笑ってしまう。大学基準協会に酷評されるはずだ!
要するに、この程度の「初歩的なFD」を専任教員たちがやっても、専任教員の教育能力
や授業の質が向上するわけでもなく、ましてや専任教員と非常勤講師との間にある巨大な
賃金格差を正当化できるはずもない。
佐藤英明学長さん、裁判に提出する準備書面の作成にあなたが関与していることは、
当組合も知っている。こんな主張が珍論奇論の類であることを、わからないのかね!
当組合と弁護団の目は節穴ではない。
■学生のためであることを忘却
中央学院大学は、すでに10年間もFDをやっている。しかし、なぜ「初歩的な段階」
にとどまっているのであろうか。
それは中央学院大学が、FDが何のために行われているかを理解していないからである。
いうまでもなくFDは学生に対する教育の効果をあげるためのものだ。もし中央学院
大学が真剣にFDのことを考えていたなら、年2回程度の「講演会」で、FDをやって
いるとのアリバイをつくることなどしていなかったであろう。
もっと深刻な問題は、FDは専任教員のみが「やっている」ことを、非常勤講師との巨大な
賃金格差を正当化する理由として挙げていることに潜む自己矛盾に、中央学院大学が
全く気付いていないことである。
もし、FDが重要なら、そして教員の教育能力の向上に役立つなら、FDを専任教員の間だけ
にとどめておくのではなく、非常勤講師の間にも広げなければならないことに、考えが
至らなければならない。講義科目の実に約半分は、非常勤講師が担当しているから
なおさらだ。
しかし中央学院大学は、約半数の講義を担当する非常勤講師の教育能力の向上に、
全く無関心であり、このことは結果として、非常勤講師の授業を受ける学生のこと
など、全く考えていないことを露呈させている。
非常勤講師にもFDへの参加を促している大学も存在している。もちろん、「無給」
でこのFDに参加を促すことの問題はあるのだが・・・
はっきりしていることは、専任教員がFDをやっていることをもって、専任教員の教育能力
の向上が「制度的に保障されている」などと主張する大学は、中央学院大学以外には存在して
いないことだ。
また、専任教員と非常勤講師の巨大な賃金格差の正当化理由に、このFDを挙げる
大学も、中央学院大学以外には存在しないことだ。
第三者機関に酷評されているFDを、巨大な賃金格差の正当化理由とすることに、
恥ずかしさをおぼえないのかね、中央学院大学さん!
■授業内容に質的違いがあるのだとさ!
被告(=学校法人中央学院)の第2準備書面は、これまた前代未聞の珍論奇論を繰り
出して、非常勤講師と専任教員の巨大な賃金格差を正当化している。
こう書かれている。
「授業内容においても、専任教員と非常勤講師には相違がある」(被告第2準備書面
3頁)。
ここでの「相違」とは、明らかに質的相違のことである。
この主張を読むとき、たいていの者は、被告(=学校法人中央学院≒中央学院
大学)が、専任教員の方が非常勤講師よりも学問的業績が優れていると主張して
いるのだ、と予想する。
ところが中央学院大学はいつものように、この予想を見事にくつがえしてくれる。
業績のことをいっているのではないのである。
それもそうだろう。第三者機関である「大学基準協会」が2015年に中央学院
大学に対して行った評価(認証評価結果)では、中央学院大学の専任教員の研究が
不活発であることが、次のように指摘されており、専任教員の研究業績が、非常勤
講師の研究業績よりも優れているなどとの主張は、できるはずがないからである。
「教員の教育・研究活動については、過去5年間の研究
業績がない場合(=者)も見られ、
科学研究費補助金等外部資金への申請もほとんどなく、全体的に研究活動は
不活発である。より実効性のある取り組みを実施し、教員の研究活動を
活性化させその成果を教育に結び付けられる仕組みを作ることが必要である」
(3頁)(https://www.cgu.ac.jp/Portals/0/data0/jikotenken/pdf/20080325hyouka.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27)
同じような指摘は、この7年前の2008年の認証評価結果においても指摘されて
いる。
要するに中央学院大学の専任教員の研究活動は、何度このような指摘を受けても、
概して不活発なままであり、それでも降格、解雇、減給、警告等の処分を受けること
がないのである。
中には、定年までの数十年間に、論文らしきものが数点の
者もいたし、10年以上、学問的業績がゼロの者もいるのである。
では、「授業内容の(質的)相違」とは、何のことを言っているのであろうか?
■専任教員はFDを行っているからだとさ!
中央学院大学がいう「授業内容の(質的)相違」とは、専任教員だけがFDを行っている
ことをいっているのである。
その箇所を引用しておこう。
「専任教員は、全員がFD委員会の活動に参加する義務がある。FD(=Faculty
Development)とは、教員が授業の内容や方法を改善し向上させるために行う
組織的取り組みをいう。具体的には授業評価アンケートの実施と分析、模擬
授業や事例に基づく研究会などである。アンケートは非常勤講師なども対象に
なるが、模擬授業や研究会は専任教員のみの参加である。
このように専任教員の行う教育は、制度的に
能力向上の保障がされているのである」(被告第2準備書面2頁)。
大学関係者の間では、この「エフディー」という言葉はかなり浸透してきた。
被告第2準備書面が説明するように、この語はFaculty Development
(ファカルティ・ディヴェロップメント)のことで、教員が授業の内容や方法を
改善するために組織的取り組みを行うことをいう。
簡単に言うと、授業を改善するための、主として技術的工夫を、個人的にでは
なく組織的に行うことが、FDである。
さて、裁判で主張するのだから、さぞかし中央学院大学は立派なFDを行っていると、
誰もが思うことであろう。ところが中央学院大学は、またもやこれをくつがえして
くれる。
そもそも中央学院大学が行っているFDは、大学を評価する第三者機関である「大学
基準協会」が中央学院大学に対して行った「認証評価結果 2015」の7頁で、次の
ようにさんざんな評価を受けている。
「授業内容・方法の改善を図るための組織的な研修・研究に関しては、<中略>
検討を行っている。しかし、学生による授業評価アンケートが実施されている
ものの、組織的に活用されておらず、そのほかには、年に2回程度の講演を
中心としたものであり、その結果を改善に結び付けているとは判断できない。
いずれにしても、
ファカルティ・ディヴェロップメント(FD)活動については、初歩的な段階に
ありその取り組みの姿勢もきわめて消極的であるため、改善が望まれる」(https://www.cgu.ac.jp/Portals/0/data0/jikotenken/pdf/20080325hyouka.pdf#search=%27%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%90%E6%9E%9C+%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6%27)。
大学基準協会の指摘を整理すると、こうである。
① 中央学院大学では、授業評価アンケートをやってはいるが、アンケートの結果は
組織的に活用されていない。
② FDといいながら、やっていることは、年2回程度の単なる「講演会」にすぎない。
だからFDは授業の改善には結びついていない。
③ 中央学院大学のFDは初歩的なものにすぎず、取り組み姿勢は消極的で、改善が
望まれる。
第三者機関にこれほど酷評(こくひょう)されているのに、裁判で、FDを立派に
やっているとよくも堂々と主張できるものだと、ただただ感心し、またあきれてしまう。
■中央学院大学の行っているFD――FDとは無縁なものが大半!
2015年度の「商学部長年次報告」が、これまでのFDの内容を明らかにしている。
その内容を見てみると、大学基準協会の指摘のとおり、大半はFDとは無関係である
ことがわかる。
次のようなものまでFDとされており、笑ってしまう(なお、出席は義務とされて
いながら、専任教員のFDへの出席率は悪い)。
① 地域リーダーとの教育懇談会 我孫子市商工会会長、我孫子市国際交流協会
会長との懇談
② 大学の経営品質のあり方を考える 講演者:<株>アイビー代表取締役
③ 第4回アドバイザリーボード 久寺家まちづくり協議会会長、
久寺家自治会会長、
久寺家マンション自治会長、
久寺家三菱自治会会長、
久寺家二丁目自治会長
④ 学校法人中央学院の財政問題と第二次財政安定化協議会について
常務理事・三友宏、学長・椎名市郎
地域の町内会長等との懇談会や、大学や学校法人の財政の「窮状」の説明が、
なぜFDに化(ば)けてしまうのか、と笑ってしまう。大学基準協会に酷評されるはずだ!
要するに、この程度の「初歩的なFD」を専任教員たちがやっても、専任教員の教育能力
や授業の質が向上するわけでもなく、ましてや専任教員と非常勤講師との間にある巨大な
賃金格差を正当化できるはずもない。
佐藤英明学長さん、裁判に提出する準備書面の作成にあなたが関与していることは、
当組合も知っている。こんな主張が珍論奇論の類であることを、わからないのかね!
当組合と弁護団の目は節穴ではない。
■学生のためであることを忘却
中央学院大学は、すでに10年間もFDをやっている。しかし、なぜ「初歩的な段階」
にとどまっているのであろうか。
それは中央学院大学が、FDが何のために行われているかを理解していないからである。
いうまでもなくFDは学生に対する教育の効果をあげるためのものだ。もし中央学院
大学が真剣にFDのことを考えていたなら、年2回程度の「講演会」で、FDをやって
いるとのアリバイをつくることなどしていなかったであろう。
もっと深刻な問題は、FDは専任教員のみが「やっている」ことを、非常勤講師との巨大な
賃金格差を正当化する理由として挙げていることに潜む自己矛盾に、中央学院大学が
全く気付いていないことである。
もし、FDが重要なら、そして教員の教育能力の向上に役立つなら、FDを専任教員の間だけ
にとどめておくのではなく、非常勤講師の間にも広げなければならないことに、考えが
至らなければならない。講義科目の実に約半分は、非常勤講師が担当しているから
なおさらだ。
しかし中央学院大学は、約半数の講義を担当する非常勤講師の教育能力の向上に、
全く無関心であり、このことは結果として、非常勤講師の授業を受ける学生のこと
など、全く考えていないことを露呈させている。
非常勤講師にもFDへの参加を促している大学も存在している。もちろん、「無給」
でこのFDに参加を促すことの問題はあるのだが・・・
はっきりしていることは、専任教員がFDをやっていることをもって、専任教員の教育能力
の向上が「制度的に保障されている」などと主張する大学は、中央学院大学以外には存在して
いないことだ。
また、専任教員と非常勤講師の巨大な賃金格差の正当化理由に、このFDを挙げる
大学も、中央学院大学以外には存在しないことだ。
第三者機関に酷評されているFDを、巨大な賃金格差の正当化理由とすることに、
恥ずかしさをおぼえないのかね、中央学院大学さん!