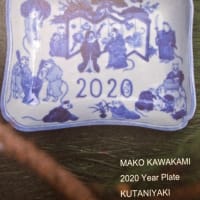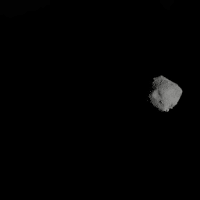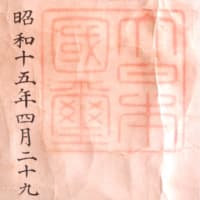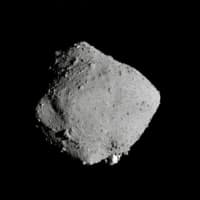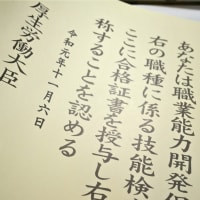オスカー・ワイルドの「幸せな王子」は、同時に収録されている他の短編に比べると書かれ方がまったく違う。
ストーリーの印象もそうなのだけど、ただ印象とか、読者の好みとか、そういうレベルに留まる話でもない。
構成の緻密さがそもそも全然違うのである。
本のタイトルだって《The Happy Prince and Other Tales》というわけなので、
表題として掲げるに足る1編という以上に、
この1編のための1冊だと、作者自身が考えていたとすることだって、十分にできる。
テキストの質がまったく別次元。
オスカー・ワイルドがギリシア語において優秀だったという話を裏付けするような、
彼の言葉のチョイスに注意が向いてしまいがちなのだけど、
別次元のレベル、それを補償するのが聖書であるっていう点は何度でも指摘しなくてはならない。
というのも、あらゆるイメージが聖書を念頭に書かれているから。
ツバメくんだって、聖書から飛び出してきたんだ!って言える。
スタイルの美しい「葦」の彼女も、墓所に横たわるエジプトの王も、神殿に仲間たちが巣を作っていることも。
「幸せな王子」の像がやがて引き倒されることも、
ツバメくんが最初に王子の足元にとまることさえ。
最初に引っかかったのは《preparation》という言葉。
ツバメくんが上空からこの街を眺めながらつぶやくセリフにあるのだけど、
全編にこの言葉が響いているとすれば、なるほど、
この構成が必然であることを認めざるを得ない。
お話には主に2つの《preparation》の意味が隠されているが、うまいことストーリーにこの意味が散りばめられている。
それはツバメくんの語りの中、エジプトでの仲間の暮らしぶりに現れていたり、
ツバメくんが金箔を一枚一枚剥ぎ取っていくシーンにも現れていたりする。
マッチ売りの少女に王子に残された最後のサファイアが捧げられる理由でもある。
およそ、オスカー・ワイルドのイメージ、人物像に「敬虔」という言葉は似合わないように思うのだけれど、
「幸せな王子」この1編だけは、彼の「敬虔」さが尋常でないことを表してしまっている。
この本当にささやかな1編のお話について、「どんな話なの?」と訊かれたら、現在の僕は答えに窮してしまう。
さっちゃんと一緒にオリジナルを読む前であったら。
きっとなんの障りもなく、「これってさ♪」と嬉々として説明できたかもしれない。
今、説明するとしたら?
説明するより、「とにかく一度読んでごらんよ。」としか言いようがない。
なんなら、一緒に読んでみようか?と言うのが良心に叶う。
その時、さり気なく聖書の一節を差し出せれば、なにかの説明にはなるのかもしれない。
本当に「いまさら」なんだけど、僕はこの小さな作品の真価を見過ごし続けてきたんだなぁと。
自分の迂闊さを嘆くよりも、その事実をちゃんと発見できたことの喜びが大きい。
「ドリアン・グレイの肖像」や「サロメ」などよりも、このお話だけが現代にも生き続けていると言い切れる理由。
オスカー・ワイルドの真価は、紛れもなくこの小さな短編に顕れている。
さっちゃんと一緒に読んでいたから、このことに気づいた。
この事実が、まったく個人的ながら、啓示的としか言いようがなくて。
二人で本を読むなんて、初めてのことだった。
その初めが「幸せな王子」で本当によかったな♪
ただ、それもあって、次のテキストになかなか進めない。
とりあえず次のテキストを!という風になかなかなれないでいる。
とはいえ、せっかく「二人で読む」という新しい習慣を手に入れようとしているところ。
できることなら、この「続き」をはやく読み始めたい。
ストーリーの印象もそうなのだけど、ただ印象とか、読者の好みとか、そういうレベルに留まる話でもない。
構成の緻密さがそもそも全然違うのである。
本のタイトルだって《The Happy Prince and Other Tales》というわけなので、
表題として掲げるに足る1編という以上に、
この1編のための1冊だと、作者自身が考えていたとすることだって、十分にできる。
テキストの質がまったく別次元。
オスカー・ワイルドがギリシア語において優秀だったという話を裏付けするような、
彼の言葉のチョイスに注意が向いてしまいがちなのだけど、
別次元のレベル、それを補償するのが聖書であるっていう点は何度でも指摘しなくてはならない。
というのも、あらゆるイメージが聖書を念頭に書かれているから。
ツバメくんだって、聖書から飛び出してきたんだ!って言える。
スタイルの美しい「葦」の彼女も、墓所に横たわるエジプトの王も、神殿に仲間たちが巣を作っていることも。
「幸せな王子」の像がやがて引き倒されることも、
ツバメくんが最初に王子の足元にとまることさえ。
最初に引っかかったのは《preparation》という言葉。
ツバメくんが上空からこの街を眺めながらつぶやくセリフにあるのだけど、
全編にこの言葉が響いているとすれば、なるほど、
この構成が必然であることを認めざるを得ない。
お話には主に2つの《preparation》の意味が隠されているが、うまいことストーリーにこの意味が散りばめられている。
それはツバメくんの語りの中、エジプトでの仲間の暮らしぶりに現れていたり、
ツバメくんが金箔を一枚一枚剥ぎ取っていくシーンにも現れていたりする。
マッチ売りの少女に王子に残された最後のサファイアが捧げられる理由でもある。
およそ、オスカー・ワイルドのイメージ、人物像に「敬虔」という言葉は似合わないように思うのだけれど、
「幸せな王子」この1編だけは、彼の「敬虔」さが尋常でないことを表してしまっている。
この本当にささやかな1編のお話について、「どんな話なの?」と訊かれたら、現在の僕は答えに窮してしまう。
さっちゃんと一緒にオリジナルを読む前であったら。
きっとなんの障りもなく、「これってさ♪」と嬉々として説明できたかもしれない。
今、説明するとしたら?
説明するより、「とにかく一度読んでごらんよ。」としか言いようがない。
なんなら、一緒に読んでみようか?と言うのが良心に叶う。
その時、さり気なく聖書の一節を差し出せれば、なにかの説明にはなるのかもしれない。
本当に「いまさら」なんだけど、僕はこの小さな作品の真価を見過ごし続けてきたんだなぁと。
自分の迂闊さを嘆くよりも、その事実をちゃんと発見できたことの喜びが大きい。
「ドリアン・グレイの肖像」や「サロメ」などよりも、このお話だけが現代にも生き続けていると言い切れる理由。
オスカー・ワイルドの真価は、紛れもなくこの小さな短編に顕れている。
さっちゃんと一緒に読んでいたから、このことに気づいた。
この事実が、まったく個人的ながら、啓示的としか言いようがなくて。
二人で本を読むなんて、初めてのことだった。
その初めが「幸せな王子」で本当によかったな♪
ただ、それもあって、次のテキストになかなか進めない。
とりあえず次のテキストを!という風になかなかなれないでいる。
とはいえ、せっかく「二人で読む」という新しい習慣を手に入れようとしているところ。
できることなら、この「続き」をはやく読み始めたい。