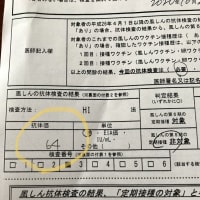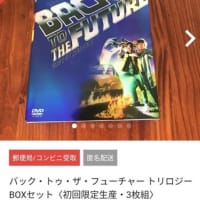ものすごくショック!!
昨日の夕方、NHKのラジオで「格差社会」に関する解説をしたいた。そこでは信じられない話がされていたので、本当かどうかを確認するためにネットで調べてみた。全部、本当の話だった。ショックだった!
就学援助受給者が全国平均で、10%を超えた。
文房具代、給食費、修学旅行代金が払えない人たちに市町村が援助をする制度。30人のクラスなら3人はその制度を使っていることになる。私が小学生だった昭和40年代だってそんな友達はほとんどいなかったと思う。みんな貧乏だったけど、給食費の袋はちゃんと持ってきてたはず。本当に日本の話なんだろうか?
調べたらこんなニュースがあった。悲しくて涙が出そうになった。親にも問題はあるだろうが、「鉛筆やノートを持たない小学生」ってどう?「携帯持って夜遅くまで塾に通う小学生」とあまりにもギャップがあるでしょう。世の中平等ではないけど、チャンスもないじゃん。
就学援助4年で4割増
給食費など東京・大阪4人に1人(朝日新聞)
2006年01月03日17時09分
|
公立の小中学校で文房具代や給食費、修学旅行費などの援助を受ける児童・生徒の数が04年度までの4年間に4割近くも増え、受給率が4割を超える自治体もあることが朝日新聞の調べで分かった。東京や大阪では4人に1人、全国平均でも1割強に上る。経済的な理由で子どもの学習環境が整いにくい家庭が増え、地域的な偏りも目立っている。 文部科学省によると、就学援助の受給者は04年度が全国で約133万7000人。00年度より約37%増えた。受給率の全国平均は12.8%。 都道府県で最も高いのは大阪府の27.9%で、東京都の24.8%、山口県の23.2%と続く。市区町村別では東京都足立区が突出しており、93年度は15.8%だったのが、00年度に30%台に上昇、04年度には42.5%に達した。 背景にはリストラや給与水準の低下がある。厚生労働省の調査では、常用雇用者の給与は04年まで4年連続で減り、00年の94%まで落ちた。 給付の基準は自治体によって異なり、足立区の場合、対象となるのは前年の所得が生活保護水準の1.1倍以内の家庭。支給額は年平均で小学生が7万円、中学生が12万円。修学旅行費や給食費は、保護者が目的外に使ってしまうのを防ぐため、校長管理の口座に直接、振り込んでいる。 同区内には受給率が7割に達した小学校もある。この学校で6年生を担任する男性教員は、鉛筆の束と消しゴム、白紙の紙を持参して授業を始める。クラスに数人いるノートや鉛筆を持って来ない児童に渡すためだ。 卒業文集を制作するため、クラスの児童に「将来の夢」を作文させようとしたが、3分の1の子が何も書けなかった。「自分が成長してどんな大人になりたいのか、イメージできない」のだという。 同区の公立中学校の50代男性教員は、進路指導で私立高校を併願する生徒が減ったことを実感している。「3、4時間目にきて給食を食べて、またいなくなる子がいる」とも話した。 就学援助費については、昨年3月の法改正で05年度から、自治体が独自に資格要件を定めている「準要保護」への援助に対する国庫補助がなくなった。一部の自治体では06年度の予算編成に向け、準要保護の資格要件を厳しくするなど、縮小への動きも始まっている。 ■二極化に驚き 〈苅谷剛彦・東大教授(教育社会学)の話〉塾に1カ月に何万円もかける家庭がある一方で、学用品や給食費の補助を受ける子どもがこれだけ増えているのは驚きだ。教育環境が、義務教育段階でこんなに差があって、次世代の社会は、どうなってしまうのか。こうした中で、国は補助金を一般財源化した。今後、自治体が財政難を理由に、切り捨てを進めるおそれもある。機会の均等もなし崩しになっては、公正な競争社会とは呼べない。 〈キーワード・就学援助〉学校教育法は、経済的な理由で就学に支障がある子どもの保護者を対象に「市町村は必要な援助を与えなければならない」と定めている。保護者が生活保護を受けている子ども(要保護)に加え、市町村が独自の基準で「要保護に準ずる程度に困窮している」と認定した子ども(準要保護)が対象。 生活保護受給者が100万世帯を超えた。
生活保護を受ける人たちは「自助努力」が足りないといえば、それまでかもしれませんが、根本的に解決をはからないと、みんなで支えきれなくなってしまいます。 その上、治安も悪化して、犯罪の発生件数が250万件、検挙者は35万人以上です。 こんな世の中で大丈夫でしょうか?本当に日本の将来が不安です。なんとかして社会システムを変えていかないと、戦後、みんなで頑張って作り上げた「日本」が崩れていきます。 しんぶん赤旗の中には「所得格差」のことも書いてありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||