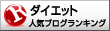・正月行事 しょうがつぎょうじ
お正月は、年の初めで様ざまの行事がひしめき合っています。お正月をはじめ、日本のさまざまな行事は稲作などの農耕に深く結びついているようです。特に正月の行事は、1年の農耕と繁栄を司る歳神(としがみ)様をおもてなしする接待行事です。「1年の計は元旦にあり」というように、日本人に根付いています。
1月を睦月と言います。もとは旧暦1月の呼称でしたが、今日の日本では新暦(グレゴリオ暦)の1月のことです。 睦月の語源では1月は年始であり、新年を迎え親族知人が集まって互いに往来し、仲睦まじく宴を催す月としています。
年神様(正月様・歳徳神[としとくじん]・祖先霊の神)が、日の出と共に降臨(こうりん)するのは元旦、元旦は1月1日の朝のことを元日は1月1日の意味としています。元旦に初日の出のご来光を、初詣(はつもうで)をして新年が寄りよい年となるように拝(おが)みます。
現在は、年頭の祝いをする三が日で一年の最初の日である元日から3日までです。松の内は元日から7日または15日までをいいます。
松の内とは、正月飾りの一種の松飾りを飾っておく期間の事です。 松飾りの門松は歳神様が道に迷う事なく家に来るための目印とも、家に年神様の滞在を示す印とも言われています。年神様は鏡餅に宿ると言われており、松の内は鏡餅を飾って年神様をお迎えします。
正月に餅を食べる風習は、平安時代初期935年頃の紀貫之の『土佐日記』に、正月に餅を食べ稲の霊力を吸収し、よき歳を重ねることへの願いを込めた歯固め餅(はがため・よわいがため)の記述が残されています。
正月に雑煮を食べますが雑煮とは ごった煮でもあり、古く上方((かみがた)では五臓を保養するものとして保臓(ほうぞう)とよんでいました。四条家園部流膳部之巻(しじょうけそのべりゅうぜんぶのまき)で臓煮の字をあてるのもこの例です。
正月に餅を食べる風習は、平安時代初期935年頃の紀貫之の『土佐日記』に、正月に餅を食べ稲の霊力を吸収し、よき歳を重ねることへの願いを込めた歯固め餅(はがため・よわいがため)の記述が残されています。
正月に雑煮を食べますが雑煮とは ごった煮でもあり、古く上方((かみがた)では五臓を保養するものとして保臓(ほうぞう)とよんでいました。四条家園部流膳部之巻(しじょうけそのべりゅうぜんぶのまき)で臓煮の字をあてるのもこの例です。
宮中の女房詞(ことば)では烹雑(ほうぞう・ぼうぞう)ともいいます。
お汁粉は、小豆(あずき)の赤に魔よけの意味があります。正月の祝い膳は、順番がありお屠蘇から始まり黒豆、数の子などの祝い肴、その他おせち料理、雑煮の順です。屠蘇は中国では7世紀頃の唐の時代に始まったとしています。
日本には平安時代に伝わり、宮中では「元日御薬」という名の儀式が行われ一献目に屠蘇、二献目に白散(びゃくさん)、三献目に度嶂散(どしょうさん・とちょうさん)とそれぞれ違う薬酒を一献ずつ飲むという決まりがありました。
室町幕府は白散のみ、江戸時代は屠蘇のみを用いるというようにと変化しています。庶民の間には江戸時代の頃に伝わり医者が薬代の返礼として屠蘇散を配り歩いたのが始まりと言われます。
2日は、以前は初荷として商(あきな)い始めの日とし荷を旗、のぼりを飾りつけ取り引き先に運んでいましたが、現在では企業単位で4日に行われることが多くなりました。さらに、2日は初夢(1年の吉凶を占う)、書初めの日ともしています。
2日は、以前は初荷として商(あきな)い始めの日とし荷を旗、のぼりを飾りつけ取り引き先に運んでいましたが、現在では企業単位で4日に行われることが多くなりました。さらに、2日は初夢(1年の吉凶を占う)、書初めの日ともしています。
6日は出初式です。7日は七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ)、2021年は、11日が成人式です。
松の内は年神様が鏡餅に宿っているので、松の内が終わってから、11日に鏡開きをします。鏡餅を割るのは正月の終わりとその年の仕事始めを意味し皆で分け合い振舞われています。新年の仕事の始まりの行事でした。
松の内は年神様が鏡餅に宿っているので、松の内が終わってから、11日に鏡開きをします。鏡餅を割るのは正月の終わりとその年の仕事始めを意味し皆で分け合い振舞われています。新年の仕事の始まりの行事でした。
お年玉は、古くは神仏の加護を得るため、お供えしたお餅をおさがりとして子供達に食べさせることを御年魂(おとしだま)と呼んでいました。年の賜物という説です。
松の内で正月の大きな行事が一段落、小正月にあたる15日、正月飾りや書き初めを燃やす行事で左義長(さぎちょう)といい、その煙に乗って年神様が天上に帰ってゆくというもので各神社でおこなわれます。左義長は、三毬杖(さぎちょう)という青竹で正月飾りの門松、しめ縄などを焼いたことに由来します。
松の内で正月の大きな行事が一段落、小正月にあたる15日、正月飾りや書き初めを燃やす行事で左義長(さぎちょう)といい、その煙に乗って年神様が天上に帰ってゆくというもので各神社でおこなわれます。左義長は、三毬杖(さぎちょう)という青竹で正月飾りの門松、しめ縄などを焼いたことに由来します。
「どんど焼き」「とんど」ともいいます。左義長は中国漢時代の正月行事として行われ、爆竹によって厄除けしたといわれています。わが国では承久元年(1219年)より鎮護国家、五穀豊穣を祈る祭りとしておこなわれてきました。
この行事ででひとまず終了、正月気分も一掃です。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
この行事ででひとまず終了、正月気分も一掃です。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
初版2020,1,3