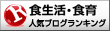・陸封の生物Land-sealed creaturesland‐lock りくふうのせいぶつ
魚介の中には一生のうちに海水と陸水に生息する時期とをもつ生物がいます。長い歴史の中で地殻変動などがあり地形その他環境の変化で湖・池ができ陸の中に閉じ込められ一生そこで生活せざるをえなくなってしまった生物です。
その生物は河口・汽水域にも見られています。もともとは海に住んですんでいた生物なのですが河口・汽水に移動していて、やがては淡水の湖沼などに封じ込められた為に、そこで淡水の生物として生き延びるべくして世代を重ねているのです。
食用とする魚介類についての記載です。
主にサケ科(姫鱒・ヤマメ・イワナなど)の魚に見られています。鮎、イサザアミ(アミ科)、しじみ(シジミガイ科)の類があります。
サケの仲間では、一生の間に淡水と海の間を往復、同種で海で育つ走海型(降海型)のものと、実際の湖沼残留型(陸封型)としている淡水で一生を過ごす魚種があります。一般に陸封型は降海型に比べ小型の傾向です。
◇姫鱒Oncorhynchus nerka ひめます
サケ科、陸封型でカナダ・アメリカ・北海道の阿寒湖が原産地です。主にプランクトンの小さな動物を好んで餌として3~4年で産卵期を迎えます。体長30~60cmぐらいで6~7月に捕獲し旬です。
9月下旬から11月頃までの産卵期には体を赤く染め海で主に生息する紅鱒(紅鮭)の系統であることを示しています。紅鱒(紅鮭)の陸封(海の魚が淡水に定住:いわな、虹鱒、姫鱒)したもので明治時代に養殖して全国の湖に放流が始まり和井内貞行が十和田湖に放流したのは良く知られます。紅色の魚肉で刺身、塩焼き、粕漬け、フライ、燻製にしています。
&紅鱒/紅鮭Red salmon べにます
サケ科、主に千島列島から北アメリカ西岸にかけての北太平洋の海域に分布しています。秋から冬、上流に湖のある河川をさかのぼり、砂礫上に産卵します。100g中でエネルギー127cal、水分71.4g、タンパク質22.5g、脂質4.5g、炭水化物0.1g、灰分1.5g、ビタミンA27μgを含みます。
◇山女・山女魚Cherry trout/ Oncorhynchus masou やまめ
サケ科、全長20~30cm、その女性的美しさから渓流の女王と呼ばれます。桜鱒の陸封で一条木ため池(秋田県)でよく知られ関東以北の山間部、渓流に生息するが最近は、養殖し放流しています。ヤマメの上流にはイワナが棲むといわれます。9~11月に産卵、サケ科の多くは、寿命が短く産卵にエネルギーを使い果たし2~4年で産卵後死に至るものが多いようです。
◇岩魚Bull trout いわな・オショロコマ
サケ科イワナ属、日本では、北海道から中国以北の山間の渓流に生息する淡水魚で冷水を好み九州にはあまり見かけないようです。自然状態で交雑のマスの陸封された魚といわれます。鮎の昇れないところにヤマメ(山女魚)がいてヤマメが昇れないところに岩魚が住むといわれます。
◇天魚 雨女魚 あまご
サケ科サケ属、サクラマスの亜種といわれ降海型はサツキマス(五月鱒)、陸封型・河川残留型はアマゴと呼ばれます。山女とアマゴは似ており、 アマゴは関東以南の太平洋岸河川の上流にすみ、全長約30cmに成長し、山女魚は日本海側と関東以北に多く生息します。産卵期は10月前後1ヵ月ぐらいで寿命は4~5年といわれ養殖が盛んです。
◇鮎Sweet smelt あゆ
キュウリウオ科、アユ亜科 アユ属の分類です。日本全国各地のきれいな河川、湖、海にもいますが主に川魚としています。秋に川を下り下流で卵を産み孵化して川の流れに乗って汽水域ないし海の浅瀬で冬の間を過ごし水ぬるむ春になると川の中流付近まで登り藻を食べ生活しています。
やがて秋になると立派に成長し川を下り卵を産み一生を終えるのです。
寿司ネタに姿がいいので姿寿司にしたり、塩焼きには、おどり串とし形を生かす料理に、若鮎は、頭より丸ごと食べられ揚げ物にも利用しています。うろこ、筋肉に寄生虫がいることがあるので刺身などの生食は避けた方がよいでしょう。
体長20cmほどに成長した秋口の産卵期は、餌をとらないため味が落ち、みそ焼き、粕漬け、甘露煮がよいようです。
鮎のハラワタ、それぞれ内蔵、白子、卵を原料としてうるかという塩辛があります。
養殖鮎が多く出まわるようになって香気が失われ、脂肪が多く天然ものに比べだいぶ見劣りがするといわれています。
◇白魚Japanese icefish しらうお
サケ目シラウオ科、日本全国、北海道より九州の湖沼、沿岸に生息し立春を過ぎた頃より早春、河口付近に産卵にやってくる、降海型と陸封型のふたつのタイプがあります。寿命は1年程で2~4月を旬としています。欧米の沿岸では成育の確認がなく、日本近海だけの温帯性、東洋の特産魚といわれます。
他にもギンブナ、ドジョウ、ナマズなどが河川や湖沼に生息しています。
スナヤツメ、ヤリタナゴ、シナイモツゴ、ホトケドジョウ、メダカ、アカザ、カジカなどは少なくなっているようです。
魚 類 遡上タイプ別リスト |帯広開発建設部 (mlit.go.jp)
の一覧の掲載です。抜き書きしました。
一次淡水魚(一生を淡水で生活する):コイ・ヤツメウナギ・ドジョウ・ギンブナ・モツゴ・ヤチウグイ・モロコ
その他の淡水産:たにし・テナガエビ・アメリカザリガニ・スジエビ・サワガニやモクズガニ
陸封性(元々は海や汽水にいたがのちに一生淡水で生活している):ヤマメ・イワナ・アメマス・ウグイ・ニジマス・ハナカジカ・ワカサギ・イトウ
降河性(海で産卵、成長して川を昇って育ち秋に産卵の為海に下っていく):ウナギ
遡河性そかせい/昇河性しょうかせい1(産卵の時だけ川に来る。ふ化してすぐ沿岸海域で生活):キュウリウオ:ワカサギ・シシャモ
遡河性2(産卵の時だけ川にやって来て孵化後は、しばらく川にいて、やがて沿岸海域で生活):サケ・カラフトマス
遡河性3(成熟前に川に来て、後に産卵する。ふ化後かなり川にいて沿岸海域で生活):サクラマス・アメマス・ウグイ・イトウ・カワヤツメ
両側回遊(ほとんど川で生活しているが、汽水域、沿岸海域でも生活):ウキゴリ・ヨシノボリ・ジュズカケ・ハゼ
陸封の生物は、もともとは海に住んですんでいた生物なのですが陸水の河口・汽水に移動していて、やがては淡水の湖沼などに封じ込められた為に、そこで淡水の生物として生き延びるべくして世代を重ねている生物です。現在海産として見つかっていない淡水に生息する生物は一次淡水生物となるようです。
現在の魚類2万8,000種(海水魚16,700種・淡水魚11,300種)のうち約43%が淡水魚といわれていますが、淡水域に進出し適応した海水魚が、淡水魚へ進化したのではと推測しています。遺伝子の研究で判明しています。
淡水魚がいる陸水は、地球上に存在する全ての水のうち0.01%にも満たず、海水は97.5%、海水魚よりも狭い生物圏で淡水魚は、隔離状態で種分化が促進されやすい環境などで、もたらされたのではと考えられています。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。