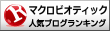・四方草Mugwort よもぎ
明日の3月3日は、🎎雛祭りです。ひな祭りに蓬の入った草もち、菱餅を作る習慣があります。
旧暦3月3日は現在の新暦の暦で4月初旬、蓬も芽生え、季節の桃の花を飾ることもできました。
五節句のひとつで3月3日は、上巳〈じょうみ・じょうし〉桃の節句・雛の節句ですが節句の行事は、中国より奈良時代に伝えられ季節の節目に、季節を感じ心豊かに暮らせること、体調を崩しやすい季節の変わり目に「無病息災」を願い豊作、健康、子孫繁栄を人々がお互いに無事に過ごせることを神に祈り食物を供(そな)え祝う行事です。
古来からの中国では、上巳節に母子草(ははこぐさ:ごぎょう)を入れたお餅を食べる風習がありました。よもぎをもち草とするまで母子草は、もち草ととして使われていたようです。
やがて日本に伝わり、ひな祭りにひな人形を飾り、お供えとして桃の花、桃花酒から白酒、草もちは菱餅ともして母子草ないし蓬は邪気払い、菱形については、心臓をも意味し形づくって大切なものです。
それに3色の白、緑、赤で着色して季節をも表したり、薬用植物のよもぎ(緑)、菱の実(白)、くちなしまたは、紅花(赤)を使いひし形にして菱の実の四角い突起のある形にして魔よけにした言い伝えなどがあります。
蓬Japanese mugwortは、キク科、日本、中国を主産地としています。全国各地の野山に自生、春菊と同じようなかたちをし、葉の裏側は、白っぽくうぶげがあります。夏、秋になり成長すると1mほどに成長し淡褐色の小さな花をたくさん咲かせます。
四方に根茎を伸ばし繁殖するすることから四方草(よもぎ)、よく燃える善燃草(よもぎ)など語源に諸説あります。
春3~5月に新芽が出た頃の軟らかい葉を摘み取り軟らかめに茹で水にさらし苦味を抜きし多くは草もちの材料とし塩漬け、冷凍し保存できます。
茹でて晒したものをそのままお浸し、汁の実、炊きこみご飯、佃煮に、またすり鉢でよく擦って上新粉、白玉粉とよく混ぜ弥生3月の草もち(よもぎ餅)に利用しています。主に草もちに利用されることからモチグサともいわれているのです。
根をよく洗いよもぎ酒、新芽の若葉を青汁、粉末としたり、綿毛を乾燥させもぐさの原料としています。
葉の茹でたもの100g中でエネルギー42kcal、タンパク質4.8g、脂質0.1g、炭水化物8.2g、
灰分1.0g、ナトリウム3mg、カリウム250mg(生890mg)、カルシウム140mg、マグネシウム24mg、リン88mg、鉄3.0mg、亜鉛0.4mg、銅0.28mg、マンガン0.75mg、
ビタミンA:1000μg、ビタミンD:(0)μg、ビタミンE:3.5mg、ビタミンK:380μg、
ビタミンB1:0.08mg、ビタミンB2:0.09mg、ナイアシン0.5mg、ビタミンB6:0.04mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸150μg、パントテン酸0.91mg、ビタミンC19mg 食物繊維4.2gを含みます。
葉緑素が毛細血管の拡張、抗アレルギー、免疫力を高めます。グリーンのすがすがしい香りがあり精油(シネオール)しアロマセラピー(芳香療法)に、苦味成分のサントニンSantoninを駆虫に用います。血行促進、鎮痛、鎮静、疲労回復、抗菌、解毒作用があり入浴剤としても利用しています。
タンニンの殺菌、抗炎作用によりアトピーなどの痒みを和らげます。
漢方で艾葉(がいよう)といい葉を乾燥させて加工したものをお灸として使用します。煎じて飲用とし健胃、腹痛、下痢、貧血、冷え性などにも使います。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。