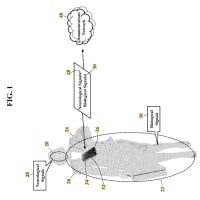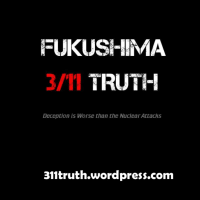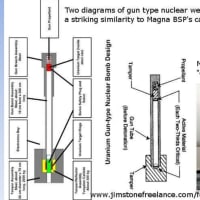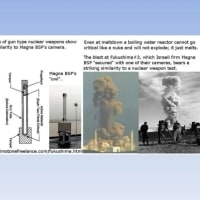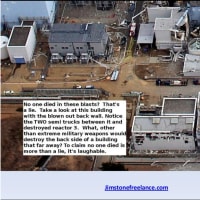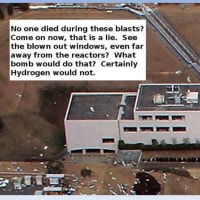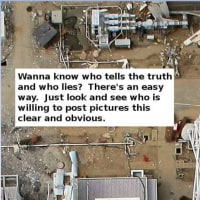2018年2月15日ヤフーブログに投稿した記事より
フォークランド紛争と竹島問題の比較は現在のイギリスと日本の安全保障の比較のモデルケースであると同時に、両国の為政者(ノットイコール、エリート)の比較でもある。
イギリスという国はローマカトリック教会の秩序の中にいないイギリス国教会の長でもある「女王」が君臨している国、殆んどの戦争で勝利者側にいた国、スペインのように、7つの海を征服した後で普通の国にまで「没落してしまった」わけでは決してない(と思わせる何かがある)国、「他の国が持たない何かをもっている」国だと思う。
例えとして、ナポレオン戦争のときの「ワーテルローの戦い」について、ウェリントン公爵が「ワーテルローの戦いはイートン校の運動場で成し遂げられた」という名言を残したとされているが、(実際はこのような発言があったのではなく、ウェリントン公死後に出版された「イングランドの政治的未来」(シャルル・モンタラベール:1855)の中の一節であったそうだが)、この言葉の意味するところは、「国の命運を左右するのはその国を背負っているエリートの資質である」ということではないだろうか。
フォークランド紛争(1982)当時、日本人の多くは、イギリスが国を挙げて南米の小さな島の領有権を守る姿に、驚きの目を向け、アナクロニズム的な感覚すら感じた(若い人間はとくに)のではなかっただろうか。
しかし、この島がイギリスにとってどんな歴史的な意味を持っていたのかを理解すれば、また今日われわれが絶えず「鬱陶しさ」さえ感じている「竹島問題」との比較で考えても、イギリスの姿勢の正しさに羨望を禁じ得ず、対照的に、日本の卑屈さ、「ことなかれ的な無為無策ぶり」と、「戦後の自虐史観で地に落ちた『国家観』のなさ」、国家としての「矜持」のなさに絶望感すら感じてしまう。
韓国の1952年の「海洋主権宣言(李承晩ライン)」から今日までの日本外交はお粗末すぎる。国交が回復していなかった52年から65年までの間に、韓国沿岸警備隊によって竹島周辺の日本人漁民44人が虐殺、328隻、3929人もの日本人漁民、漁船が拿捕抑留されるという事件が起きたのだ。せめてICJに提訴するなり、日米安保条約(1960)締結後にアメリカ海兵隊の巡回を依頼するなり、日韓の経済交流と技術支援をやめるなどの制裁を加えるなり、やれることを本気でやらなかったのは何故だったのだろう。恐らくそれをやると、むしろ日本国内で起きるかもしれない潜在的な脅威があるからに他ならなかったからではないだろうか。
拿捕された漁民を人質にとられ、韓国や在日韓国人にあまりにも多くのものを与えてきて、尚、「千年被害者」面される始末。「盗人に追い銭」のような状態。
ここで、再びイギリスと日本の違いがどこにあるのかと考えてみて、日本の国としての命運を左右するべき人材が、いずれAIで置き換えてもいいような「優秀な」官僚養成のための偏差値教育しか受けられないような教育の現状にも問題があるのではないだろうか、と思う。
そして、国家のためならば(国王になる長男はおくとして)次男のアンドルー王子に、”noblesse oblige”のため、対潜水艦攻撃用ヘリコプターの副操縦士として航空母艦に乗艦するよう命じたエリザベス女王のような君主の不在。象徴天皇が政治的な意思を示されることはないので、ここでは誰がその立場にあるのかといえば、やはり総理大臣でしょうか。現在の安倍総理にもう少し、まだ期待したいところです。
それでも、今の日本の政治に限界があることもわかるので、今後の日本を担う「真のエリートを育てる教育」こそが望まれる。
現実の問題としての憲法改正の議論も、長年9条が「神聖視」されているような有様で、現実的かつ冷静な議論が回避されてきたことも実は「平和ぼけ」というよりも思考停止状態のようなものだと思う。もっと理性的にあらゆる想定で議論されなければならないのに。
最後は自分たちの国は自分達で守るという覚悟がなければ、どこかの国の大統領のように、支離滅裂な「もの乞い外交」をやるしかなくなるのだ。

イートン校
フォークランド紛争と竹島問題の比較は現在のイギリスと日本の安全保障の比較のモデルケースであると同時に、両国の為政者(ノットイコール、エリート)の比較でもある。
イギリスという国はローマカトリック教会の秩序の中にいないイギリス国教会の長でもある「女王」が君臨している国、殆んどの戦争で勝利者側にいた国、スペインのように、7つの海を征服した後で普通の国にまで「没落してしまった」わけでは決してない(と思わせる何かがある)国、「他の国が持たない何かをもっている」国だと思う。
例えとして、ナポレオン戦争のときの「ワーテルローの戦い」について、ウェリントン公爵が「ワーテルローの戦いはイートン校の運動場で成し遂げられた」という名言を残したとされているが、(実際はこのような発言があったのではなく、ウェリントン公死後に出版された「イングランドの政治的未来」(シャルル・モンタラベール:1855)の中の一節であったそうだが)、この言葉の意味するところは、「国の命運を左右するのはその国を背負っているエリートの資質である」ということではないだろうか。
フォークランド紛争(1982)当時、日本人の多くは、イギリスが国を挙げて南米の小さな島の領有権を守る姿に、驚きの目を向け、アナクロニズム的な感覚すら感じた(若い人間はとくに)のではなかっただろうか。
しかし、この島がイギリスにとってどんな歴史的な意味を持っていたのかを理解すれば、また今日われわれが絶えず「鬱陶しさ」さえ感じている「竹島問題」との比較で考えても、イギリスの姿勢の正しさに羨望を禁じ得ず、対照的に、日本の卑屈さ、「ことなかれ的な無為無策ぶり」と、「戦後の自虐史観で地に落ちた『国家観』のなさ」、国家としての「矜持」のなさに絶望感すら感じてしまう。
韓国の1952年の「海洋主権宣言(李承晩ライン)」から今日までの日本外交はお粗末すぎる。国交が回復していなかった52年から65年までの間に、韓国沿岸警備隊によって竹島周辺の日本人漁民44人が虐殺、328隻、3929人もの日本人漁民、漁船が拿捕抑留されるという事件が起きたのだ。せめてICJに提訴するなり、日米安保条約(1960)締結後にアメリカ海兵隊の巡回を依頼するなり、日韓の経済交流と技術支援をやめるなどの制裁を加えるなり、やれることを本気でやらなかったのは何故だったのだろう。恐らくそれをやると、むしろ日本国内で起きるかもしれない潜在的な脅威があるからに他ならなかったからではないだろうか。
拿捕された漁民を人質にとられ、韓国や在日韓国人にあまりにも多くのものを与えてきて、尚、「千年被害者」面される始末。「盗人に追い銭」のような状態。
ここで、再びイギリスと日本の違いがどこにあるのかと考えてみて、日本の国としての命運を左右するべき人材が、いずれAIで置き換えてもいいような「優秀な」官僚養成のための偏差値教育しか受けられないような教育の現状にも問題があるのではないだろうか、と思う。
そして、国家のためならば(国王になる長男はおくとして)次男のアンドルー王子に、”noblesse oblige”のため、対潜水艦攻撃用ヘリコプターの副操縦士として航空母艦に乗艦するよう命じたエリザベス女王のような君主の不在。象徴天皇が政治的な意思を示されることはないので、ここでは誰がその立場にあるのかといえば、やはり総理大臣でしょうか。現在の安倍総理にもう少し、まだ期待したいところです。
それでも、今の日本の政治に限界があることもわかるので、今後の日本を担う「真のエリートを育てる教育」こそが望まれる。
現実の問題としての憲法改正の議論も、長年9条が「神聖視」されているような有様で、現実的かつ冷静な議論が回避されてきたことも実は「平和ぼけ」というよりも思考停止状態のようなものだと思う。もっと理性的にあらゆる想定で議論されなければならないのに。
最後は自分たちの国は自分達で守るという覚悟がなければ、どこかの国の大統領のように、支離滅裂な「もの乞い外交」をやるしかなくなるのだ。

イートン校