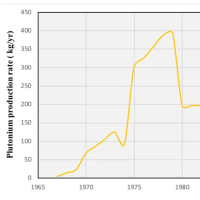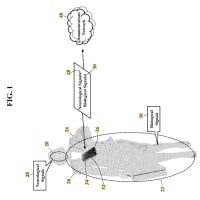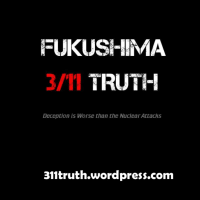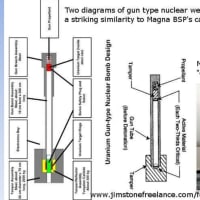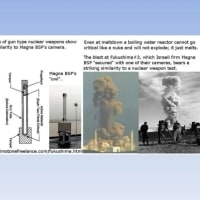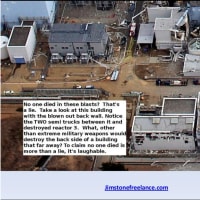2019/2/6(水) 午後 7:30
好きな映画監督なのですが、ビクトル・エリセ監督は1940年にスペインのバスク地方で生まれました。バスク地方というのは、ピレネー山脈のフランスとスペインにまたがる地域で、そこに暮らす人々はバスク語を話し、自らをバスク人と呼ぶそうです。道路標識や看板も、バスク語、スペイン語、英語表記だとか。また、この地域の人々は日本人のように繊細で勤勉な気質で、芸術と美食の文化をもっているそうです。
エリセ監督はそういう地域で17年間ほど過ごし、その後は首都マドリードに移り住み、政治学と法学を学んだ後に、20歳のときにスペイン国立映画学校に入学し映画製作を学びました。1973年から1992年までの約20年間につくった長編作品はたったの3作品。その他オムニバス作品に参加しておられ、例えば東日本大震災を受けて河瀬直美の呼びかけにより制作された21人の映画監督による3分11秒の短編映画集にも参加。
長編作品
「ミツバチのささやき」El Espiritu de la colmena (1973)、
「エルスール」 El Sur (1982)
「マルメロの陽光」El Sol del membrillo (1992)

オムニバス
「挑戦」Los Desafios (1969)、
「10ミニッツオールダー人生のメビウス・ライフライン」Ten Minutes Older: The Trumpet / Lifeline (2002)
「3・11 A Sense of Home Films 」(2011)
「ポルトガル、ここに誕生す~ギマランイス歴史地区」(2012)
「ミツバチのささやき」(73年)
スペインのとある田舎の村に住んでいる姉妹が村の公民館のようなところで上映された映画「フランケンシュタイン」を観たところからお話しが始まります。
ヒロインは姉妹の内の妹でアナという名の少女。その役を演じた子役の名もアナ・トレントという名なので、恐らく、自分の名前の役を、現実なのか映画の撮影なのか、彼女は夢うつつのままに演じていたのかもしれません
アナ・トレントは後に大人になってからも女優となって演じている作品があり、興味があったので観てみましたが、子役の頃の彼女の宝石の原石のような輝きが失われていました。とにかく、この映画の最大の見どころは、この「アナ」の可愛らしさ、愛くるしさにつきます。そして、エリセ監督の映画の全てにいえるのですが、台詞が最小限度で、この映画も静かに静かに、日常の場面と、その中で起こる「夢うつつのような非日常」とが、少女「アナ」の目を通して描かれていました。
「マルメロの陽光」(92年)
スペインの画家アントニオ・ロペス・ガルシアが自宅の庭に実ったマルメロの実を描く姿を撮ったドキュメンタリー映画です。日本でも一部の映画館で上映され、その当時、待望の3作目だったこともあり、私も日比谷の映画館に観に行きました。台詞が殆んどない、静かな静かな、哲学的な作品です。
この映画は観終わったとき、「人間もマルメロの実と同様、実り、熟したあと、やがて土の上に落ち、朽ちてゆくのである」という、人間も自然界の一部にすぎないという哲学を台詞ではなく映像を通して語りかけてくる作品。
太陽の光を浴びて輝いているときすでに、陽光を浴びる昼間と夜との変化の中で、マルメロの実が刻々と翳りを帯びてゆく光景や、画家のガルシアがいろいろな角度から、ああでもないこうでもないと、陽光を受けて輝くマルメロをキャンバスの中に写しとろうとするも、納得のいく作品がなかなかでき上らない様子、そして日没後に疲れ果てて自分のベッドの上に横たわっている姿も描かれており、「土に落ち、朽ちていくマルメロの実」と「死んだように疲れて眠っている、老いた画家自身」がちょうど二重写しに描かれていて、「死」はまさに「実が地面に落ちて土に戻ること」なのだという感覚が極めて自然に心に入ってきます。そこには「死」を「誰にでも訪れる休息のようなもの」としてもとらえられているようにも思えました。
エリセ監督の長編第一作にして代表作である「ミツバチのささやき」(73年 スペイン)
El Espiritu de la colmena
https://youtu.be/aqvpMJNlqxE
コメント
バスク語は興味深いです。発音や構造や活用形態は、丸で知りませんが。恐らくは、外敵が侵入しずらい、孤立した地域で有ったのでしょうね。スイスの山間の僻地に古いロマン語が残っているという事を読みました。支那の奥地、雲南にも特有の言語がのこっているらしい。消滅しない内に採取し残す事が課題でしょうね。
2019/2/7(木) 午前 9:25[ 井頭山人(魯鈍斎) ]
> 井頭山人(魯鈍斎)さん
こんにちは。コメントをありがとうございます。各地域に古くからある言語というのは、文化人類学的に貴重な財産ですね。言語はその地域の独自の風土に根差しており、それを駆使する人々の精神にも影響を与えるもので、そこから生まれる文化や芸術にも大きく寄与しているようです。
2019/2/7(木) 午後 1:57kamakuraboy
「ミツバチのささやき」を探しにわたしのまちのレンタルDVD ショップに行きましたが、田舎町なものでありませんでした。
隣市の大きなツタヤに行きましたがやはりありません。
でも、係の方がパソコンで調べて取り寄せてくださって、1週間後に借りられることになりました。
楽しみですね。
2019/2/10(日) 午後 9:16[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
こんばんは。コメントをありがとうございます。古い作品なので探すのが大変だったようですね。私の大学時代の友人二人は、昔私の家でこの映画を一緒に観たとき、あまりに静かな静かな展開で途中から眠くなっていました。私は気にいっていた映画ですが、感性というものは人それぞれだと感じた次第。
2019/2/10(日) 午後 9:41kamakuraboy
レンタルDVDショップから「『ミツバチのささやき』が届いています」の電話があって借りてきて観てみました。
子どもの目を通してみた世界のお話なのでしょう。
アナにとっては、現実と空想の区別も明確ではなくて、どちらも実際のことって感じてしまっているのでしょう…?
どちらかというと、難しい内容でした。
2019/2/14(木) 午後 11:09[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
おはようございます。映画をご覧になったのですね。「どちらかというと、難しい内容」との感想、確かに台詞が少なく、エリセ監督の背景的なものを知らなければ、この映画が何を表しているのかということがつかみにくい作品だと思います。
映画の設定は1940年頃のスペイン内戦直後のフランコ体制下のとある村のお話し。そこでスペインの内戦とフランコ独裁体制などのスペインの現代史をみながら、映画の解釈を記事に書いてみました。
2019/2/15(金) 午前 6:59kamakuraboy
ブログの中に、
> この映画の最大の見どころは、この「アナ」の可愛らしさ、愛くるしさにつきます。とありますので、kamakuraboyさんは「可愛らしさ、愛くるらしさ」だけで満足なのかなって思いましたが…
でも、
タイトルに「フランコ独裁体制下のスペイン」とあったり、コメントの中に「スペインの内戦とフランコ独裁体制」とありますので、可愛らしさ、愛くるらしさだけのお話ではないと思われます。
以前、沖縄の基地問題のお話のときにどちらかというと沖縄の人たちではなくて政府の考え方を支持していたり、韓国との問題などの問題に関しても、武力行使や戦争を肯定する
わけではないとしつつも時と場合にはそれも致し方ないっていった感じでしたが…
同じようにこのブログのお話についても、一般ピープルサイドではなくて体制側を応援しているっていうことなのでしょうか…?
2019/2/15(金) 午後 1:39[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
映画の最大の魅力はやはりアナのあどけない可愛らしさにつきると思います。しかし幼いアナの目を通してこの映画の中でエリセ監督が描きたかったことは何だったのかということを、映画の時代背景やエリセ監督自身のバックボーン、個々の登場人物像に注目してみると更に面白いので書いてみました。よかったら読んでみてください。
2019/2/15(金) 午後 2:35kamakuraboy
weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
辺野古反対をやっている人々は一般の沖縄県民ではありません。プロ市民です。在日韓国人や中国人が圧倒的です。戦前から普通の外国籍の出稼ぎ労働者の人々に紛れて日本には多くの外国籍工作員が入り込んでいました。
韓国との問題で積極的な武力行使を支持する考えを示したことはないと思いますが。あくまでも日本人の生命財産を守るべきは米国頼みではなく日本国民自らで守るべきだという考えなのです。
韓国が嘗て竹島周辺で漁民を殺傷し拿捕し、人質にとって日韓条約交渉を有利に進めた経緯があるのです。泣いた赤鬼さんは失礼ながらこの経緯について全くご存知ないのですか。
2019/2/15(金) 午後 7:40kamakuraboy
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
日本人ならば、いくら相手がすぐ隣国であっても、そのような歴史的事実をありのままに知った上で、二度とそのような目にあわないように、日本国民の生命と財産をしっかり守るのが日本政府の果たすべき役割だという考えで、沖縄の米軍基地もだから危険な市街地にある普天間より、人口の少ない辺野古に移転すべきだと思っているまでです。
ご自身で、普天間周辺と辺野古をみて来られたら良いと思いますよ。それらがどのような立地で、現実の沖縄県民の人々のお考えがどのようなものなのかを。
私は無知で無責任な平和主義者ばかりでは国家は守れないと思っております。
2019/2/15(金) 午後 7:41kamakuraboy
> kamakuraboyさん
【「ミツバチのささやき」とフランコ独裁体制下のスペイン 2019/2/15(金) 午前 7:00】に目を通させていただきました。
kamakuraboyさんがお書きになりましたように、幼いアナの目を通してこの映画の中でエリセ監督が描きたかったことは
映画の時代背景
エリセ監督自身のバックボーン
個々の登場人物像
に注目して観ていかないと掴むことができないということで、やはり難しいなぁって思わせられてしまいました。
2019/2/15(金) 午後 10:24[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> 辺野古反対をやっている人々は一般の沖縄県民ではありません。プロ市民です。在日韓国人や中国人が圧倒的です。戦前から普通の外国籍の出稼ぎ労働者の人々に紛れて日本には多くの外国籍工作員が入り込んでいました。
→ このお話は初めて耳にしました。
> 韓国が嘗て竹島周辺で漁民を殺傷し拿捕し、人質にとって日韓条約交渉を有利に進めた経緯があるのです。泣いた赤鬼さんは失礼ながらこの経緯について全くご存知ないのですか。
→ そのようなことがあったっていうことはこれまで知りませんでした。また、なかなか信じられません。
> 漁民を殺傷し拿捕し、人質にとって
っていったことは、韓国の漁民などの一般人ではなくて、軍隊がということだったのでしょうか…?
2019/2/15(金) 午後 10:25[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> そのような歴史的事実をありのままに知った上で、
> 二度とそのような目にあわないように、
→ 1つ前のコメントに書きましたが、にわかには信じることができない気持ちです。
> 無知で無責任な平和主義者ばかりでは国家は守れない
→ わたしのことを言っているのだと思いますが、日本人のたいていのみなさんはそのようなことをご存じなのでしょうか…?
2019/2/15(金) 午後 10:26[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
顔アイコン> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
拙ブログ記事の「朝鮮戦争」のところの最後に「補足」として竹島を不法占拠されるに至った経緯を書いてます。「李承晩ライン」「竹島」で調べれば同様の記載がありますが、
「サンフランシスコ講和条約(51年9月署名、52年4月開始)では、日本が放棄すべき領土に竹島が含まれていなかったにもかかわらず、52年1月に李承晩は一方的に「李承晩ライン」を設定。52年4月朝鮮戦争のさなか、韓国は武装警察を投入し、竹島を不法占拠。「李承晩ライン越境」を理由に日本漁船328隻を拿捕し、日本人44人を死傷(死亡者数は不明)、3,929人を抑留。韓国側からの海上保安庁巡視船への銃撃等の事件は15件におよび、16隻が攻撃された。拿捕された漁民は65年の条約締結まで解放されず、これらの漁民を人質にしたことで、日韓基本条約を韓国は自国有利にし、朝鮮戦争当時日本に押し寄せた不法上陸者である在日韓国人の居住資格(在日1世と2世まで)の許可を日本から引き出したのであった。」
2019/2/16(土) 午前 2:17kamakuraboy
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
「拘束された日本人漁民の釈放の代わりに日本の刑務所で常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている韓国人受刑者の釈放を要求し、(しかし当時の朴正熙大統領はこれらの人々の韓国への帰国は認めず)日本政府はその要求を受け入れて受刑者472人を釈放し永住許可を与えたとされる。」
まぁ、ご自分で調べてみた方がよいと思いますよ。当時の新聞が国会図書館などに残っているはずですから取り寄せられるはずですよ。それから日本以外の国が「竹島」をどう考えているのかなども。
良かったらその結果を教えて下さい。
2019/2/16(土) 午前 2:26kamakuraboy返
> kamakuraboyさん
ご丁寧な説明をやっていただきありがとうございました。
また、投稿時刻が真夜中になってしまっていることで申し訳ございません。
李承晩大統領の時代に、
> 日本漁船328隻を拿捕、日本人44人を死傷、3,929人を抑留。海上保安庁巡視船への銃撃等の事件15件、16隻が攻撃。拿捕された漁民は65年の条約締結まで解放されず、漁民を人質にし、日韓基本条約を韓国は自国有利にし、朝鮮戦争当時日本に押し寄せた不法上陸者である在日韓国人の居住資格(在日1世と2世まで)の許可を日本から引き出した。
といったようなことがあったなんって初めて知りました。
2019/2/16(土) 午後 6:37[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
さらに、
> 拘束された日本人漁民の釈放の代わりに日本の刑務所で常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている韓国人受刑者の釈放を要求し、(しかし当時の朴正熙大統領はこれらの人々の韓国への帰国は認めず)日本政府はその要求を受け入れて受刑者472人を釈放し永住許可を与えたとされる。
とのことに驚かされてしまいました。
> まぁ、ご自分で調べてみた方がよいと思いますよ。良かったらその結果を教えて下さい。
とのことですが、わたしの小さなキャパシティの限界を超えてしまっているお話でとてもとても無理な感じですね!
すみません!!
2019/2/16(土) 午後 6:38[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
日韓間の問題は大変複雑で、韓国びいきの方々には心を痛めるようなニュースも多い昨今ですね。
その上、竹島問題については実は日韓双方でその経緯などを知らない人々(無関心な方人々)も多いのが現実かもしれません。しかし、この問題は双方の国民が第三者的客観的な事実はやはり知った上で、冷静に解決していくべき課題だと思います。「武力による奪還」は憲法の制約上日本にとっては無理ですし、そんなことをすれば全面衝突になってしまう可能性もあるわけで、やはりもちろん避けるべきですから。
ただ、国民として、その当時何が起こったのか、どうして現在に至ったかくらいは知るべきことではないでしょうか。
2019/2/18(月) 午後 3:26kamakuraboy
好きな映画監督なのですが、ビクトル・エリセ監督は1940年にスペインのバスク地方で生まれました。バスク地方というのは、ピレネー山脈のフランスとスペインにまたがる地域で、そこに暮らす人々はバスク語を話し、自らをバスク人と呼ぶそうです。道路標識や看板も、バスク語、スペイン語、英語表記だとか。また、この地域の人々は日本人のように繊細で勤勉な気質で、芸術と美食の文化をもっているそうです。
エリセ監督はそういう地域で17年間ほど過ごし、その後は首都マドリードに移り住み、政治学と法学を学んだ後に、20歳のときにスペイン国立映画学校に入学し映画製作を学びました。1973年から1992年までの約20年間につくった長編作品はたったの3作品。その他オムニバス作品に参加しておられ、例えば東日本大震災を受けて河瀬直美の呼びかけにより制作された21人の映画監督による3分11秒の短編映画集にも参加。
長編作品
「ミツバチのささやき」El Espiritu de la colmena (1973)、
「エルスール」 El Sur (1982)
「マルメロの陽光」El Sol del membrillo (1992)

オムニバス
「挑戦」Los Desafios (1969)、
「10ミニッツオールダー人生のメビウス・ライフライン」Ten Minutes Older: The Trumpet / Lifeline (2002)
「3・11 A Sense of Home Films 」(2011)
「ポルトガル、ここに誕生す~ギマランイス歴史地区」(2012)
「ミツバチのささやき」(73年)
スペインのとある田舎の村に住んでいる姉妹が村の公民館のようなところで上映された映画「フランケンシュタイン」を観たところからお話しが始まります。
ヒロインは姉妹の内の妹でアナという名の少女。その役を演じた子役の名もアナ・トレントという名なので、恐らく、自分の名前の役を、現実なのか映画の撮影なのか、彼女は夢うつつのままに演じていたのかもしれません
アナ・トレントは後に大人になってからも女優となって演じている作品があり、興味があったので観てみましたが、子役の頃の彼女の宝石の原石のような輝きが失われていました。とにかく、この映画の最大の見どころは、この「アナ」の可愛らしさ、愛くるしさにつきます。そして、エリセ監督の映画の全てにいえるのですが、台詞が最小限度で、この映画も静かに静かに、日常の場面と、その中で起こる「夢うつつのような非日常」とが、少女「アナ」の目を通して描かれていました。
「マルメロの陽光」(92年)
スペインの画家アントニオ・ロペス・ガルシアが自宅の庭に実ったマルメロの実を描く姿を撮ったドキュメンタリー映画です。日本でも一部の映画館で上映され、その当時、待望の3作目だったこともあり、私も日比谷の映画館に観に行きました。台詞が殆んどない、静かな静かな、哲学的な作品です。
この映画は観終わったとき、「人間もマルメロの実と同様、実り、熟したあと、やがて土の上に落ち、朽ちてゆくのである」という、人間も自然界の一部にすぎないという哲学を台詞ではなく映像を通して語りかけてくる作品。
太陽の光を浴びて輝いているときすでに、陽光を浴びる昼間と夜との変化の中で、マルメロの実が刻々と翳りを帯びてゆく光景や、画家のガルシアがいろいろな角度から、ああでもないこうでもないと、陽光を受けて輝くマルメロをキャンバスの中に写しとろうとするも、納得のいく作品がなかなかでき上らない様子、そして日没後に疲れ果てて自分のベッドの上に横たわっている姿も描かれており、「土に落ち、朽ちていくマルメロの実」と「死んだように疲れて眠っている、老いた画家自身」がちょうど二重写しに描かれていて、「死」はまさに「実が地面に落ちて土に戻ること」なのだという感覚が極めて自然に心に入ってきます。そこには「死」を「誰にでも訪れる休息のようなもの」としてもとらえられているようにも思えました。
エリセ監督の長編第一作にして代表作である「ミツバチのささやき」(73年 スペイン)
El Espiritu de la colmena
https://youtu.be/aqvpMJNlqxE
コメント
バスク語は興味深いです。発音や構造や活用形態は、丸で知りませんが。恐らくは、外敵が侵入しずらい、孤立した地域で有ったのでしょうね。スイスの山間の僻地に古いロマン語が残っているという事を読みました。支那の奥地、雲南にも特有の言語がのこっているらしい。消滅しない内に採取し残す事が課題でしょうね。
2019/2/7(木) 午前 9:25[ 井頭山人(魯鈍斎) ]
> 井頭山人(魯鈍斎)さん
こんにちは。コメントをありがとうございます。各地域に古くからある言語というのは、文化人類学的に貴重な財産ですね。言語はその地域の独自の風土に根差しており、それを駆使する人々の精神にも影響を与えるもので、そこから生まれる文化や芸術にも大きく寄与しているようです。
2019/2/7(木) 午後 1:57kamakuraboy
「ミツバチのささやき」を探しにわたしのまちのレンタルDVD ショップに行きましたが、田舎町なものでありませんでした。
隣市の大きなツタヤに行きましたがやはりありません。
でも、係の方がパソコンで調べて取り寄せてくださって、1週間後に借りられることになりました。
楽しみですね。
2019/2/10(日) 午後 9:16[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
こんばんは。コメントをありがとうございます。古い作品なので探すのが大変だったようですね。私の大学時代の友人二人は、昔私の家でこの映画を一緒に観たとき、あまりに静かな静かな展開で途中から眠くなっていました。私は気にいっていた映画ですが、感性というものは人それぞれだと感じた次第。
2019/2/10(日) 午後 9:41kamakuraboy
レンタルDVDショップから「『ミツバチのささやき』が届いています」の電話があって借りてきて観てみました。
子どもの目を通してみた世界のお話なのでしょう。
アナにとっては、現実と空想の区別も明確ではなくて、どちらも実際のことって感じてしまっているのでしょう…?
どちらかというと、難しい内容でした。
2019/2/14(木) 午後 11:09[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
おはようございます。映画をご覧になったのですね。「どちらかというと、難しい内容」との感想、確かに台詞が少なく、エリセ監督の背景的なものを知らなければ、この映画が何を表しているのかということがつかみにくい作品だと思います。
映画の設定は1940年頃のスペイン内戦直後のフランコ体制下のとある村のお話し。そこでスペインの内戦とフランコ独裁体制などのスペインの現代史をみながら、映画の解釈を記事に書いてみました。
2019/2/15(金) 午前 6:59kamakuraboy
ブログの中に、
> この映画の最大の見どころは、この「アナ」の可愛らしさ、愛くるしさにつきます。とありますので、kamakuraboyさんは「可愛らしさ、愛くるらしさ」だけで満足なのかなって思いましたが…
でも、
タイトルに「フランコ独裁体制下のスペイン」とあったり、コメントの中に「スペインの内戦とフランコ独裁体制」とありますので、可愛らしさ、愛くるらしさだけのお話ではないと思われます。
以前、沖縄の基地問題のお話のときにどちらかというと沖縄の人たちではなくて政府の考え方を支持していたり、韓国との問題などの問題に関しても、武力行使や戦争を肯定する
わけではないとしつつも時と場合にはそれも致し方ないっていった感じでしたが…
同じようにこのブログのお話についても、一般ピープルサイドではなくて体制側を応援しているっていうことなのでしょうか…?
2019/2/15(金) 午後 1:39[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
映画の最大の魅力はやはりアナのあどけない可愛らしさにつきると思います。しかし幼いアナの目を通してこの映画の中でエリセ監督が描きたかったことは何だったのかということを、映画の時代背景やエリセ監督自身のバックボーン、個々の登場人物像に注目してみると更に面白いので書いてみました。よかったら読んでみてください。
2019/2/15(金) 午後 2:35kamakuraboy
weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
辺野古反対をやっている人々は一般の沖縄県民ではありません。プロ市民です。在日韓国人や中国人が圧倒的です。戦前から普通の外国籍の出稼ぎ労働者の人々に紛れて日本には多くの外国籍工作員が入り込んでいました。
韓国との問題で積極的な武力行使を支持する考えを示したことはないと思いますが。あくまでも日本人の生命財産を守るべきは米国頼みではなく日本国民自らで守るべきだという考えなのです。
韓国が嘗て竹島周辺で漁民を殺傷し拿捕し、人質にとって日韓条約交渉を有利に進めた経緯があるのです。泣いた赤鬼さんは失礼ながらこの経緯について全くご存知ないのですか。
2019/2/15(金) 午後 7:40kamakuraboy
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
日本人ならば、いくら相手がすぐ隣国であっても、そのような歴史的事実をありのままに知った上で、二度とそのような目にあわないように、日本国民の生命と財産をしっかり守るのが日本政府の果たすべき役割だという考えで、沖縄の米軍基地もだから危険な市街地にある普天間より、人口の少ない辺野古に移転すべきだと思っているまでです。
ご自身で、普天間周辺と辺野古をみて来られたら良いと思いますよ。それらがどのような立地で、現実の沖縄県民の人々のお考えがどのようなものなのかを。
私は無知で無責任な平和主義者ばかりでは国家は守れないと思っております。
2019/2/15(金) 午後 7:41kamakuraboy
> kamakuraboyさん
【「ミツバチのささやき」とフランコ独裁体制下のスペイン 2019/2/15(金) 午前 7:00】に目を通させていただきました。
kamakuraboyさんがお書きになりましたように、幼いアナの目を通してこの映画の中でエリセ監督が描きたかったことは
映画の時代背景
エリセ監督自身のバックボーン
個々の登場人物像
に注目して観ていかないと掴むことができないということで、やはり難しいなぁって思わせられてしまいました。
2019/2/15(金) 午後 10:24[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> 辺野古反対をやっている人々は一般の沖縄県民ではありません。プロ市民です。在日韓国人や中国人が圧倒的です。戦前から普通の外国籍の出稼ぎ労働者の人々に紛れて日本には多くの外国籍工作員が入り込んでいました。
→ このお話は初めて耳にしました。
> 韓国が嘗て竹島周辺で漁民を殺傷し拿捕し、人質にとって日韓条約交渉を有利に進めた経緯があるのです。泣いた赤鬼さんは失礼ながらこの経緯について全くご存知ないのですか。
→ そのようなことがあったっていうことはこれまで知りませんでした。また、なかなか信じられません。
> 漁民を殺傷し拿捕し、人質にとって
っていったことは、韓国の漁民などの一般人ではなくて、軍隊がということだったのでしょうか…?
2019/2/15(金) 午後 10:25[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
> そのような歴史的事実をありのままに知った上で、
> 二度とそのような目にあわないように、
→ 1つ前のコメントに書きましたが、にわかには信じることができない気持ちです。
> 無知で無責任な平和主義者ばかりでは国家は守れない
→ わたしのことを言っているのだと思いますが、日本人のたいていのみなさんはそのようなことをご存じなのでしょうか…?
2019/2/15(金) 午後 10:26[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
顔アイコン> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
拙ブログ記事の「朝鮮戦争」のところの最後に「補足」として竹島を不法占拠されるに至った経緯を書いてます。「李承晩ライン」「竹島」で調べれば同様の記載がありますが、
「サンフランシスコ講和条約(51年9月署名、52年4月開始)では、日本が放棄すべき領土に竹島が含まれていなかったにもかかわらず、52年1月に李承晩は一方的に「李承晩ライン」を設定。52年4月朝鮮戦争のさなか、韓国は武装警察を投入し、竹島を不法占拠。「李承晩ライン越境」を理由に日本漁船328隻を拿捕し、日本人44人を死傷(死亡者数は不明)、3,929人を抑留。韓国側からの海上保安庁巡視船への銃撃等の事件は15件におよび、16隻が攻撃された。拿捕された漁民は65年の条約締結まで解放されず、これらの漁民を人質にしたことで、日韓基本条約を韓国は自国有利にし、朝鮮戦争当時日本に押し寄せた不法上陸者である在日韓国人の居住資格(在日1世と2世まで)の許可を日本から引き出したのであった。」
2019/2/16(土) 午前 2:17kamakuraboy
> weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼)さん
「拘束された日本人漁民の釈放の代わりに日本の刑務所で常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている韓国人受刑者の釈放を要求し、(しかし当時の朴正熙大統領はこれらの人々の韓国への帰国は認めず)日本政府はその要求を受け入れて受刑者472人を釈放し永住許可を与えたとされる。」
まぁ、ご自分で調べてみた方がよいと思いますよ。当時の新聞が国会図書館などに残っているはずですから取り寄せられるはずですよ。それから日本以外の国が「竹島」をどう考えているのかなども。
良かったらその結果を教えて下さい。
2019/2/16(土) 午前 2:26kamakuraboy返
> kamakuraboyさん
ご丁寧な説明をやっていただきありがとうございました。
また、投稿時刻が真夜中になってしまっていることで申し訳ございません。
李承晩大統領の時代に、
> 日本漁船328隻を拿捕、日本人44人を死傷、3,929人を抑留。海上保安庁巡視船への銃撃等の事件15件、16隻が攻撃。拿捕された漁民は65年の条約締結まで解放されず、漁民を人質にし、日韓基本条約を韓国は自国有利にし、朝鮮戦争当時日本に押し寄せた不法上陸者である在日韓国人の居住資格(在日1世と2世まで)の許可を日本から引き出した。
といったようなことがあったなんって初めて知りました。
2019/2/16(土) 午後 6:37[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
さらに、
> 拘束された日本人漁民の釈放の代わりに日本の刑務所で常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている韓国人受刑者の釈放を要求し、(しかし当時の朴正熙大統領はこれらの人々の韓国への帰国は認めず)日本政府はその要求を受け入れて受刑者472人を釈放し永住許可を与えたとされる。
とのことに驚かされてしまいました。
> まぁ、ご自分で調べてみた方がよいと思いますよ。良かったらその結果を教えて下さい。
とのことですが、わたしの小さなキャパシティの限界を超えてしまっているお話でとてもとても無理な感じですね!
すみません!!
2019/2/16(土) 午後 6:38[ weeping_reddish_ogre(泣いた赤鬼) ]
日韓間の問題は大変複雑で、韓国びいきの方々には心を痛めるようなニュースも多い昨今ですね。
その上、竹島問題については実は日韓双方でその経緯などを知らない人々(無関心な方人々)も多いのが現実かもしれません。しかし、この問題は双方の国民が第三者的客観的な事実はやはり知った上で、冷静に解決していくべき課題だと思います。「武力による奪還」は憲法の制約上日本にとっては無理ですし、そんなことをすれば全面衝突になってしまう可能性もあるわけで、やはりもちろん避けるべきですから。
ただ、国民として、その当時何が起こったのか、どうして現在に至ったかくらいは知るべきことではないでしょうか。
2019/2/18(月) 午後 3:26kamakuraboy