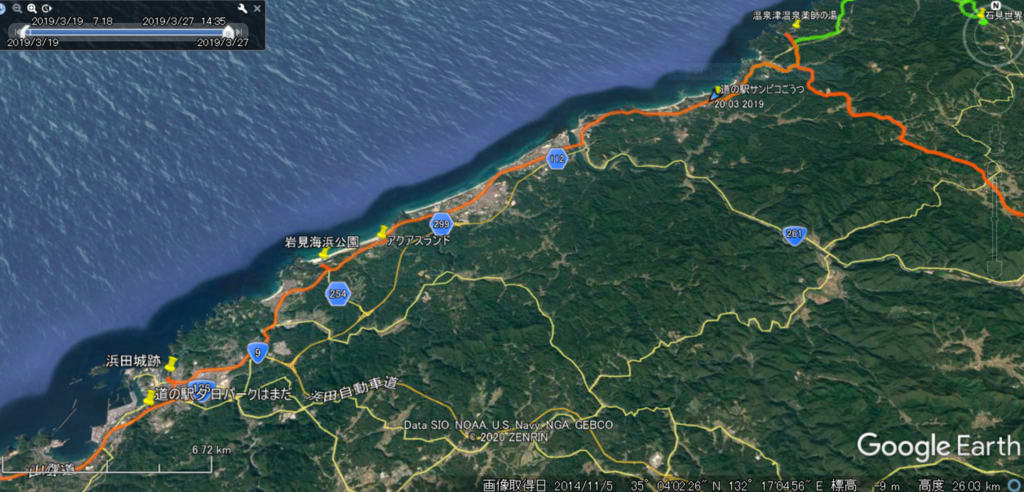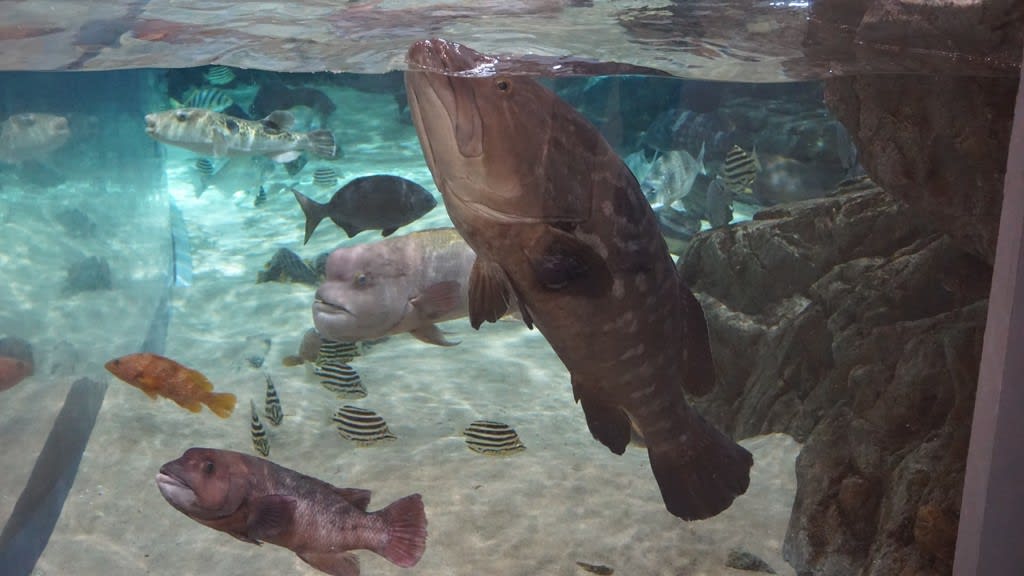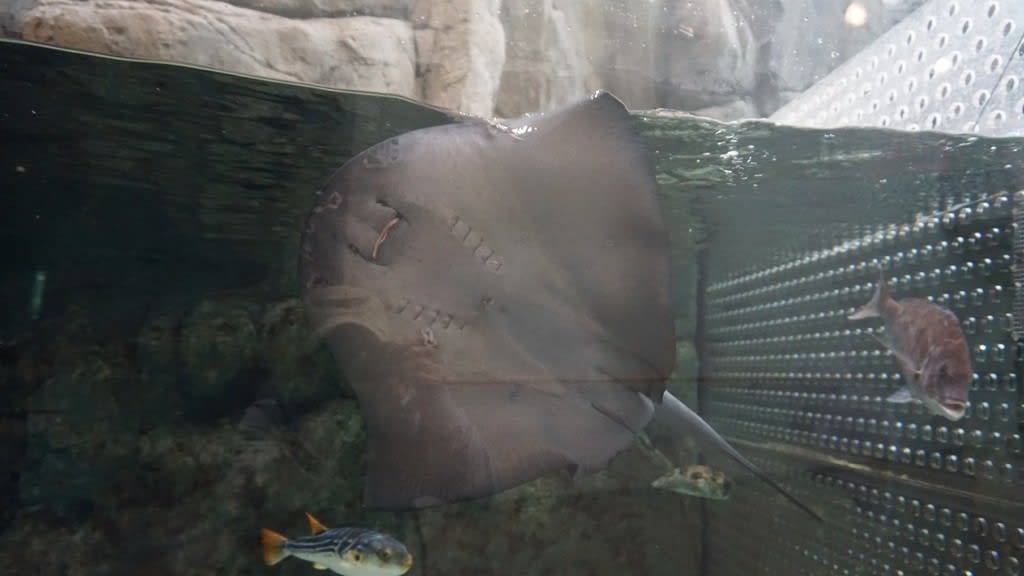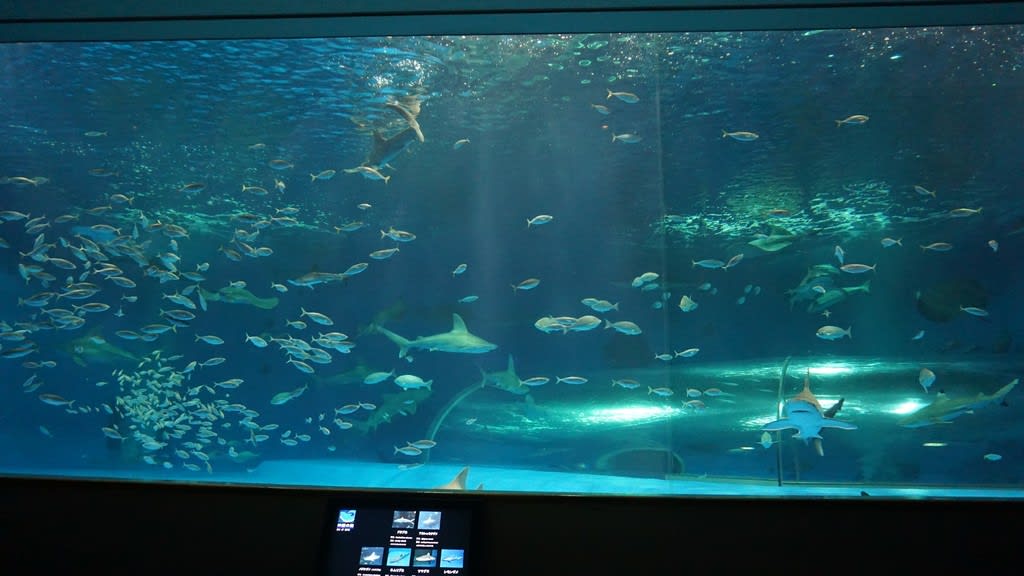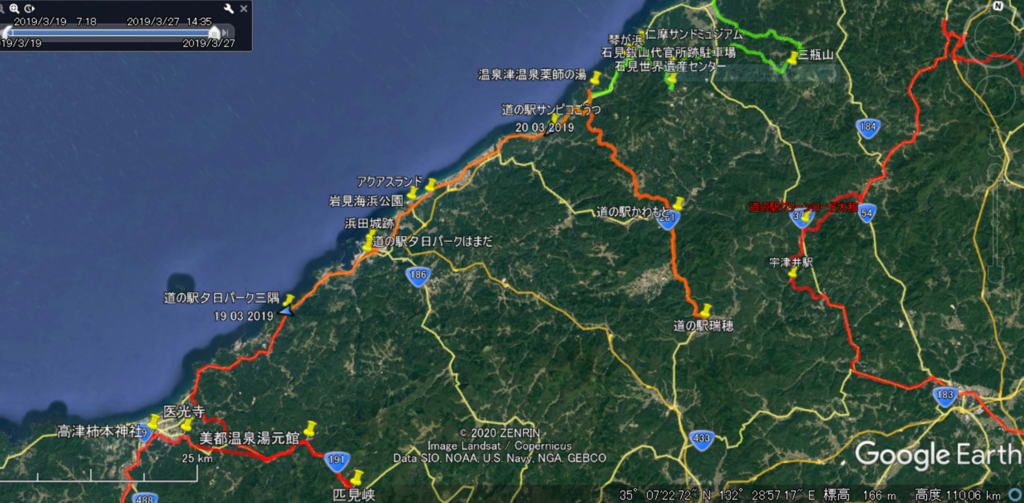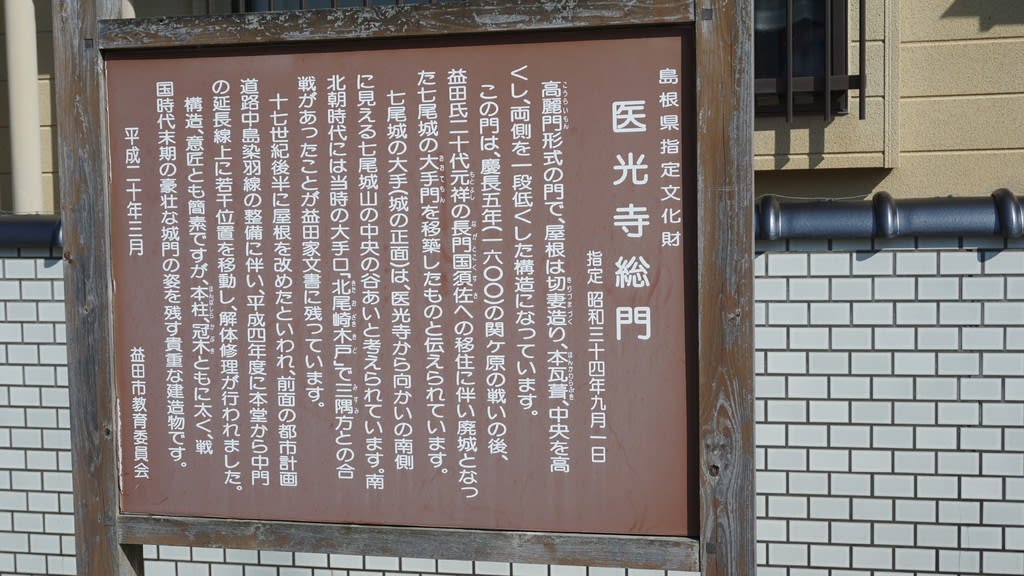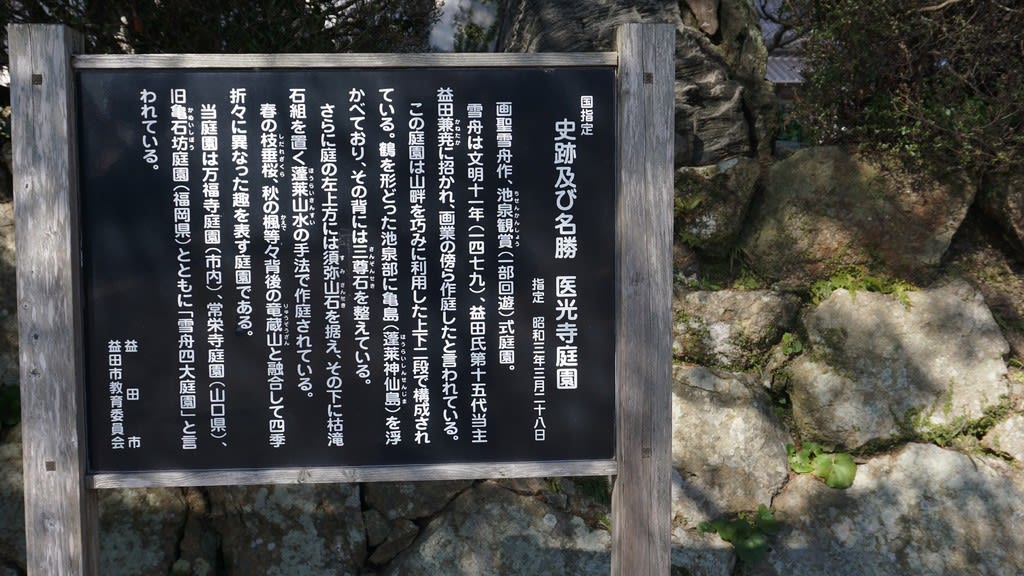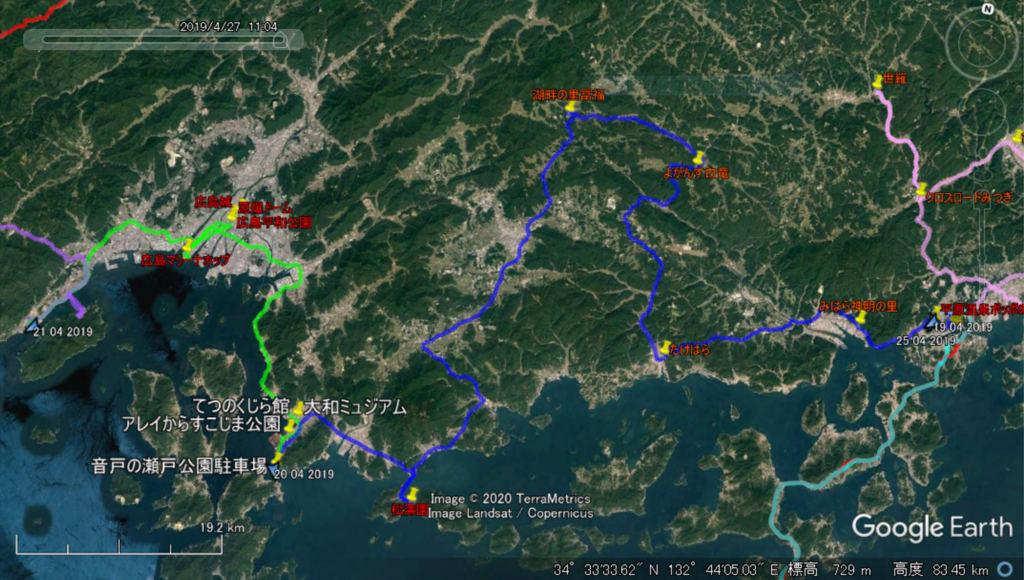島根県松江市八束町と鳥取県境港市渡町をつなぐ道路に
「江島大橋」と云う橋が架かってます
日本一の「PCラーメン橋」だそうです、おいしそうな橋ですね
残念ながら、みそ味でもとんこつ味でもない様です、鉄骨の橋の様です
PCと云うのはプレストレスト・コンクリート(舌を咬んじゃいそう)と云う橋梁の素材の事で
ラーメン橋と云うのは橋台と橋桁が一体化して繋がっている橋の事だそうです
ネットからの受け売りで、難しくてよくわからないいのさんです
よく見てくださいね、橋が坂になってます 「ベタ踏み坂」と云うそうです


橋の全長は1,446.2m有るそうです、最上部の高さは約45m有るそうです

こちらは島根県側です

視覚角度が45度あるそうです、視覚角度?見た目の勾配っていうことかな?
難しい事はよくわからないいのさんです


かなり急な勾配に見えるけど、体感的にはそんなに急なこう配とは感じなかったです

ここから見るとかなりの急坂ですね

実際高さは高いです

で、このベタ踏み坂写真を撮る場所と撮り方ですごい橋に見えるんです
次の写真です

凄いですよね、離れたところからカメラのズーム機能を使って撮ると
こんな具合に撮れるんだそうです
(ネットから拝借)

ところで、いよいよいのさんもキャンピングカーの旅に出かけるつもりです
勿論新型コロナウイルスの感染防止策を徹底し、三蜜にならない行動を心掛けてです
幾分の不安と、期待をいだきつつ準備に余念のないいのさんでした