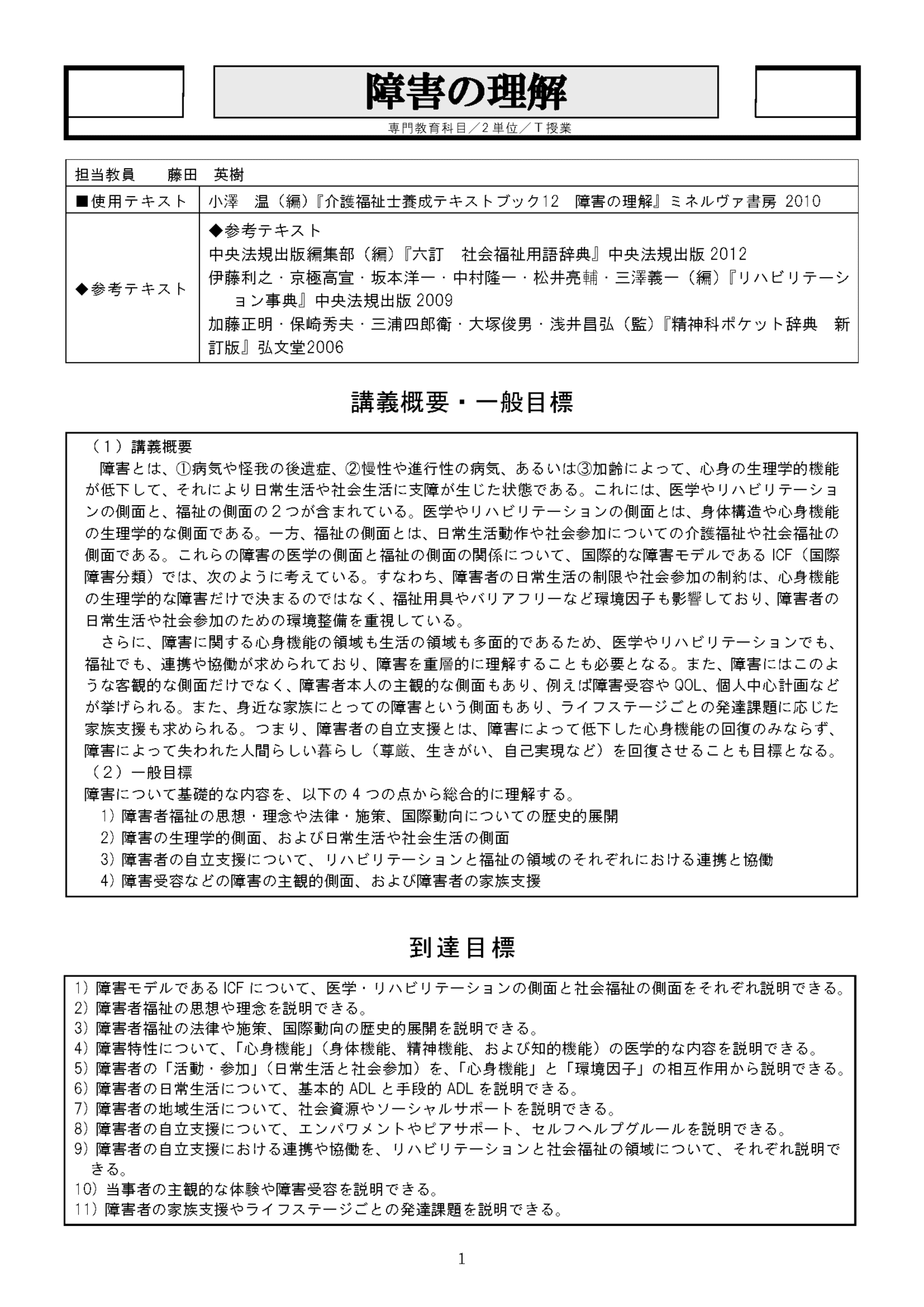■使用テキスト
小澤 温(編)『介護福祉士養成テキストブック12 障害の理解』ミネルヴァ書房 2010
◆参考テキスト
中央法規出版編集部(編)『六訂 社会福祉用語辞典』中央法規出版2012
伊藤利之・京極高宣・坂本洋一・中村隆一・松井亮輔・三澤義一(編)『リハビリテーション事典』中央法規出版2009
加藤正明・保崎秀夫・三浦四郎衛・大塚俊男・浅井昌弘(監)『精神科ポケット辞典 新訂版』弘文堂2006
◎講義概要・一般目標
(1)講義概要
障害とは、①病気や怪我の後遺症、②慢性や進行性の病気、あるいは③加齢によって、心身の生理学的機能が低下して、それにより日常生活や社会生活に支障が生じた状態である。これには、医学やリハビリテーションの側面と、福祉の側面の2つが含まれている。医学やリハビリテーションの側面とは、身体構造や心身機能の生理学的な側面である。一方、福祉の側面とは、日常生活動作や社会参加についての介護福祉や社会福祉の側面である。これらの障害の医学の側面と福祉の側面の関係について、国際的な障害モデルであるICF(国際障害分類)では、次のように考えている。すなわち、障害者の日常生活の制限や社会参加の制約は、心身機能の生理学的な障害だけで決まるのではなく、福祉用具やバリアフリーなど環境因子も影響しており、障害者の日常生活や社会参加のための環境整備を重視している。
さらに、障害に関する心身機能の領域も生活の領域も多面的であるため、医学やリハビリテーションでも、福祉でも、連携や協働が求められており、障害を重層的に理解することも必要となる。また、障害にはこのような客観的な側面だけでなく、障害者本人の主観的な側面もあり、例えば障害受容やQOL、個人中心計画などが挙げられる。また、身近な家族にとっての障害という側面もあり、ライフステージごとの発達課題に応じた家族支援も求められる。つまり、障害者の自立支援とは、障害によって低下した心身機能の回復のみならず、障害によって失われた人間らしい暮らし(尊厳、生きがい、自己実現など)を回復させることも目標となる。
(2)一般目標
障害について基礎的な内容を、以下の4つの点から総合的に理解する。
1) 障害者福祉の思想・理念や法律・施策、国際動向についての歴史的展開
2) 障害の生理学的側面、および日常生活や社会生活の側面
3) 障害者の自立支援について、リハビリテーションと福祉の領域のそれぞれにおける連携と協働
4) 障害受容などの障害の主観的側面、および障害者の家族支援
◎到達目標
1) 障害モデルであるICFについて、医学・リハビリテーションの側面と社会福祉の側面をそれぞれ説明できる。
2) 障害者福祉の思想や理念を説明できる。
3) 障害者福祉の法律や施策、国際動向の歴史的展開を説明できる。
4) 障害特性について、「心身機能」(身体機能、精神機能、および知的機能)の医学的な内容を説明できる。
5) 障害者の「活動・参加」(日常生活と社会参加)を、「心身機能」と「環境因子」の相互作用から説明できる。
6) 障害者の日常生活について、基本的ADLと手段的ADLを説明できる。
7) 障害者の地域生活について、社会資源やソーシャルサポートを説明できる。
8) 障害者の自立支援について、エンパワメントやピアサポート、セルフヘルプグルールを説明できる。
9) 障害者の自立支援における連携や協働を、リハビリテーションと社会福祉の領域について、それぞれ説明できる。
10) 当事者の主観的な体験や障害受容を説明できる。
11) 障害者の家族支援やライフステージごとの発達課題を説明できる。
◎評価方法
科目単位認定試験により評価する。
◎学習指導
第1章 障害の基礎的理解
一般目標:1)
到達目標:1, 2), 3)
(1) 障害モデル:
国際障害分類(ICIDH)も国際生活機能分類―国際障害分類改訂版―(ICF)も、障害を3つの層(レベル)に分け、障害を重層的に捉える点では共通している(6~7頁図1-2、1-3)。すなわち、①生理学的レベル、②日常生活レベル、および③社会参加レベルの3つである。しかし、ICIDHと比較してICFの特徴として3点挙げられる。すなわち、①環境因子を設定したこと(5頁上9行)、②機能障害を起点とした一方向の因果関係ではなく(6頁9行)、相互作用を想定したこと(6頁下6行)、および③活動や参加など中立的な用語を使用し、プラスの面から障害を捉えたこと(3頁下7行、4頁下13行、4行)である。例えば、ICFの「活動」は、「心身機能」と「環境因子」の相互作用の結果であり(6頁下6行)、環境改善の重要性が指摘される(4頁下6行)。逆に、廃用症候群のように、ICFの「活動」の低下が「心身機能」の低下を引き起こすこともある(59頁下15行)。
(2) ノーマライゼーション:
過去の時代には、障害者(知的障害者)はノーマルから逸脱していると捉えられていた(15頁下15行)。そのような時代に生まれたノーマライゼーションの考え方は、それまでの価値観を根本的に変えるものであった(16頁5行)。それは、ノーマルから逸脱した障害者をノーマルに近づけるのではなく、障害者もノーマルな生活(同じ生活圏の多くの人が営む暮らし)ができるような生活条件を提供することを提唱した(15頁9行、15頁下1行)。
(3) エンパワメント:
障害のマイナスの面に注目する病理欠陥アプローチ(89頁3行)やサービスを専門家主導で決定することは、障害者をパワレスな状態にする(18頁下9行)。パワレスな状態にある障害者の自己決定や問題解決力を高める援助がエンパワメントである(17頁下3行)。例えば、病理欠陥アプローチに対するものはストレングス・アプローチであり(18頁下17行、89頁4行)、障害者の持っている強みに注目する。一方、専門家主導の援助に対するものはピアサポートやセルフヘルプグループであり、(192頁4行)、当事者同士の助け合いによる問題解決を目指す(194頁下10行)。
(4) 自立と自己決定:
障害者の自立とは、日常生活動作の自立や経済的自立というよりも、むしろ人格的な自立のことであり(191頁14行)、選択と自己決定を行うことにより生活の主体となり(138頁下5行、191頁5行)、社会に参加することである(191頁7行)。障害者の自己決定は、「人権」「自立」「ソーシャルワーク」の3つの文脈があり(190頁7行)、ノーマライゼーションや自立生活運動(18頁1行、191頁7行)、エンパワメント、セルフアドボカシーの影響を受けている。同様に、リハビリテーションにおいて、障害によって低下した心身の機能を訓練により回復させることを治療的・代償的アプローチと呼び(17頁下14行、140頁下10行)、これはADLの自立を目標としている。それに対して、リハビリテーションを人間的復権であると考えることは、障害によって失われた人間らしく生きる権利(生きがい、役割、尊厳など)を回復させることである(17頁4行)。これはリハビリテーションの目的をADLからQOLへ転換したといえる(117頁12行、191頁11行)。
(5) 国際動向:
人権思想が形成された初期には「自由権」、すなわち個人の財産や幸福追求の自由を国家の介入から守る権利が中心であった(10頁1行)。それとは逆に、「社会権(生存権)」とは個人の生存権を国家が保障する責任があり、国家に社会保障を求める権利である。第二次大戦後、国連では人権を保障することが世界平和の礎になると考え、世界人権宣言が発せられた。これにより、世界共通の普遍的原理として「生存権保障」が定着した(10頁18行)。この生存権保障の1つが障害者福祉であるといえる。障害者については、1975年に採択された「障害者権利宣言」に沿って、各国に具体的な行動を要請した国際障害者年(1981年)では、主題として障害者の「完全参加と平等」が掲げられた(22頁12行)。近年では、法的拘束力のある障害者権利条約が締結され、我が国でも批准に向けて国内法の整備が進められている(11頁9行)。
(6) 障害者自立支援法:
戦傷者(傷痍軍人)の機能回復(16頁下15行、19頁下8行)や、貧困対策(20頁3行)、戦災孤児、浮浪児、貧困家庭児問題(20頁下6行)、私宅監置(12頁下3行)として行われていた戦前の障害者施策が、戦後になって、基本的人権を明記した日本国憲法が制定され、身体障害者福祉法が誕生したことにより、障害者福祉が貧困対策から独立した(20頁4行)。身体障害、知的障害、および精神障害の3障害の法律や制度は縦割りとなっていた(21頁下14行)。それらの3障害の法律や制度を一元化したのが障害者自立支援法である。障害者自立支援法では大きな改革が行われ、これまでの障害者福祉施策にない特徴として5つ挙げられる(25頁2行)。中でも、①市町村による支給決定手続きの明確化、②3障害を統合化した新しいサービス体系の2点は、これまでの障害者福祉の枠組みを変更した点で、大きな特徴である(142頁12行)。
第2章 障害の理解
一般目標:2)
到達目標:4)、5)
(1) 疾病と障害、日常生活:
障害の医学・リハビリテーションの側面、すなわちICFの「心身機能」とは、病気や怪我、加齢により、心身の生理学的機能が低下することである(4頁上6~8行)。その心身機能を活用して日常生活動作(ADL)を行うことがICFの「活動」にあたる。ICFの「活動」の制約」は、「心身機能」の低下と「環境因子」の相互作用として現れる。また、病気と障害は別物であるが、内部障害や精神障害(統合失調症など)、運動障害(筋ジストロフィーなど)などで、疾病が慢性あるいは進行性である場合は、病気であり障害でもある状態といえる(87頁上9行)。
(2) 生体機能と適応機能:
この「心身機能」は生体機能と適応機能の2つの側面に分けられる。人間の心身機能には人間は、生体機能を維持するために、空気中の酸素や食物の栄養を摂取し、それを体内で代謝して生体物質やエネルギーを生み出している(内部機能)。これは生命にかかわる機能といえる。一方、生活環境に適応するために、環境内の情報を得て(感覚機能)、その情報を大脳で処理し、判断や意思決定を行い(知能、高次脳機能、精神機能)、それに基づき行動する(運動機能)。さらに、言語を用いて他者とコミュニケーションを行い、集団生活や社会生活を営む(言語機能)。
(3) 内部障害:
吸気された空気中の酸素は、気管支を通り肺胞でガス交換により血液中に取り入れられる。代わりに血液中の二酸化炭素が肺胞に排出され、呼気として空気中に排出される(呼吸機能)。血液中に取り入れられた酸素は、心臓から全身に供給される(心機能)。また、食物を経口摂取して、それらを体内で消化吸収し、代謝して生体物質やエネルギーを作り出す。食物は、食物は胃で粥状にされ、十二指腸から小腸で消化・吸収される(小腸機能)。小腸で吸収された栄養は、肝門脈を通り肝臓に運ばれる。肝臓では、生体に必要となる物質の貯蔵、分解、合成、および解毒が行われる(肝機能)。血液中の老廃物は、腎臓の糸球体で濾過され(腎機能)、膀胱から排尿される(膀胱機能)。一方、小腸で消化・吸収された食物の残滓は、大腸、直腸を通り肛門から排便される(直腸機能)。免疫機能とは、生体が非自己の病原体などの侵入を防御することであるが、身体障害の免疫機能障害として判定されるのは、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)による後天性免疫不全症候群(AIDS)となる。それ以外で免疫機能の障害としては、例えばベーチェット病(29頁欄外)、全身性エリテマトーデス(116頁)、関節リウマチ(52頁)などの自己免疫疾患(膠原病)が挙げられる(116頁欄外)。
(4) 感覚機能:
生体機能には食物と酸素が必要であったが、適応機能には環境内の情報を得ることが必要である。環境内の物理的情報を電気信号に変換して脳に伝えることを感覚機能という。人間には5つの感覚(五感)があるといわれるが、障害の対象としては視覚と聴覚になる。これらは、光や音が感覚器官で電気信号に変換され、神経を通って大脳に伝えられる。視覚と聴覚は、その性質が一長一短であるといえる。つまり、視覚は情報を一覧でき、さらに確実な方法であるが、自分の背後や障害物の先は見えない。一方、聴覚は、全方位からの情報を得ることができ、視覚のような瞼がないため常に開いており、注意喚起力が強い(サイレン、アラームなど)。また、言語コミュニケーションも音声言語が文字言語よりも優位であり、音声言語は聴覚によって理解される。ただし、音声だけでは具体的なイメージがなく、聴き手の想像によって受け取り方が異なる(不確かなものとなる)。健常者は視覚と聴覚を両方活用し、それぞれの弱みを、それぞれの強みで互いに補っている。それに対して、視覚障害者や聴覚障害者は、障害のある感覚の強みを失い、さらに残された感覚の弱みの制約を受けることになる。
(5) 知的機能、高次脳機能:
感覚から受け取るのは、環境内にあるすべての情報ではない。現在の活動に必要な情報だけが選択される(注意機能)。その情報は、大脳で一時的あるいは長期的に記憶され(記憶機能)、情報処理され、認知的に理解し、判断される(知的機能)。その判断に基づき、プランニングや意思決定、モニタリング、プランの変更などを行う(遂行機能)。知的能力とは社会適応に必要な理解力や判断力であり、言語性と動作性に分けられる。知的能力の指標であるIQは知能検査の総合得点の偏差値として算出され、それは平均が100、標準偏差(SD)が15の正規分布に従う。知的障害の判定基準は、平均から2SDの位置であるIQ=70とされる。重症心身障害とは知的障害も身体障害も重度であり、大島分類(94頁)では、知的障害はIQ=35以下、身体障害は歩けない程度(身体障害の1~2級)が該当する。
高次脳機能障害とは、古典的には失語、失認、失行、半側空間無視のことであるが(120頁下7行)、福祉行政上の高次脳機能障害とは、①注意障害、②記憶障害、③遂行機能障害、④社会的行動障害の4つである(120頁上7行)。これらは、身体麻痺や失語症がない場合は見過ごされやすかった障害であり、それらを支援するために行政的な診断基準が作られた(121頁上17行、下7行)。このうち、遂行機能障害と社会的行動障害は前頭葉(前頭連合野)の損傷によるものである。前頭連合野の機能は、計画性や道徳性、感情の抑制など、人間らしい行動を司る最も高次の機能といえる。
(6) 運動機能:
知的機能や高次脳機能で行った環境情報の理解、判断、および意思決定をもとに、身体で行動を起こす(運動機能)。自分で意図して行う随意運動は、大脳の運動野からの運動指令が延髄の錐体で交差し、対側の皮質脊髄路(錘体路)を通り、筋に伝わることで実現する(49頁図2-1)。このような錘体路の働きを支えて円滑にしているのが錐体外路系である。例えば脳卒中後の片麻痺(55頁)や脊髄損傷(53頁)、ALS(55頁、119ページ)などは錐体路の障害であり、パーキンソン病(59頁)や脊髄小脳変性症(58頁)などは錐体外路の障害である。脳に原因のある脳原性の運動障害は、知的障害や失語症、高次脳機能障害を伴うことがあり、例えば脳性麻痺や脳卒中が挙げられる。肢体不自由とは、上肢、下肢、体幹の機能に分けた場合である。地球には重力が働いており、人間は直立二足歩行をすることにより、上肢が自由に使えるようになり、さらに手指で細かい作業も行うことができる。一方、下肢は歩行などの移動を、体幹は抗重力に身体を垂直に立て、寝返りを打つなどする。
(7) 言語機能:
言語機能は、大脳の言語中枢(高次脳機能)と発声発語(運動機能)の2つの過程がある。言語中枢には、側頭葉のウェルニッケ野(言語理解)と前頭葉のブローカ野(言語表出)がある。一方、発声発語運動には、音声と構音がある。音声とは声帯を振動させることであり、構音とは口腔や鼻腔で共鳴させて言語音を作ることである。話し手の発声発語運動で産生された言語音(空気振動)は、空気中を伝わり、聴き手の聴覚に届いて理解される。また、話し手は、自分の声を自分の耳でも聞いており(聴覚フィードバック)、これにより発声発語運動がコントロールされている。このような高次脳機能や運動機能としての言語機能のほかに、言語発達があり、これは知的障害や自閉症などの発達障害(100頁1行)で問題となる(109頁)。発達障害の言語機能としては、①コミュニケーション、②行動コントロール(自分に言い聞かせる)、③思考(言葉で考える)の3つが挙げられる。先述のように重症心身障害とは、狭義には知的障害も運動障害も重度の場合であるが、広義には、運動障害がなく知的障害が最重度(IQ=20以下)で、且つ強度行動障害を伴う場合も含まれる(94頁下13行)。このような場合、自分の要求を言語によって表出し、言葉で行動をコントロールできないため、2次的に行動障害が生じやすい。
(8) 精神機能:
大脳の情報処理については、認知的な側面(認知機能)だけではなく、情意的な側面もある(気分・感情と動機づけ)。例えば、①気分や感情といった快-不快や好-悪についての評価的な機能や、②覚醒レベルや自我機能といった主観的な意識機能、③気質やパーソナリティ、個性といった思考や行動パターンの個人差も、④道徳性や人格も、大脳の情報処理に影響している(精神機能)。気質とは生まれつきの反応傾向の個人差であり、パーソナリティとは発達の過程で経験により形成された思考や行動パターンの個人差である。パーソナリティの基礎は児童期に形成され、思春期・青年期に確立される。確立されたパーソナリティは変化しにくいため、不適応なパーソナリティは持続的な不適応を生じさせ、これがパーソナリティ障害である。どのような精神障害でも、認知機能の側面と精神機能の側面があり、例えば統合失調症の認知機能障害、認知症の周辺症状(BPSD)、高次脳機能障害の社会的行動障害(感情コントロールや道徳性などの問題)、知的障害や自閉症の強度行動障害(二次的な精神障害)(109頁下5行)などが挙げられる。
(9) 各障害の生活ニーズ:
各障害の特徴的な生活ニーズを挙げると、以下のようになる;視覚障害(安全や確認に時間を要し不正確、移動)、聴覚障害(環境音、警報、音声言語によるコミュニケーション)、言語障害(言語理解、言語コミュニケーション)、運動障害(日常生活動作、移動)、内部障害(医療依存度が高い)、精神障害(対人関係、社会生活、気分・感情)、高次脳機能障害(手段的な日常生活動作、病識の欠如)、知的障害(抽象的な理解、社会的な判断)、発達障害(認知特性の偏り、部分的障害、周囲の誤解)。
第3章 自立支援のための連携と協働
第4章 障害の及ぼす心理的影響
第5章 当事者および家族への支援
一般目標:3)
到達目標:6), 7), 8), 9), 10), 11)
(1) 地域生活支援:
障害者福祉では、歴史的に見て障害者は保護収容の対象から、権利の主体として、地域福祉が推進されてきた(23頁)。第2章で学習したように、障害とは病気や怪我、加齢が原因となって生じるものである。しかし、ICFでは、障害者の日常生活や社会生活は、心身機能の低下という生理学的な側面だけではなく、環境因子も影響するとしている。またICFでは、障害の対義語は「生活機能」とされている(3頁欄外、25頁参考文献)。つまり、障害者の自立支援とは生活にかかわるものであり、環境整備や本人のエンパワメントによる生活支援(115頁10行)であるといえる。障害者福祉における生活支援とは、生活ニーズの7つの側面(日常生活動作[ADL]、介護負担、家事、経済、家族関係、社会交流、ストレス)に分けられる(138頁1行)。自立生活支援でとくに重要となるのは、自立生活への動機づけの支援、自立生活の基盤としての権利擁護の2つであり、具体的な実践としては、自立生活プログラム、ピアカウンセリングの2つとなる(139頁4行)。自立生活プログラムとは、障害者のエンパワメント(問題対処の力の獲得)の向上を目的としたプログラムといえる(139頁10行)。地域生活では、ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンの理念に基づき、自己決定に基づき主体的に暮らすという側面の他にも、権利擁護やリスクを避けるという側面や(203行4行)、医療的ケアの確保の課題もある。
(2) チームアプローチ:
医療分野では感染症を中心とした急性疾患から、日々の生活習慣から生じる生活習慣病を中心とした慢性疾患へと対応の重点が移行し(140頁11行)、チームアプローチの取り組みが先駆的になされた。医療分野で最もチームアプローチを強調しているのがリハビリテーションである(同19行)。リハビリテーションでは、障害の心身機能の範囲の広さへの対応と、病気や怪我からの回復の時間的対応の2つがある(143頁)。心身機能の範囲の広さについて、リハビリテーションには様々な専門職種がある。一方、時間的対応について、リハビリテーションは急性期、回復期、維持期の順に進んでいく(同12行)。
(3) 日常生活動作(ADL):
ADLとは起居動作や身辺のこと、さらに地域で一人暮らしをするためのスキルであり、基本的ADLと手段的ADLの2つに分けられる(130頁欄外)。基本的ADLとは、食事、排泄、更衣、入浴、整容、移乗・移動の6つが挙げられる。一方、手段的ADLとは、掃除、洗濯、調理、買い物、交通機関の利用、金銭管理の6つが挙げられる。ADLが自立していないと介護が必要となる。例えば、運動障害ではどちらのADLにもニーズがあり、高次脳機能障害では基本的ADLは自立しているが手段的ADLに障害があるといえる(124頁下7行)。
(4) 社会資源、ソーシャルサポート:
社会資源とは、社会的ニーズを充足する様々な物質や人材の総称で、社会福祉では社会福祉施設、備品、サービス、資金、制度、情報、知識・技能、人材などにわたる(148頁下11行)。社会資源はフォーマルとインフォーマルに分けられる(同下8行)。フォーマルな社会刺激は行政機関など制度化されているものである。一方、インフォーマルな社会資源の1つに、ソーシャルサポートが挙げられる。ソーシャルサポートとは支援的な人間関係のことであり、ストレス対処や適応にとって重要な役割を果たす(150頁6行)。ソーシャルサポートには、手段的と情緒的の2種類ある(150頁欄外)。地域の在宅障害者のQOLには、家族以外の人間関係の形成、すなわちソーシャルサポートが大きな役割を果たしている(150頁上12行)。障害者のもつ複数のニーズと社会資源を結びつけることがケアマネジメントであり(142頁欄外)、障害者自立支援法から導入された(142頁14行)。障害者のケアマネジメントでは、従来の援助の必要性を中心としたニーズ把握から、当事者の希望、願望に沿ったニーズ把握への視点を変化させており(193頁上5行)、それは個人中心計画と呼ばれる(193頁欄外)。
(5) 障害受容:
障害には客観的な側面と主観的な側面がある。後者の主観的な側面として、①障害受容、②個人中心計画におけるニーズ、③QOL(生活の質・人生の質)などが挙げられる。障害受容について、モリス・グレイソンは、ボディーイメージの再建を提唱した。タマラ・デンボーとベアトリーチェ・ライトは、4つの価値転換を提唱した。すなわち、①価値の範囲の拡大、②比較価値から資産価値への転換、③身体の価値を従属的なものにする、および④障害の与える影響の制限の4つである(180頁下4行)。ナンシー・コーンらのステージ理論では、受傷の心理的ショックからの立ち直りは段階的に進み、障害の受容には「悲哀の仕事」が必要であるとした(180頁5行)。ただし、すべてが障害受容の問題ではない。例えば、①脳卒中後のうつ(171頁11行)、②自殺未遂による受傷(185頁下9行)、③左片麻痺および半側空間無視と合併することの多い病態失認(168頁下13行)、④高次脳機能障害の約半数に認められる病識の欠如(125頁下11行)が挙げられる。
(6) 家族支援:
障害には、本人だけでなく身近な家族にとっての障害という側面もある。ライフステージとは、乳幼児期、学童期、思春期、成人期、高齢期の5つの時期のことであり、それぞれの時期に取り組まれるべき発達課題がある(199頁)。障害に気づく時期や障害の特性によってライフステージのあり方は異なる(202頁下4行)。また、ほとんどの障害児が学齢期に放課後は家族と過ごすことが多く、(200頁下6行)、在宅者の8割程度が家族と同居しているなど(195頁下8行)、これらの発達課題と直面する経験が希薄なため、個々の人生のライフコースを築きにくい(199頁10行)。成人期には介護者である家族の高齢化や親亡き後の問題がある(202頁4行)。生涯を通じて関わる支援機関が存在しないことも課題とされる(203頁1行)。また在宅者の場合、家族が主要な介護者として位置づけられており、在宅介護の介護者のうつは施設介護に比べて高率で発生する(177頁12行)。それは、量的負担が大きいことと、家族への同一化(自分のことように思うこと)といった質的側面があり、それら2つが重なって大きな負担となる(同19行)。それに対しては、家族に対するレスパイトサービスやショートステイの活用が挙げられる(197頁)。
以下余白
小澤 温(編)『介護福祉士養成テキストブック12 障害の理解』ミネルヴァ書房 2010
◆参考テキスト
中央法規出版編集部(編)『六訂 社会福祉用語辞典』中央法規出版2012
伊藤利之・京極高宣・坂本洋一・中村隆一・松井亮輔・三澤義一(編)『リハビリテーション事典』中央法規出版2009
加藤正明・保崎秀夫・三浦四郎衛・大塚俊男・浅井昌弘(監)『精神科ポケット辞典 新訂版』弘文堂2006
◎講義概要・一般目標
(1)講義概要
障害とは、①病気や怪我の後遺症、②慢性や進行性の病気、あるいは③加齢によって、心身の生理学的機能が低下して、それにより日常生活や社会生活に支障が生じた状態である。これには、医学やリハビリテーションの側面と、福祉の側面の2つが含まれている。医学やリハビリテーションの側面とは、身体構造や心身機能の生理学的な側面である。一方、福祉の側面とは、日常生活動作や社会参加についての介護福祉や社会福祉の側面である。これらの障害の医学の側面と福祉の側面の関係について、国際的な障害モデルであるICF(国際障害分類)では、次のように考えている。すなわち、障害者の日常生活の制限や社会参加の制約は、心身機能の生理学的な障害だけで決まるのではなく、福祉用具やバリアフリーなど環境因子も影響しており、障害者の日常生活や社会参加のための環境整備を重視している。
さらに、障害に関する心身機能の領域も生活の領域も多面的であるため、医学やリハビリテーションでも、福祉でも、連携や協働が求められており、障害を重層的に理解することも必要となる。また、障害にはこのような客観的な側面だけでなく、障害者本人の主観的な側面もあり、例えば障害受容やQOL、個人中心計画などが挙げられる。また、身近な家族にとっての障害という側面もあり、ライフステージごとの発達課題に応じた家族支援も求められる。つまり、障害者の自立支援とは、障害によって低下した心身機能の回復のみならず、障害によって失われた人間らしい暮らし(尊厳、生きがい、自己実現など)を回復させることも目標となる。
(2)一般目標
障害について基礎的な内容を、以下の4つの点から総合的に理解する。
1) 障害者福祉の思想・理念や法律・施策、国際動向についての歴史的展開
2) 障害の生理学的側面、および日常生活や社会生活の側面
3) 障害者の自立支援について、リハビリテーションと福祉の領域のそれぞれにおける連携と協働
4) 障害受容などの障害の主観的側面、および障害者の家族支援
◎到達目標
1) 障害モデルであるICFについて、医学・リハビリテーションの側面と社会福祉の側面をそれぞれ説明できる。
2) 障害者福祉の思想や理念を説明できる。
3) 障害者福祉の法律や施策、国際動向の歴史的展開を説明できる。
4) 障害特性について、「心身機能」(身体機能、精神機能、および知的機能)の医学的な内容を説明できる。
5) 障害者の「活動・参加」(日常生活と社会参加)を、「心身機能」と「環境因子」の相互作用から説明できる。
6) 障害者の日常生活について、基本的ADLと手段的ADLを説明できる。
7) 障害者の地域生活について、社会資源やソーシャルサポートを説明できる。
8) 障害者の自立支援について、エンパワメントやピアサポート、セルフヘルプグルールを説明できる。
9) 障害者の自立支援における連携や協働を、リハビリテーションと社会福祉の領域について、それぞれ説明できる。
10) 当事者の主観的な体験や障害受容を説明できる。
11) 障害者の家族支援やライフステージごとの発達課題を説明できる。
◎評価方法
科目単位認定試験により評価する。
◎学習指導
第1章 障害の基礎的理解
一般目標:1)
到達目標:1, 2), 3)
(1) 障害モデル:
国際障害分類(ICIDH)も国際生活機能分類―国際障害分類改訂版―(ICF)も、障害を3つの層(レベル)に分け、障害を重層的に捉える点では共通している(6~7頁図1-2、1-3)。すなわち、①生理学的レベル、②日常生活レベル、および③社会参加レベルの3つである。しかし、ICIDHと比較してICFの特徴として3点挙げられる。すなわち、①環境因子を設定したこと(5頁上9行)、②機能障害を起点とした一方向の因果関係ではなく(6頁9行)、相互作用を想定したこと(6頁下6行)、および③活動や参加など中立的な用語を使用し、プラスの面から障害を捉えたこと(3頁下7行、4頁下13行、4行)である。例えば、ICFの「活動」は、「心身機能」と「環境因子」の相互作用の結果であり(6頁下6行)、環境改善の重要性が指摘される(4頁下6行)。逆に、廃用症候群のように、ICFの「活動」の低下が「心身機能」の低下を引き起こすこともある(59頁下15行)。
(2) ノーマライゼーション:
過去の時代には、障害者(知的障害者)はノーマルから逸脱していると捉えられていた(15頁下15行)。そのような時代に生まれたノーマライゼーションの考え方は、それまでの価値観を根本的に変えるものであった(16頁5行)。それは、ノーマルから逸脱した障害者をノーマルに近づけるのではなく、障害者もノーマルな生活(同じ生活圏の多くの人が営む暮らし)ができるような生活条件を提供することを提唱した(15頁9行、15頁下1行)。
(3) エンパワメント:
障害のマイナスの面に注目する病理欠陥アプローチ(89頁3行)やサービスを専門家主導で決定することは、障害者をパワレスな状態にする(18頁下9行)。パワレスな状態にある障害者の自己決定や問題解決力を高める援助がエンパワメントである(17頁下3行)。例えば、病理欠陥アプローチに対するものはストレングス・アプローチであり(18頁下17行、89頁4行)、障害者の持っている強みに注目する。一方、専門家主導の援助に対するものはピアサポートやセルフヘルプグループであり、(192頁4行)、当事者同士の助け合いによる問題解決を目指す(194頁下10行)。
(4) 自立と自己決定:
障害者の自立とは、日常生活動作の自立や経済的自立というよりも、むしろ人格的な自立のことであり(191頁14行)、選択と自己決定を行うことにより生活の主体となり(138頁下5行、191頁5行)、社会に参加することである(191頁7行)。障害者の自己決定は、「人権」「自立」「ソーシャルワーク」の3つの文脈があり(190頁7行)、ノーマライゼーションや自立生活運動(18頁1行、191頁7行)、エンパワメント、セルフアドボカシーの影響を受けている。同様に、リハビリテーションにおいて、障害によって低下した心身の機能を訓練により回復させることを治療的・代償的アプローチと呼び(17頁下14行、140頁下10行)、これはADLの自立を目標としている。それに対して、リハビリテーションを人間的復権であると考えることは、障害によって失われた人間らしく生きる権利(生きがい、役割、尊厳など)を回復させることである(17頁4行)。これはリハビリテーションの目的をADLからQOLへ転換したといえる(117頁12行、191頁11行)。
(5) 国際動向:
人権思想が形成された初期には「自由権」、すなわち個人の財産や幸福追求の自由を国家の介入から守る権利が中心であった(10頁1行)。それとは逆に、「社会権(生存権)」とは個人の生存権を国家が保障する責任があり、国家に社会保障を求める権利である。第二次大戦後、国連では人権を保障することが世界平和の礎になると考え、世界人権宣言が発せられた。これにより、世界共通の普遍的原理として「生存権保障」が定着した(10頁18行)。この生存権保障の1つが障害者福祉であるといえる。障害者については、1975年に採択された「障害者権利宣言」に沿って、各国に具体的な行動を要請した国際障害者年(1981年)では、主題として障害者の「完全参加と平等」が掲げられた(22頁12行)。近年では、法的拘束力のある障害者権利条約が締結され、我が国でも批准に向けて国内法の整備が進められている(11頁9行)。
(6) 障害者自立支援法:
戦傷者(傷痍軍人)の機能回復(16頁下15行、19頁下8行)や、貧困対策(20頁3行)、戦災孤児、浮浪児、貧困家庭児問題(20頁下6行)、私宅監置(12頁下3行)として行われていた戦前の障害者施策が、戦後になって、基本的人権を明記した日本国憲法が制定され、身体障害者福祉法が誕生したことにより、障害者福祉が貧困対策から独立した(20頁4行)。身体障害、知的障害、および精神障害の3障害の法律や制度は縦割りとなっていた(21頁下14行)。それらの3障害の法律や制度を一元化したのが障害者自立支援法である。障害者自立支援法では大きな改革が行われ、これまでの障害者福祉施策にない特徴として5つ挙げられる(25頁2行)。中でも、①市町村による支給決定手続きの明確化、②3障害を統合化した新しいサービス体系の2点は、これまでの障害者福祉の枠組みを変更した点で、大きな特徴である(142頁12行)。
第2章 障害の理解
一般目標:2)
到達目標:4)、5)
(1) 疾病と障害、日常生活:
障害の医学・リハビリテーションの側面、すなわちICFの「心身機能」とは、病気や怪我、加齢により、心身の生理学的機能が低下することである(4頁上6~8行)。その心身機能を活用して日常生活動作(ADL)を行うことがICFの「活動」にあたる。ICFの「活動」の制約」は、「心身機能」の低下と「環境因子」の相互作用として現れる。また、病気と障害は別物であるが、内部障害や精神障害(統合失調症など)、運動障害(筋ジストロフィーなど)などで、疾病が慢性あるいは進行性である場合は、病気であり障害でもある状態といえる(87頁上9行)。
(2) 生体機能と適応機能:
この「心身機能」は生体機能と適応機能の2つの側面に分けられる。人間の心身機能には人間は、生体機能を維持するために、空気中の酸素や食物の栄養を摂取し、それを体内で代謝して生体物質やエネルギーを生み出している(内部機能)。これは生命にかかわる機能といえる。一方、生活環境に適応するために、環境内の情報を得て(感覚機能)、その情報を大脳で処理し、判断や意思決定を行い(知能、高次脳機能、精神機能)、それに基づき行動する(運動機能)。さらに、言語を用いて他者とコミュニケーションを行い、集団生活や社会生活を営む(言語機能)。
(3) 内部障害:
吸気された空気中の酸素は、気管支を通り肺胞でガス交換により血液中に取り入れられる。代わりに血液中の二酸化炭素が肺胞に排出され、呼気として空気中に排出される(呼吸機能)。血液中に取り入れられた酸素は、心臓から全身に供給される(心機能)。また、食物を経口摂取して、それらを体内で消化吸収し、代謝して生体物質やエネルギーを作り出す。食物は、食物は胃で粥状にされ、十二指腸から小腸で消化・吸収される(小腸機能)。小腸で吸収された栄養は、肝門脈を通り肝臓に運ばれる。肝臓では、生体に必要となる物質の貯蔵、分解、合成、および解毒が行われる(肝機能)。血液中の老廃物は、腎臓の糸球体で濾過され(腎機能)、膀胱から排尿される(膀胱機能)。一方、小腸で消化・吸収された食物の残滓は、大腸、直腸を通り肛門から排便される(直腸機能)。免疫機能とは、生体が非自己の病原体などの侵入を防御することであるが、身体障害の免疫機能障害として判定されるのは、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)による後天性免疫不全症候群(AIDS)となる。それ以外で免疫機能の障害としては、例えばベーチェット病(29頁欄外)、全身性エリテマトーデス(116頁)、関節リウマチ(52頁)などの自己免疫疾患(膠原病)が挙げられる(116頁欄外)。
(4) 感覚機能:
生体機能には食物と酸素が必要であったが、適応機能には環境内の情報を得ることが必要である。環境内の物理的情報を電気信号に変換して脳に伝えることを感覚機能という。人間には5つの感覚(五感)があるといわれるが、障害の対象としては視覚と聴覚になる。これらは、光や音が感覚器官で電気信号に変換され、神経を通って大脳に伝えられる。視覚と聴覚は、その性質が一長一短であるといえる。つまり、視覚は情報を一覧でき、さらに確実な方法であるが、自分の背後や障害物の先は見えない。一方、聴覚は、全方位からの情報を得ることができ、視覚のような瞼がないため常に開いており、注意喚起力が強い(サイレン、アラームなど)。また、言語コミュニケーションも音声言語が文字言語よりも優位であり、音声言語は聴覚によって理解される。ただし、音声だけでは具体的なイメージがなく、聴き手の想像によって受け取り方が異なる(不確かなものとなる)。健常者は視覚と聴覚を両方活用し、それぞれの弱みを、それぞれの強みで互いに補っている。それに対して、視覚障害者や聴覚障害者は、障害のある感覚の強みを失い、さらに残された感覚の弱みの制約を受けることになる。
(5) 知的機能、高次脳機能:
感覚から受け取るのは、環境内にあるすべての情報ではない。現在の活動に必要な情報だけが選択される(注意機能)。その情報は、大脳で一時的あるいは長期的に記憶され(記憶機能)、情報処理され、認知的に理解し、判断される(知的機能)。その判断に基づき、プランニングや意思決定、モニタリング、プランの変更などを行う(遂行機能)。知的能力とは社会適応に必要な理解力や判断力であり、言語性と動作性に分けられる。知的能力の指標であるIQは知能検査の総合得点の偏差値として算出され、それは平均が100、標準偏差(SD)が15の正規分布に従う。知的障害の判定基準は、平均から2SDの位置であるIQ=70とされる。重症心身障害とは知的障害も身体障害も重度であり、大島分類(94頁)では、知的障害はIQ=35以下、身体障害は歩けない程度(身体障害の1~2級)が該当する。
高次脳機能障害とは、古典的には失語、失認、失行、半側空間無視のことであるが(120頁下7行)、福祉行政上の高次脳機能障害とは、①注意障害、②記憶障害、③遂行機能障害、④社会的行動障害の4つである(120頁上7行)。これらは、身体麻痺や失語症がない場合は見過ごされやすかった障害であり、それらを支援するために行政的な診断基準が作られた(121頁上17行、下7行)。このうち、遂行機能障害と社会的行動障害は前頭葉(前頭連合野)の損傷によるものである。前頭連合野の機能は、計画性や道徳性、感情の抑制など、人間らしい行動を司る最も高次の機能といえる。
(6) 運動機能:
知的機能や高次脳機能で行った環境情報の理解、判断、および意思決定をもとに、身体で行動を起こす(運動機能)。自分で意図して行う随意運動は、大脳の運動野からの運動指令が延髄の錐体で交差し、対側の皮質脊髄路(錘体路)を通り、筋に伝わることで実現する(49頁図2-1)。このような錘体路の働きを支えて円滑にしているのが錐体外路系である。例えば脳卒中後の片麻痺(55頁)や脊髄損傷(53頁)、ALS(55頁、119ページ)などは錐体路の障害であり、パーキンソン病(59頁)や脊髄小脳変性症(58頁)などは錐体外路の障害である。脳に原因のある脳原性の運動障害は、知的障害や失語症、高次脳機能障害を伴うことがあり、例えば脳性麻痺や脳卒中が挙げられる。肢体不自由とは、上肢、下肢、体幹の機能に分けた場合である。地球には重力が働いており、人間は直立二足歩行をすることにより、上肢が自由に使えるようになり、さらに手指で細かい作業も行うことができる。一方、下肢は歩行などの移動を、体幹は抗重力に身体を垂直に立て、寝返りを打つなどする。
(7) 言語機能:
言語機能は、大脳の言語中枢(高次脳機能)と発声発語(運動機能)の2つの過程がある。言語中枢には、側頭葉のウェルニッケ野(言語理解)と前頭葉のブローカ野(言語表出)がある。一方、発声発語運動には、音声と構音がある。音声とは声帯を振動させることであり、構音とは口腔や鼻腔で共鳴させて言語音を作ることである。話し手の発声発語運動で産生された言語音(空気振動)は、空気中を伝わり、聴き手の聴覚に届いて理解される。また、話し手は、自分の声を自分の耳でも聞いており(聴覚フィードバック)、これにより発声発語運動がコントロールされている。このような高次脳機能や運動機能としての言語機能のほかに、言語発達があり、これは知的障害や自閉症などの発達障害(100頁1行)で問題となる(109頁)。発達障害の言語機能としては、①コミュニケーション、②行動コントロール(自分に言い聞かせる)、③思考(言葉で考える)の3つが挙げられる。先述のように重症心身障害とは、狭義には知的障害も運動障害も重度の場合であるが、広義には、運動障害がなく知的障害が最重度(IQ=20以下)で、且つ強度行動障害を伴う場合も含まれる(94頁下13行)。このような場合、自分の要求を言語によって表出し、言葉で行動をコントロールできないため、2次的に行動障害が生じやすい。
(8) 精神機能:
大脳の情報処理については、認知的な側面(認知機能)だけではなく、情意的な側面もある(気分・感情と動機づけ)。例えば、①気分や感情といった快-不快や好-悪についての評価的な機能や、②覚醒レベルや自我機能といった主観的な意識機能、③気質やパーソナリティ、個性といった思考や行動パターンの個人差も、④道徳性や人格も、大脳の情報処理に影響している(精神機能)。気質とは生まれつきの反応傾向の個人差であり、パーソナリティとは発達の過程で経験により形成された思考や行動パターンの個人差である。パーソナリティの基礎は児童期に形成され、思春期・青年期に確立される。確立されたパーソナリティは変化しにくいため、不適応なパーソナリティは持続的な不適応を生じさせ、これがパーソナリティ障害である。どのような精神障害でも、認知機能の側面と精神機能の側面があり、例えば統合失調症の認知機能障害、認知症の周辺症状(BPSD)、高次脳機能障害の社会的行動障害(感情コントロールや道徳性などの問題)、知的障害や自閉症の強度行動障害(二次的な精神障害)(109頁下5行)などが挙げられる。
(9) 各障害の生活ニーズ:
各障害の特徴的な生活ニーズを挙げると、以下のようになる;視覚障害(安全や確認に時間を要し不正確、移動)、聴覚障害(環境音、警報、音声言語によるコミュニケーション)、言語障害(言語理解、言語コミュニケーション)、運動障害(日常生活動作、移動)、内部障害(医療依存度が高い)、精神障害(対人関係、社会生活、気分・感情)、高次脳機能障害(手段的な日常生活動作、病識の欠如)、知的障害(抽象的な理解、社会的な判断)、発達障害(認知特性の偏り、部分的障害、周囲の誤解)。
第3章 自立支援のための連携と協働
第4章 障害の及ぼす心理的影響
第5章 当事者および家族への支援
一般目標:3)
到達目標:6), 7), 8), 9), 10), 11)
(1) 地域生活支援:
障害者福祉では、歴史的に見て障害者は保護収容の対象から、権利の主体として、地域福祉が推進されてきた(23頁)。第2章で学習したように、障害とは病気や怪我、加齢が原因となって生じるものである。しかし、ICFでは、障害者の日常生活や社会生活は、心身機能の低下という生理学的な側面だけではなく、環境因子も影響するとしている。またICFでは、障害の対義語は「生活機能」とされている(3頁欄外、25頁参考文献)。つまり、障害者の自立支援とは生活にかかわるものであり、環境整備や本人のエンパワメントによる生活支援(115頁10行)であるといえる。障害者福祉における生活支援とは、生活ニーズの7つの側面(日常生活動作[ADL]、介護負担、家事、経済、家族関係、社会交流、ストレス)に分けられる(138頁1行)。自立生活支援でとくに重要となるのは、自立生活への動機づけの支援、自立生活の基盤としての権利擁護の2つであり、具体的な実践としては、自立生活プログラム、ピアカウンセリングの2つとなる(139頁4行)。自立生活プログラムとは、障害者のエンパワメント(問題対処の力の獲得)の向上を目的としたプログラムといえる(139頁10行)。地域生活では、ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョンの理念に基づき、自己決定に基づき主体的に暮らすという側面の他にも、権利擁護やリスクを避けるという側面や(203行4行)、医療的ケアの確保の課題もある。
(2) チームアプローチ:
医療分野では感染症を中心とした急性疾患から、日々の生活習慣から生じる生活習慣病を中心とした慢性疾患へと対応の重点が移行し(140頁11行)、チームアプローチの取り組みが先駆的になされた。医療分野で最もチームアプローチを強調しているのがリハビリテーションである(同19行)。リハビリテーションでは、障害の心身機能の範囲の広さへの対応と、病気や怪我からの回復の時間的対応の2つがある(143頁)。心身機能の範囲の広さについて、リハビリテーションには様々な専門職種がある。一方、時間的対応について、リハビリテーションは急性期、回復期、維持期の順に進んでいく(同12行)。
(3) 日常生活動作(ADL):
ADLとは起居動作や身辺のこと、さらに地域で一人暮らしをするためのスキルであり、基本的ADLと手段的ADLの2つに分けられる(130頁欄外)。基本的ADLとは、食事、排泄、更衣、入浴、整容、移乗・移動の6つが挙げられる。一方、手段的ADLとは、掃除、洗濯、調理、買い物、交通機関の利用、金銭管理の6つが挙げられる。ADLが自立していないと介護が必要となる。例えば、運動障害ではどちらのADLにもニーズがあり、高次脳機能障害では基本的ADLは自立しているが手段的ADLに障害があるといえる(124頁下7行)。
(4) 社会資源、ソーシャルサポート:
社会資源とは、社会的ニーズを充足する様々な物質や人材の総称で、社会福祉では社会福祉施設、備品、サービス、資金、制度、情報、知識・技能、人材などにわたる(148頁下11行)。社会資源はフォーマルとインフォーマルに分けられる(同下8行)。フォーマルな社会刺激は行政機関など制度化されているものである。一方、インフォーマルな社会資源の1つに、ソーシャルサポートが挙げられる。ソーシャルサポートとは支援的な人間関係のことであり、ストレス対処や適応にとって重要な役割を果たす(150頁6行)。ソーシャルサポートには、手段的と情緒的の2種類ある(150頁欄外)。地域の在宅障害者のQOLには、家族以外の人間関係の形成、すなわちソーシャルサポートが大きな役割を果たしている(150頁上12行)。障害者のもつ複数のニーズと社会資源を結びつけることがケアマネジメントであり(142頁欄外)、障害者自立支援法から導入された(142頁14行)。障害者のケアマネジメントでは、従来の援助の必要性を中心としたニーズ把握から、当事者の希望、願望に沿ったニーズ把握への視点を変化させており(193頁上5行)、それは個人中心計画と呼ばれる(193頁欄外)。
(5) 障害受容:
障害には客観的な側面と主観的な側面がある。後者の主観的な側面として、①障害受容、②個人中心計画におけるニーズ、③QOL(生活の質・人生の質)などが挙げられる。障害受容について、モリス・グレイソンは、ボディーイメージの再建を提唱した。タマラ・デンボーとベアトリーチェ・ライトは、4つの価値転換を提唱した。すなわち、①価値の範囲の拡大、②比較価値から資産価値への転換、③身体の価値を従属的なものにする、および④障害の与える影響の制限の4つである(180頁下4行)。ナンシー・コーンらのステージ理論では、受傷の心理的ショックからの立ち直りは段階的に進み、障害の受容には「悲哀の仕事」が必要であるとした(180頁5行)。ただし、すべてが障害受容の問題ではない。例えば、①脳卒中後のうつ(171頁11行)、②自殺未遂による受傷(185頁下9行)、③左片麻痺および半側空間無視と合併することの多い病態失認(168頁下13行)、④高次脳機能障害の約半数に認められる病識の欠如(125頁下11行)が挙げられる。
(6) 家族支援:
障害には、本人だけでなく身近な家族にとっての障害という側面もある。ライフステージとは、乳幼児期、学童期、思春期、成人期、高齢期の5つの時期のことであり、それぞれの時期に取り組まれるべき発達課題がある(199頁)。障害に気づく時期や障害の特性によってライフステージのあり方は異なる(202頁下4行)。また、ほとんどの障害児が学齢期に放課後は家族と過ごすことが多く、(200頁下6行)、在宅者の8割程度が家族と同居しているなど(195頁下8行)、これらの発達課題と直面する経験が希薄なため、個々の人生のライフコースを築きにくい(199頁10行)。成人期には介護者である家族の高齢化や親亡き後の問題がある(202頁4行)。生涯を通じて関わる支援機関が存在しないことも課題とされる(203頁1行)。また在宅者の場合、家族が主要な介護者として位置づけられており、在宅介護の介護者のうつは施設介護に比べて高率で発生する(177頁12行)。それは、量的負担が大きいことと、家族への同一化(自分のことように思うこと)といった質的側面があり、それら2つが重なって大きな負担となる(同19行)。それに対しては、家族に対するレスパイトサービスやショートステイの活用が挙げられる(197頁)。
以下余白