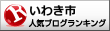本日、K様邸新築工事の”遣り方(やりかた)”を行いました。
遣り方とは?
基礎工事を行う前に、建物の位置・通り・高さなどを、
仮設の杭・大貫材に表示する作業です。
遣り方が間違っていると、建物の位置・高さなども違ってしまうので、
大変重要な作業です。
(ビビリの自分は何度も確認します。コワイので。)
遣り方の事を、別名「丁張り(ちょうはり)」とも言います。
昨日の雨が、朝まで残ってたらイヤだなぁ~と心配していた昨夜、
そんな杞憂も吹き飛ばすような青空!
「さぁ、Let’s 遣り方です!」

まずは、建物から3尺(≒90cm)離した所に、木杭を打っていきます。
木杭は全部で22本打ちます。
(建物の大きさ、形状で本数は変わってきます)
写真の人物は、大工の棟梁コマツさんです。宜しくお願いします。
自分も、大ハンマーで木杭を打っているのですが、コマツさんと比べると、
打つスピードがぜんぜん違います。さすがコマツさん。

木杭を打つために使う、”大木槌(おおきづち)”です。
通称は、大ハンマー(おおはんまー)です。

木杭が打ち終わると、次はレベルと言う測量機器を使って、
木杭1本1本に、任意の水平レベルを出していきます。
そして、そのレベルに合わせて大貫材を釘で固定して行きます。
写真は、杭に大貫材を固定している状況です。

コレ↑が”レベル”です。
正式名称は”オートレベル”です。

大貫材の設置が完了すると、次はトランシットと言う測量機器を使って、
大貫材に建物の直角の墨を出していきます。
そして、その直角の墨から通りの墨を1本ずつ出していきます。

コレ↑が”トランシット”です。
別名、”セオドライト”とも言います。
ちなみにウチの社長は、”トランヒット”と、言ってます(笑)
トランシットの据付って苦手だったのですが、前の会社でお世話になった、
O建設のT玉さんからトランシットの手ほどきを受け、
今では「トランシット2級」の腕前です。
(スミマセンそんな資格はありません。が、もしあったらそれ位だと思います。タブン)

通り墨を出し終えたら、次は四隅を大貫材で筋交い補強を行います。
そして、最後に水糸を使って建物の対角線を出します。
その対角線2本を計測して同じ寸法なら、遣り方は完了です。
対角線の計測結果は、両方とも11m864mmでした。
じゃ~ん、無事に「遣り方完了!」です。
コマツさん、お疲れ様でした。
K様、10時の休憩時に、差し入れありがとうございます。
来週月曜日から、基礎工事がスタートします。
基礎工事は、高萩ブロックさんです。タカハギさん、宜しくお願いします!

遣り方とは?
基礎工事を行う前に、建物の位置・通り・高さなどを、
仮設の杭・大貫材に表示する作業です。
遣り方が間違っていると、建物の位置・高さなども違ってしまうので、
大変重要な作業です。
(ビビリの自分は何度も確認します。コワイので。)
遣り方の事を、別名「丁張り(ちょうはり)」とも言います。
昨日の雨が、朝まで残ってたらイヤだなぁ~と心配していた昨夜、
そんな杞憂も吹き飛ばすような青空!
「さぁ、Let’s 遣り方です!」

まずは、建物から3尺(≒90cm)離した所に、木杭を打っていきます。
木杭は全部で22本打ちます。
(建物の大きさ、形状で本数は変わってきます)
写真の人物は、大工の棟梁コマツさんです。宜しくお願いします。
自分も、大ハンマーで木杭を打っているのですが、コマツさんと比べると、
打つスピードがぜんぜん違います。さすがコマツさん。

木杭を打つために使う、”大木槌(おおきづち)”です。
通称は、大ハンマー(おおはんまー)です。

木杭が打ち終わると、次はレベルと言う測量機器を使って、
木杭1本1本に、任意の水平レベルを出していきます。
そして、そのレベルに合わせて大貫材を釘で固定して行きます。
写真は、杭に大貫材を固定している状況です。

コレ↑が”レベル”です。
正式名称は”オートレベル”です。

大貫材の設置が完了すると、次はトランシットと言う測量機器を使って、
大貫材に建物の直角の墨を出していきます。
そして、その直角の墨から通りの墨を1本ずつ出していきます。

コレ↑が”トランシット”です。
別名、”セオドライト”とも言います。
ちなみにウチの社長は、”トランヒット”と、言ってます(笑)
トランシットの据付って苦手だったのですが、前の会社でお世話になった、
O建設のT玉さんからトランシットの手ほどきを受け、
今では「トランシット2級」の腕前です。
(スミマセンそんな資格はありません。が、もしあったらそれ位だと思います。タブン)

通り墨を出し終えたら、次は四隅を大貫材で筋交い補強を行います。
そして、最後に水糸を使って建物の対角線を出します。
その対角線2本を計測して同じ寸法なら、遣り方は完了です。
対角線の計測結果は、両方とも11m864mmでした。
じゃ~ん、無事に「遣り方完了!」です。
コマツさん、お疲れ様でした。
K様、10時の休憩時に、差し入れありがとうございます。
来週月曜日から、基礎工事がスタートします。
基礎工事は、高萩ブロックさんです。タカハギさん、宜しくお願いします!