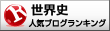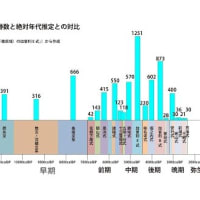金生遺跡の生け垣に、被さるように生えていた雑草、変わった蔓草二つ。なんだか分るでしょうか。

美しい青い玉は、見たことの有るものですが、何という植物なのか、知らないものだったので調べてみたら
アオツヅラフジ 下のもの 蔓が強いことから、縄文時代から葛籠つづら を造るための蔓草だったようです。 蔓は左巻きで上へ。
ブドウのように美しい果実は有毒 アルカロイドがある。
こうした編み籠を作ったようです、ヤブツルアズキの種は漏れてしまいます。粘土を貼り付ければ、漏れ止めが出来そうです。

すずめうり 上のもの カラスウリよりも小さいので、すずめうりというようです。果実は小さいので食べても美味しくもなんともないようです。 蔓は右巻き。 スズメウリが熟すと白い玉になり、生け垣の中では真珠の玉が並んでいるように真っ白く見えている。蔓が細く生け垣のネックレスのようだ。
図は一部お借りしました