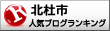唐古鍵遺跡は奈良県磯城郡田原本町あります。

奈良盆地の中央部、初瀬川と寺川の間に挟まれた広大な集落跡です。

約2000年前に水稲栽培を中心とした
森本六爾は奈良県の唐古池(農業用の溜池)の近くの生まれ、
池の堤から多数出土する土器片を集めるのが子供時代の遊びだったという。
土器についていた籾の痕や、煮炊きして焦げた土器片から
彼は弥生水田稲作の提唱をした。
しかし、それを学会で発表する機会を得たものの、
水田もない、農耕用具も出土しないのに何を言うかと、
考古学界の指導者たちからは排斥されてしまった。
専門家の人々は、何故その新しい遺物から解明する方向に進まないのか
そしてその数年後には、夫婦ともに結核で亡くなってしまうという不運に遭遇していた。
六爾は当時の大学の考古学を遺物研究と批判し、
その遺物がどう使われたのか、生活文化はどうだったのか、
それを復元すべきとしたのであるが、
大学の研究者からは空想の産物と批判されていたという。
何故新しい発見の事実からそれをチャンスとして解明する方向に進まないのか
しかしその1年後に逆転劇が起きた。
彼の出発点ともいえる唐古の道路工事現場から、続々と弥生遺跡が発掘されだした。
水田跡、農耕用具に多数の壊れていない土器など出土することにより、
六爾の仮説が証明された。
この時期に道路工事という考古学者の石と関係なく、これが偶然から起きたことからで、
これは考古学者の失敗では無いのか、解明する石の基に、そのために発掘していたのでは無かった。今でもこの発見者はないがしろにされている。
金生遺跡・大配石での太陽暦の発見も同様にチャンスと捉える人、専門家は誰も居なかった。
図と文はお借りしました
引用ーーーーーーーーーーーーーー
在野の考古学者だった森本六爾(1903-36)については、
1920年旧制畝傍中学卒業後小学校の代用教員だったが、その後東京に出て1924年から29年まで考古学者の東京師範教授・三宅米吉の副手(ほとんど無給だと思う)を務めた。この間に、若い研究者と共に考古学研究会を立ち上げ研究雑誌も発行していた。仲間には小林行雄、杉原荘介、藤森栄一、それに妻となったミツギ夫人などがいた。
このうち小林行雄は工学部出身ながら考古学に転じ、唐古遺跡などを研究して京大教授になっている。杉原荘介は戦後、弥生の登呂遺跡を発掘し、さらに相沢忠洋から持ち込まれた旧石器を得て岩宿遺跡を発掘した。
藤森栄一は在野考古学者として八ヶ岳山麓の遺跡を発掘し、縄文農耕論を提唱した。縄文農耕説が正しかったことは、縄文水田の発見や三内丸山遺跡の研究で実証されている。
で、森本六爾であるが、奈良県の唐古池(農業用の溜池)の近くの代々の庄屋の生まれ、池の堤から多数出土する土器片を集めるのが子供時代の遊びだった。東京へ出たのは、上野の博物館で全国から集まった遺物を実測するためだった。
彼が研究会を立ち上げた理由は全国のアマチュア研究者からの情報を集めるためでもあった。そのことによって、古代人の生活の様子、文化の発展や影響関係を見ようとしたのだろう。主として取り組んだ全国の弥生土器の編年は死後になったが、杉原と小林によって完成した。
彼の最大の業績となったのは弥生水田稲作の提唱であるが、その根拠として弥生土器についていた籾の痕や、煮炊きして焦げた土器片だった。しかし、それを学会で発表する機会を得たものの、水田もない、農耕用具も出土しないのに何を言うかと考古学界の指導者たちから排斥されてしまった。彼の師事した三宅米吉がすでに亡くなっていたせいもあるのだろう。
で、その数年後に夫婦ともに結核で亡くなってしまった。しかし1年後に逆転劇が起きた。彼の出発点ともいえる唐古の道路工事現場から、続々と弥生遺跡が発掘されだしたからである。水田跡、農耕用具に多数の壊れていない土器などで、六爾の仮説が証明された。
六爾は当時の大学の考古学を遺物研究と批判し、その遺物がどう使われたのか、生活文化はどうだったのか、それを復元すべきとしたのであるが、大学の研究者からは空想の産物と批判されていた。どうやら当時の考古学は仮説を立てるのを恐れていたに違いない。