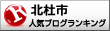八尾の天照御魂神社の位置は、立春に三輪山山頂から昇る朝日を拝する位置にあるが、石見の天照御魂神社の地では、一年でもっとも日照時間が短いが、この日から一日毎に日照時間が長くなる冬至の朝、三輪山山頂から昇る日の出を遙拝していたという。
三輪山

三輪山
「日読み」というのは、八尾と石見の鏡作神社については、三輪山々頂から昇る立春と冬至の朝日を拝する地にあることが重要である。という。
「日読み」とは農耕儀礼であり、農政であり、マツリゴトそのものである。太陽祭祀、つまり鏡作や他田の日祀りは、種まきなどの時期を知り、一粒を万倍にするマツリゴトで最重要祭祀なのであるという。
石見の天照御魂神社では、--- 当社に関する資料がほとんどないため、当社の創建年代・由緒など不詳だが、当社の南方にある石見遺跡(推定・4世紀末~5世紀初頭)が、出土品からみて「当遺跡の祭祀は、祭天の儀を背景とする天的宗儀の色彩をもつ」(石野博信)祭祀遺跡と推測されることから、近接する当社も、同じ頃から続く古代祭祀の聖地(特に日読みの聖地-下記)であったろうという。
石見の天照御魂神社の地では、一年でもっとも日照時間が短いが、この日から一日毎に日照時間が長くなる冬至の朝、三輪山山頂から昇る日の出を遙拝していた。---という。
また、 石見遺跡は五世紀後半のものであり、伊勢の王権祭祀の始まりも五世紀後半とみられている。
こうしたことから、石見遺跡は伊勢などに見る冬至、夏至の日の出が重視される祭祀に繋がるもので、縄文時代以来の唐古鍵遺跡、纏向石塚古墳、纏向遺跡の立春を重視する縄文以来の列島の暦とは異なるものになる。
石見遺跡が5世紀前後とされていることから、チャイナの伝統を継承する種族がここから支配を強めたものなのだろうか。
八尾は石塚古墳成立に近い頃とみられることから成立は200年頃と古いのかも知れないので、
縄文以来の伝統を受け継いでいたのは八尾であり、古来の鏡が残されていたのに、纏向遺跡は消されていた。 「八尾の鏡作神社には三角縁神獣鏡の内区だけの遺品があって、鏡製作の原型と推測できる」
という。 鏡作坐天照御魂神社/神宝の鏡 このような鏡の由緒についても伝えられていない。
こうした八尾の立春を起点とする暦は太陽暦となり固定されて支配者にも動かせないものである。
冬至を起点とする暦は、冬至そのものがその日を判定しがたいものなので、月の満ち欠けの太陰暦と合わせて時の支配、暦の支配には都合良く、毎年公布することで支配力を生じてくる。
縄文時代から続いてきた太陽暦の伝統 立春起点の暦は支配には不都合なので、纏向廃絶後は冬至起点に変えられ暦は支配するための道具と変えられたものと考える。
チャイナから入ってきたとすれば、それは太陽暦では無く、支配のため公布する太陰太陽暦というものだったのではないのか、それは冬至夏至を祭祀するのを主とするものだったのだろう。
三輪山からの日の出時期

しかしその後も立春起点の暦は、八十八夜、二百十日など、細々と残ってきた。
写真と図はお借りしました