


ある日の夕方、このマンホールの上を自転車で通り過ぎた時
「世の中こんな事があっていいのか!」と思ったのですが
暗くなってきて撮影に適していなかったし
沖縄の首里城と違って消失することはないので撮影は後日でも構わないと思ていたのですが
何度も忘れてしまい今日の休みに思い出したように撮りに行ってきました。
首里城の話を出したのは、ある方が沖縄に観光に行った時に
「首里城は逃げることはない」と思って次に来た時にしようよ思っていたら
火事で焼けてしまい後悔したという話を読んだ記憶からそう思ったからです。
このマンホールたちを見た時は本当に世の中こんなことがあっていいのかと思いましたが
調べてみたら通称「親子蓋」と呼ばれているもので珍しいものではないそうです。
小さい子供の蓋は通常のマンホールサイズで親のほうは結構巨大です。
子供のほうは人間が入るためのもので親のほうは機械を入れるための物だそうです。
また子供のほうが中心より片寄って付いているのはそちら側に梯子があるからです。
当然ながら大きいのだけあればいいのではないか、
大は小を兼ねないのかという疑問が起こりますが
その前に天才科学者であるアイザック・ニュートンの話を書きます。
ニュートンは家に猫の親子が来るようになった時に
猫たちを家に入れるために
お母さん猫用の大きい出入り口と子猫用の小さい出入り口と2つ作ってあげたそうです。
ニュートンは偉大なので現代のマンホールにまで影響を与えているのかと思ったら
そうでもないようで
小さいサイズのほうは企画刺されていて、器具などにはそちらに合わせて作られている物多くあり
大きい蓋を開けるとその器具がストンと落ちてしまうので
大きい親の蓋の中に小さい子供の蓋を作ったということだそうです。
理由を聞けば当たり前のことですが
世の中いろんなことがあるものですね。













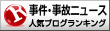

















ありがとうございます、長年の疑問が溶けました。
一つで良いという話があります。
調べてみましたがやはりニュートンでした。
キャットドアを発明したのもニュートンらしいですが
まだ確定にはいたってません。
子猫も大きいほうのドアしか使わなかったらしいですが
これもまだ確定できてません。
1つで良いかどうかの決定権は子猫にあると思いますが
もしかしたら人間でもよくあるように親猫が決めるのかもしれません。