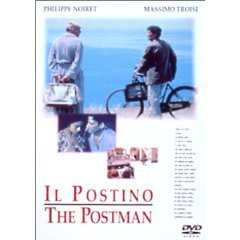
「イル・ポスティーノ」 (イタリア=フランス 1994年)
監 督 マイケル・ラドフォード
原 作 アントニオ・スカルメタ
出 演 マッシモ・トロイージ(マリオ)
フィリップ・ノワレ(パブロ・ネルーダ)
マリア・グラッツィア・クチノッタ(ベアトリーチェ)
映画は最近あまり観ていない。実は少しは観ているけど、ここに書いて残しておきたい、と思えるものに出会えなかったのかも。
これは小さな作品だけど、琴線にちょっと…、です。
●青年と詩人の交流
イタリア・ナポリの沖合の美しい小さな村。
漁業でつつましやかな生計をたてている島民の中で、父親のその職業をつぐこともなく、なんとなく自立できぬままに暮らす青年マリオ。とくにヤンチャでもなく、穏やかだけれど深くもなく…、いわゆるふつうの若者。どうにかしないとまずいのだけれど、自らどうにかしようと強く思うでもなく、かといって父親に依存していることをよしと思っているでもなく。
そんな彼がひとつの仕事を得る。チリかあら亡命してきたコミュニストの詩人パブロ・ネルーダが島に滞在することになり、その間彼にとどく郵便物を届ける仕事だ。
美しい島の海沿いの道を自転車で走り、一日に一回郵便を届ける。人民に愛される偉大な詩人もマリオにとっては特別な存在ではない。自然に素朴に触れあい、率直に純朴に疑問を口にしていく。
詩とは? 暗喩とは? そんな小難しげな疑問が実際の言葉のやりとりでマリオの中に浸透していく。詩をかきたいと思う。そして、恋に落ち、ゆっくりとではあるが何かを得ていくマリオ。それをまるで年上の友人のように見守るネルーダ。
何も事件らしいことはただの日常が美しい光景の中で進行していく。たぶんここまでが長い長い導入なのだろう。
ドラマはネルーダがチリに戻ることになり、島を離れるところから始まるといっていいだろう。
永遠の友情を誓ったはずなのにネルーダからはなんの連絡もない。寂しさと「やりきれなさをうちに秘めながら、マリオは最後に気づくのだ。自分がネルーダからどんなにたくさんのものを受け取ったのかを。マリオは録音機を使って、島のさまざまな「光景」を録音する。打ち寄せる波の音、吹きすさぶ風の音、漁の網が巻かれる音、教会の鐘…。
数年後、島を再び訪れたネルーダは、マリオの妻からそのマリオからのメッセージをきく。マリオはコミュニストの集会で詩を披露することになっていたが、そこでの混乱に巻き込まれ命を落として、もういない。ただネルーダからの名前をとった子どもが残されているだけだ。
メッセージを聴くネルーダの静かな笑顔がいい。
●島の風景とマリオのメッセージと詩人の思い出
青年マリオの成長がことさらに強調されないところが好ましい。
相変わらずのんびりで、はっきりしないところもいい。
ただ、ネルーダと知り合ったことで、言葉に敏感になり、それなりに世の中に目を向け始め、女性を愛する喜びや苦しさを味わう。さりげなさがなによりステキに描かれる。
島の風景は限りなく美しい。1950年代初期のその光景は自然の美しさだけではなく、長い戦争から解放され、さまざまな思想が許された島の人々の自由をも表しているのか。貧しい暮らしは変わらず、彼らの善良さから何かを搾取する存在もなくはないのだが、彼らはどこまでも率直で純粋だ。
ネルーダにとって、その島での暮らしはどんな重さを残したかはわからない。マリオのそれとは差があって当然だろう。「たくさんの大切な思い出のひとつ」だったのだと思えば、納得いくというものだ。
それでも再び訪れて亡きマリオが録音した「島の風景」と彼のメッセージを聴き、ネルーダの胸に去来したものを想像すると、少しせつなくなる。
思い出はそういうものだ。懐かしいとつねに思っていたら、それはたぶん「思い出」に昇華しないかもしれないし、「つねに思っている思い出」なんてあるわけないといえないこともない。
何かのきっかけにふっと胸に浮かぶ思いや風景や人こそ、私たちをとらえて離さない。
マリオはそういうものを詩人ネルーダに呼び起こす「言葉の力」をかつてその本人から教わったのだと思うと、なんだか愉快な気持ちになれる。
マリオを演じたマッシモ・トロイージはこの映画の製作に携わり、病をおして撮影に参加をしていたそうだ。クランクインの直後に亡くなったという。
詩人パブロ・ネルーダを演じたのはフィリップ・ノワレ。ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、「ニュー・シネマ・パラダイス」で映画技師を演じた俳優。
あの映画のラストシーンを思い出し、それだけで胸がいっぱいになっているワタシです。
監 督 マイケル・ラドフォード
原 作 アントニオ・スカルメタ
出 演 マッシモ・トロイージ(マリオ)
フィリップ・ノワレ(パブロ・ネルーダ)
マリア・グラッツィア・クチノッタ(ベアトリーチェ)
映画は最近あまり観ていない。実は少しは観ているけど、ここに書いて残しておきたい、と思えるものに出会えなかったのかも。
これは小さな作品だけど、琴線にちょっと…、です。
●青年と詩人の交流
イタリア・ナポリの沖合の美しい小さな村。
漁業でつつましやかな生計をたてている島民の中で、父親のその職業をつぐこともなく、なんとなく自立できぬままに暮らす青年マリオ。とくにヤンチャでもなく、穏やかだけれど深くもなく…、いわゆるふつうの若者。どうにかしないとまずいのだけれど、自らどうにかしようと強く思うでもなく、かといって父親に依存していることをよしと思っているでもなく。
そんな彼がひとつの仕事を得る。チリかあら亡命してきたコミュニストの詩人パブロ・ネルーダが島に滞在することになり、その間彼にとどく郵便物を届ける仕事だ。
美しい島の海沿いの道を自転車で走り、一日に一回郵便を届ける。人民に愛される偉大な詩人もマリオにとっては特別な存在ではない。自然に素朴に触れあい、率直に純朴に疑問を口にしていく。
詩とは? 暗喩とは? そんな小難しげな疑問が実際の言葉のやりとりでマリオの中に浸透していく。詩をかきたいと思う。そして、恋に落ち、ゆっくりとではあるが何かを得ていくマリオ。それをまるで年上の友人のように見守るネルーダ。
何も事件らしいことはただの日常が美しい光景の中で進行していく。たぶんここまでが長い長い導入なのだろう。
ドラマはネルーダがチリに戻ることになり、島を離れるところから始まるといっていいだろう。
永遠の友情を誓ったはずなのにネルーダからはなんの連絡もない。寂しさと「やりきれなさをうちに秘めながら、マリオは最後に気づくのだ。自分がネルーダからどんなにたくさんのものを受け取ったのかを。マリオは録音機を使って、島のさまざまな「光景」を録音する。打ち寄せる波の音、吹きすさぶ風の音、漁の網が巻かれる音、教会の鐘…。
数年後、島を再び訪れたネルーダは、マリオの妻からそのマリオからのメッセージをきく。マリオはコミュニストの集会で詩を披露することになっていたが、そこでの混乱に巻き込まれ命を落として、もういない。ただネルーダからの名前をとった子どもが残されているだけだ。
メッセージを聴くネルーダの静かな笑顔がいい。
●島の風景とマリオのメッセージと詩人の思い出
青年マリオの成長がことさらに強調されないところが好ましい。
相変わらずのんびりで、はっきりしないところもいい。
ただ、ネルーダと知り合ったことで、言葉に敏感になり、それなりに世の中に目を向け始め、女性を愛する喜びや苦しさを味わう。さりげなさがなによりステキに描かれる。
島の風景は限りなく美しい。1950年代初期のその光景は自然の美しさだけではなく、長い戦争から解放され、さまざまな思想が許された島の人々の自由をも表しているのか。貧しい暮らしは変わらず、彼らの善良さから何かを搾取する存在もなくはないのだが、彼らはどこまでも率直で純粋だ。
ネルーダにとって、その島での暮らしはどんな重さを残したかはわからない。マリオのそれとは差があって当然だろう。「たくさんの大切な思い出のひとつ」だったのだと思えば、納得いくというものだ。
それでも再び訪れて亡きマリオが録音した「島の風景」と彼のメッセージを聴き、ネルーダの胸に去来したものを想像すると、少しせつなくなる。
思い出はそういうものだ。懐かしいとつねに思っていたら、それはたぶん「思い出」に昇華しないかもしれないし、「つねに思っている思い出」なんてあるわけないといえないこともない。
何かのきっかけにふっと胸に浮かぶ思いや風景や人こそ、私たちをとらえて離さない。
マリオはそういうものを詩人ネルーダに呼び起こす「言葉の力」をかつてその本人から教わったのだと思うと、なんだか愉快な気持ちになれる。
マリオを演じたマッシモ・トロイージはこの映画の製作に携わり、病をおして撮影に参加をしていたそうだ。クランクインの直後に亡くなったという。
詩人パブロ・ネルーダを演じたのはフィリップ・ノワレ。ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、「ニュー・シネマ・パラダイス」で映画技師を演じた俳優。
あの映画のラストシーンを思い出し、それだけで胸がいっぱいになっているワタシです。

























