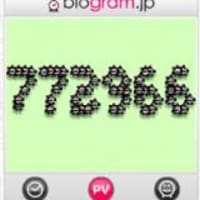用事ついでに、東京ミッドタウンへ。
とっても久しぶり。

サントリー美術館で開催中「日本美術の裏の裏」展を観ました。
裏の裏……
 (あんまりマニアックで、お勉強チックな展示だと疲れちゃうな)
(あんまりマニアックで、お勉強チックな展示だと疲れちゃうな) と
と少し迷ったのですが

実際に入ってみたら、いつもより少し詳しめで
くだけた表現の解説がついているかな、程度で
気楽に観られました。
撮影OKなのも◎。
こんな風に、展示室の仕切りが“ふすま”になっているなど
ちょっとした遊び心も。
今回、特に見入ったのは

やっぱり、ミニチュア。
おもに江戸後期以降流行った、超絶技巧。


黄瀬戸、赤絵、そして織部…
おうちに一式欲しい!なんて思ってしまった可愛いミニチュアたち。

こちらは野々村仁清の香合。

同じ鶴でも、角度によって
私には鶴の“意思”が違ってみえるような。
左はきりっと。右はどこか遠くに思いを馳せているよう。
こちらは伊賀焼だったかな

どちらを表にするかで雰囲気ががらっと変わります。
こちらの山水画は、

秘境のような場所で、一人お屋敷から遠くを眺めている姿が
眼に留まりました。

「アマゾン、早く来ないかな」
展示後半は、和歌の世界も。

奈良、平安、鎌倉と、和歌は教養の一つであり、
たやすく顔が見られない
男女間では貴重なコミュニケーションツールでもあり、
上手な歌が詠める=男女問わずアイドル的存在 だったそう。
で、そんな歌人を集めてグループ化されることもあったそうで
その代表格が平安時代の「三十六歌仙」。
花の色は 移りにけりな いたづらに 我身世にふる ながめせしまに
で有名な、小野小町も入っています。
今回の展示は総花的であったのと、
元禄の大衆文化がもうちょっとあればとも思いましたが
(歌川広重はありましたが)
ああ、やっぱりネットなどではなく、
実物を観るっていいなあ。と、改めて実感したひとときでした。