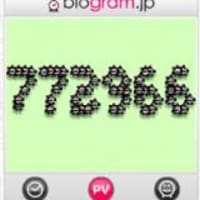三菱一号館美術館で開催中の「パリ・グラフィック展」へ。
着て行ったのは

寒い日だったので、今冬初の結城紬。
遠州椿が織り出されています。
帯は日曜日にも締めた雪椿の半幅。
今回は、椿尽くしになりました。
帯飾りも結城紬。端切れでつくられたがま口です。
上半身と後ろはこんな感じ。

デジカメを替えたのですが、露出などの設定の塩梅が
まだよくわからず、見難くてすみません…。
横はこんな感じ。背中がふくらんでしまい、反省です


---------------------
美術館前の中庭にはこんなツリー型のオブジェが。

何度か書いていますが、私は本当に絵心というものがなく、

これはモーリス・ドニの作品ですが、
こうしたポスターを観るたび、
どうしたらこんなにインプレッシブな描写ができるんだろう、と
感心してしまいます。
以前、アルフォンス・ミュシャ展のレポでも出しましたが、

左からロートレック、シェレ、ミュシャ。
いずれも商用ポスターですが、女性の表現に個性が出ています。
面白いなあと思ったのが、
庶民の暮らしぶりを歌うシャンソンの楽譜の表紙に、
こうしたグラフィカルな絵が好んで使われたこと。
19世紀末パリでは、街なかに貼られたポスターを
散歩しながら一日中眺めるのが、いわゆる知的階級の間で
流行ったそうで、
楽譜の表紙絵も、そうしたちょっと上流層にたいへん受けたそう。
もし表紙絵が飾り気のないものだったら、
シャンソンがこんなにパリに流行、定着することもなかったの
かも知れません。
館内の、撮影OKエリア。

アール・ヌーヴォー期のグラフィックはもちろん、
色の綺麗さや魅力的なモチーフも売りの一つではありますが、
よくよく観ていくといろんなタイプがあって

エリー・ランソンのような、
毛筆を思わせる線のタッチが個性的なもの

エミール・ラブルールや、後に出すヴァロットンのような
モノトーンの版画

アンリ・リヴィエールのような
浮世絵の影響を大きく受けたもの
商用グラフィックの流行により
アートの敷居が低くなった、というか支持層が広がり、
表現方法の多様化につながった、そんな市井の活気を感じます。
私は

少し前の「ナビ派」展でも観た、
ヴュイヤールの作風がとても好きです。柔らかな色と伸びやかな構図。
パリでのグラフィックの流行を支えたアナザー・サイドとして

これも以前観た「ヴァロットン展」にもあったのですが
いわゆる上流階級、知的階級の人の間では、
自宅や、同好の士が集まるサロンなど、ともかく閉ざされた空間で
官能的な作品や、スピリチュアル的な、呪術的な作品を鑑賞するのが
嗜みのようになっていたそうで
なるほど、「ナビ派」(=預言者)の作品群にそういう一面があったのは、
そんな“マーケット”が存在していたからなのかな、と。
アーティストから発信されたものが受け入れられたのか、
それとも、
世間の求めに応じる形でそんな作品がつくられるようになったのか、は、
鶏と卵のようなもので、はっきりしませんが・・・。
アール・ヌーヴォー期の美術展は、観ていてそう難しいことを考えず楽しめるし、
実際面白いし、で、国内での開催回数も多いのでしょう。
私も、最近数年間を振り返ってみてもいろいろ、足を運んでいます。
下に、思い出す限りの、過去の関連記事のリンクを貼っておきますね。
・ミュシャ展
・ヴァロットン展
・ナビ派展