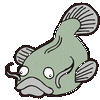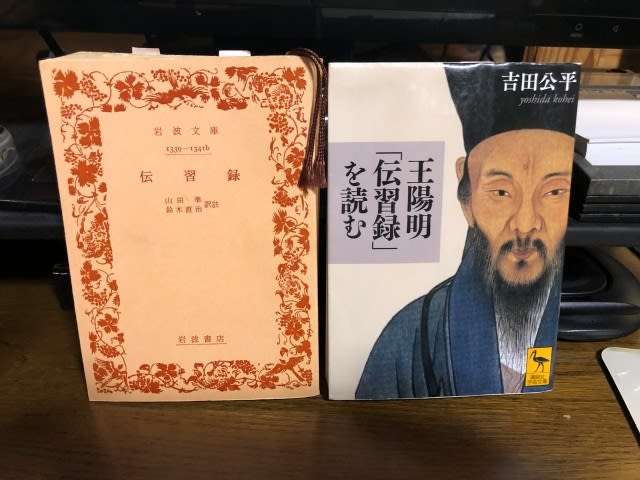その教義が如何に優れていようとも、宗教の怖さは、それが本質的に排他性と独善性を有していることだ。
それは、世に知られ、信徒が増え、更に広めるために教団が組織され、集団として動き始める時に顕在化しだす。
信者はどうすべきか?
何より、教祖教主に盲目的に従ってこそ信者なのである。教祖教主に対する盲目的な狂信こそが、教義を信ずる者の教主に対する信徒としての根本姿勢であらねばならないではないか。
とすれば、教主が「彼らを、我々の教えに従わせ、目を開かせることこそが、彼らの幸せなのである」といえば、騙したり、賺したり、脅したり、果ては暴力を使ってでも、その信仰に従わせようとせねばならぬではないか。また、教主が「あれはわれわれの信ずる教義の敵である。如何なる手段をもってしても排除抹殺せねばならぬ」と言えば、ありとあらゆる手段を講じて敵をそうしようとせねばならぬではないか。
それが使命とあれば、そうするのが信徒の使命であろう。
又、教義も後の者によって都合の良いように解釈はできるのだ。それは自己の組織の強化のため、より一層排他的狂信的になるのは必然である。
十字軍、宣教師、魔女狩り
文明へと目を開かせる、信仰の喜びを与える、信仰を守る、聖地を守るなどと、独善的で身勝手でおせっかいな理由を構えて、如何なる残虐と殺戮が、静かに平和に暮らしていた人々に為されたことか。
芸能人のファンを見ると、あれは一種の宗教であると思う。少なくともその要素が濃厚にある。少しでもファンの対象芸能人の悪評価や非難を言うと、ファンは集団となって、食って掛かって否定にかかる。
その様は正にFANATIC(狂信者)である。
宗教が常に排他的であり狂信的であったとしても、個々人の心の問題にのみ容喙するならまだしもその存在も許されるだろうが、現世の政治や社会に容喙し出すとそれは恐怖となって人を威圧する。
それは必ず組織集団として我々個々人に迫ってくる。だから恐ろしいのだ。
政治に宗教が口出さぬ限りにおいて存在が許されるという信長の政治的姿勢は評価されるべきであると思う。
今は多くの制約の中で仮面を被っているが、いつ牙を剥くかわからぬ得も言われぬ不気味な存在なのだ。
暴力を振るわずとも、無言で威圧し、我々を思う方向に従わせられるように、我々が気付かぬようにその悪謀が進んでいるのかもしれない。