
以前から、鷲田清一さんの文をまとめて読みたいと思っていました。
抱えていた原稿を無事に送り出すことができて、その時が来たように感じて。
どの文も、独創的。決して難しいことはなく、見たことのない言葉の編まれ方にはっとしたり、支えられたりする。
この本は、新聞に掲載されたコラムが中心ですが、タイトル通り、「生きながらえる術(すべ)」に方向が集中しています。
中核をなすと思われる概念、私の心にも残ったものが「ブリコラージュ」でした。
《ブリコラージュ》とは、「ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る」こと。いってみればレシピに従って材料を買い揃え、調理するのではなく、とりあえず冷蔵庫にある材料でなんとか工夫してお惣菜を作るようなもの。要は、限られた手持ちのものや使い古しのもの、もはや不要となったがらくたを、別の目的ないし用途に流用すること、使い回すことを意味する。 139ページ13行ー17行
文化人類学者のレヴィ=ストロースが「野生の思考」で提唱した概念だそうです。
なぜ、私に響いたのか?
私の書く仕事は、すべてこのブリコラージュ。そしてこの仕事がどうして大事かと言えば、手仕事を通じて初めて自分は生きている感覚を保てるから。
逆に、「生きながらえない術」とは何でしょう?
近代化や資本主義が推し進めてきたものは何でしょう?
あらゆる仕事の現金化ではないでしょうか?
この本にも書いてあってけど、どんどんサービスが開発され、行き渡り、人々はお金さえ渡せば私の仕事を身代わりしてくれる。
サービスはシステムで運営されている。便利とお金を追求し続けた果てに、人々はサービスにぶら下がるだけになっていないか? 振り落とされたとき、再起できる術を身につけてきたのか?
自分たちだけで、ありあわせのもの、人たちで、今必要なもの、形、言葉や概念、場や法を作り上げる。
東日本大震災で最も必要とされた術もまたそれだったのではないでしょうか。
今のコロナ禍で必要とされているものも。
著者の鷲田さんは、京都で生まれ育ちました。そこには、さまざまな手仕事を受け持ち、つながる人たちが暮らしていました。
鍛冶屋といっても一軒だけで成り立ってはいない。包丁を使う料理人がおり、刃物と柄を作る仕事は別々にある。そこに、下請けも孫請けもない。
術はアート(芸術)でもあります。
芸術は、実はあらゆる仕事に共通する。
芸術家たちに得意なことは、そのまま「生きながらえる術」になりうる。
マニュアルを嫌い、目標も設定せず、自分が何をしようとしているのかもわからないまま、感覚という身体の知性を頼りに、世界や時代をまさぐる。「想定外」のことが起こっても、とりあえずは周りのありあわせの物でなんとかやりくりして繕う。
異変の兆候への鋭い感受性と、どんな状況にも手業(てわざ)で対処できる器用さ。
小説家に求められている能力もまさにそれだと言えます。
この小文を書いている途中でお腹が空き、昼ごはんを作って食べました。
今日はひんやりするから温かいものがいいなあ。
登山したはずみで食べすぎたから胃に優しいものを。
おかゆかなあ。
で、湯を沸かし始め、その間に冷蔵庫をあさる。
里芋と竹輪の煮っ転がしがあった。これを入れてみよう。
梅干しと卵は定番。あとしらすがあったので投入。仕上げに醤油をちょっと。
これがおいしかった。料理は、まさにブリコラージュの実践。
そんな感慨に浸りながら食べていると、思い出す光景が二つあった。
一つは、泥で作ったホールケーキ。
雨降りの日、びしゃびしゃどろどろになって、泥遊び。どこかに落ちていた白のスプレー缶がひらめきを与えた。
私の中では最高傑作の一つになっている。それを見た親が、「わーすごい。おいしそー」と言ってくれたかどうか?
もう覚えていないけど、少なくとも「汚いからやめなさい!」と怒られはしなかったのは確かでしょう。
もう一つは、僕が最初に自分で買ったおもちゃのこと。
気仙沼のおばあちゃんと、気仙沼の百貨店で、僕は自由に好きなものを買ってよかった。
誕生日プレゼントだったかどうかも覚えていない。
覚えているのは、おばあちゃんがにこやかに見守っていたこと。
アドバイスもおすすめも押し付けも一切なかった。
優柔不断だから(慎重とも言います)、かなり迷っていたと思う。その間、ずっとおばあちゃんは手出し、口出ししなかった。
最終的に僕が選んだのはレゴブロックの郵便局。
レゴは、この本でも紹介されています。「よく遊べ」という意味だとか。
そう、ブリコラージュは遊びに通じている。
やっぱり人は遊ぶために生きている。
遊び(楽しみ)のないところに未来もまたありません。
鷲田清一 著/講談社/2019
抱えていた原稿を無事に送り出すことができて、その時が来たように感じて。
どの文も、独創的。決して難しいことはなく、見たことのない言葉の編まれ方にはっとしたり、支えられたりする。
この本は、新聞に掲載されたコラムが中心ですが、タイトル通り、「生きながらえる術(すべ)」に方向が集中しています。
中核をなすと思われる概念、私の心にも残ったものが「ブリコラージュ」でした。
《ブリコラージュ》とは、「ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る」こと。いってみればレシピに従って材料を買い揃え、調理するのではなく、とりあえず冷蔵庫にある材料でなんとか工夫してお惣菜を作るようなもの。要は、限られた手持ちのものや使い古しのもの、もはや不要となったがらくたを、別の目的ないし用途に流用すること、使い回すことを意味する。 139ページ13行ー17行
文化人類学者のレヴィ=ストロースが「野生の思考」で提唱した概念だそうです。
なぜ、私に響いたのか?
私の書く仕事は、すべてこのブリコラージュ。そしてこの仕事がどうして大事かと言えば、手仕事を通じて初めて自分は生きている感覚を保てるから。
逆に、「生きながらえない術」とは何でしょう?
近代化や資本主義が推し進めてきたものは何でしょう?
あらゆる仕事の現金化ではないでしょうか?
この本にも書いてあってけど、どんどんサービスが開発され、行き渡り、人々はお金さえ渡せば私の仕事を身代わりしてくれる。
サービスはシステムで運営されている。便利とお金を追求し続けた果てに、人々はサービスにぶら下がるだけになっていないか? 振り落とされたとき、再起できる術を身につけてきたのか?
自分たちだけで、ありあわせのもの、人たちで、今必要なもの、形、言葉や概念、場や法を作り上げる。
東日本大震災で最も必要とされた術もまたそれだったのではないでしょうか。
今のコロナ禍で必要とされているものも。
著者の鷲田さんは、京都で生まれ育ちました。そこには、さまざまな手仕事を受け持ち、つながる人たちが暮らしていました。
鍛冶屋といっても一軒だけで成り立ってはいない。包丁を使う料理人がおり、刃物と柄を作る仕事は別々にある。そこに、下請けも孫請けもない。
術はアート(芸術)でもあります。
芸術は、実はあらゆる仕事に共通する。
芸術家たちに得意なことは、そのまま「生きながらえる術」になりうる。
マニュアルを嫌い、目標も設定せず、自分が何をしようとしているのかもわからないまま、感覚という身体の知性を頼りに、世界や時代をまさぐる。「想定外」のことが起こっても、とりあえずは周りのありあわせの物でなんとかやりくりして繕う。
異変の兆候への鋭い感受性と、どんな状況にも手業(てわざ)で対処できる器用さ。
小説家に求められている能力もまさにそれだと言えます。
この小文を書いている途中でお腹が空き、昼ごはんを作って食べました。
今日はひんやりするから温かいものがいいなあ。
登山したはずみで食べすぎたから胃に優しいものを。
おかゆかなあ。
で、湯を沸かし始め、その間に冷蔵庫をあさる。
里芋と竹輪の煮っ転がしがあった。これを入れてみよう。
梅干しと卵は定番。あとしらすがあったので投入。仕上げに醤油をちょっと。
これがおいしかった。料理は、まさにブリコラージュの実践。
そんな感慨に浸りながら食べていると、思い出す光景が二つあった。
一つは、泥で作ったホールケーキ。
雨降りの日、びしゃびしゃどろどろになって、泥遊び。どこかに落ちていた白のスプレー缶がひらめきを与えた。
私の中では最高傑作の一つになっている。それを見た親が、「わーすごい。おいしそー」と言ってくれたかどうか?
もう覚えていないけど、少なくとも「汚いからやめなさい!」と怒られはしなかったのは確かでしょう。
もう一つは、僕が最初に自分で買ったおもちゃのこと。
気仙沼のおばあちゃんと、気仙沼の百貨店で、僕は自由に好きなものを買ってよかった。
誕生日プレゼントだったかどうかも覚えていない。
覚えているのは、おばあちゃんがにこやかに見守っていたこと。
アドバイスもおすすめも押し付けも一切なかった。
優柔不断だから(慎重とも言います)、かなり迷っていたと思う。その間、ずっとおばあちゃんは手出し、口出ししなかった。
最終的に僕が選んだのはレゴブロックの郵便局。
レゴは、この本でも紹介されています。「よく遊べ」という意味だとか。
そう、ブリコラージュは遊びに通じている。
やっぱり人は遊ぶために生きている。
遊び(楽しみ)のないところに未来もまたありません。
鷲田清一 著/講談社/2019










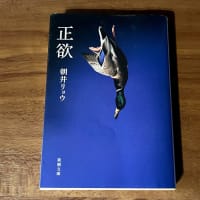
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます