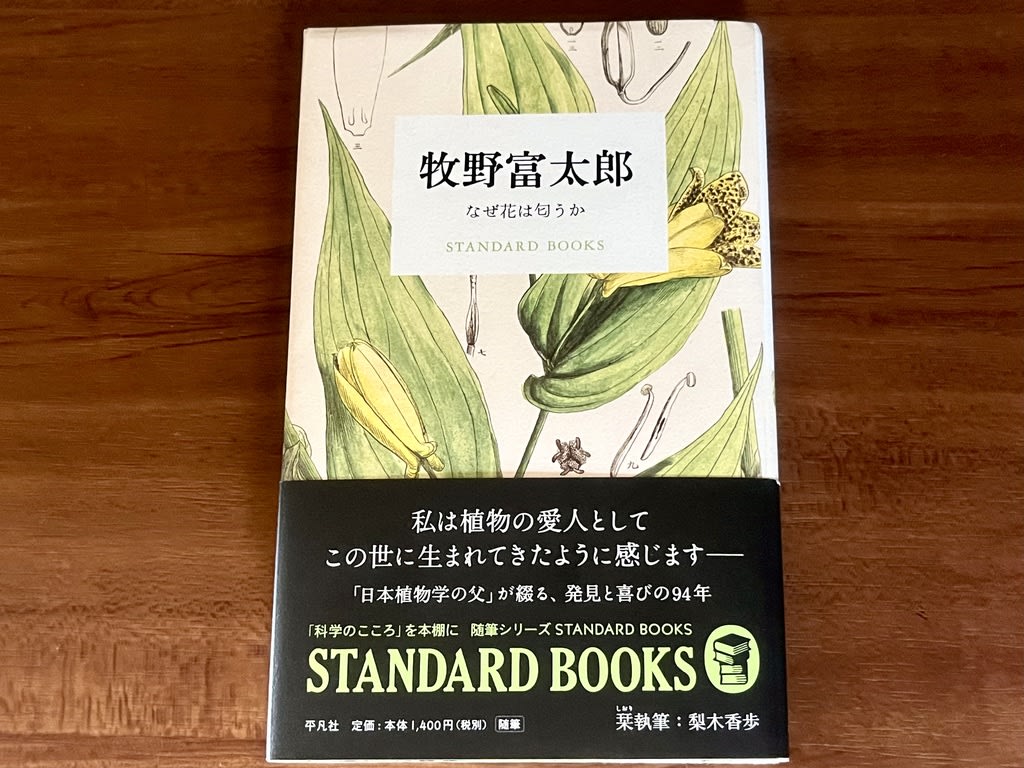3度目の読書。
書いていた小説がひと段落し、「共同執筆者」の夢にも促されてこの『デミアン』に手が伸びました。落ち着いたら読もうと買ってはいたのですが。
3度目なのですが、だからか今回はずいぶんと細部が見えた感じがしました。今までの読書では見落としていたのではないかというような。それは新潮文庫ではなく初めて岩波文庫にしたからかもしれません。訳者が違うので、全体的な雰囲気も変わります。岩波版の方が丁寧で柔らかい印象です。例えば新潮文庫では、最後に登場する重要な人物の一人であるエヴァ夫人が主人公を呼ぶとき「シンクレール」と呼び捨てですが、岩波文庫では「ジンクレエルさん」とさん付け。名前も若干変わっていますが、ドイツ語をかじった身としては「ジンクレエル」の方が原文に近い感じがします。
ジンクレエルは少年時代、クロオマアという年上の男に苦しめられます。クロオマアは暴力を振るってカツアゲしたわけでもいじめたわけでもありません。ただ、ジンクレエルが裏世界ではボスのクロオマアに認められたいがためについた嘘を利用してどこまでもたかるのです。少年らしい冒険譚の披露大会。そこでジンクレエルは農園からりんごを盗んだと言ってしまいます。クロオマアは、そのりんご園の主人が泥棒を捕まえるために賞金を出していたことを知っていました。ジンクレエルの嘘なのに彼は嘘ではないと誓ってしまう。クロオマアは言うぞ言うぞと脅してジンクレエルからお金をむしり取っていく。うちは貧しくてお前は裕福だという理屈もつけて。
ジンクレエルはどれだけ両親に真実を告げたかったか。だけど自分は嘘をつき、ごろつきとも付き合っている。自分はもう両親たちの住む「明るい世界」には戻れないのだと悲観する。びくびくとして過ごし、体まで病んでしまい、どうすればいいのかわからない。そんなとき、学校に転校生がやってきた。少し年上で、その名をデミアンと言った。
デミアンはジンクレエルと付き合うようになり、彼が苦しんでいることをも見抜いてしまう。そして聞き出すのでした。クロオマアのことを。
デミアンがクロオマアに何をしたのか記述はありません。が、ジンクレエルが道端でばったりとクロオマアと鉢合わせたとき、彼は渋い顔をして、ジンクレエルから逃げ出したのでした。
それからデミアンとの交流は続きますが、進学を機に離れてしまう。ジンクレエルは安い飲み屋に入り浸るようになり、勉学にも身が入らず孤立し、またしても精神の危機に陥ります。そのとき、彼は街中で見かけた女性(ベアトリイチェ)をモデルに絵を描き、その絵を心に掲げることで危機を乗り越えます。そのあと、もう一枚重要な絵を描きます。それは鳥が卵の殻を破って外に出ようとしている姿。その鳥は、ジンクレエルの実家の門に掲げられていた紋章でもありました。
印というのが作品の鍵にもなっています。その鳥が飛んでいく目的の神「アブラクサス」もそうですが、カインの額の印も重要なモチーフです。
カインとアベル。聖書に出てきます。カインは兄でアベルは弟。アベルへの両親の愛に嫉妬したカインが弟を殺してしまう。人類初の殺人と言われています。神はカインの額に印をつけた。それはカインに危害を加えさせないため。心理学では、兄弟間の親の愛をめぐる葛藤をカインコンプレックスと呼びます。
デミアンは、カインを擁護したのでした。それは学校での教えには反することでした。カインは悪者と相場は決まっていたから。デミアンとジンクレエルが目指していた神はアブラクサスであり、要するに善と悪が融合した神なのでした。
ヘッセの作品では、己の心にある「明るい世界」と「暗い世界」、「善」と「悪」の葛藤、その克服が大きなテーマになっています。それは彼自身が牧師の子であり、それだけにこの悪を見ないわけにはいかないじゃないか! というような心の叫びに敏感だったからかもしれません。それに大きな善と悪の混沌=戦争が目と鼻の先にありましたから。戦争は、この作品でも大きな影を落としています。
ジンクレエルは、デミアンと離れている間、二人の友人に恵まれていました。この期間が、私の中では希薄になっていた箇所です。一人がピストリウス。もう一人がクナウエル。
ピストリウスはオルガン弾き。教会から溢れてくるオルガンの音楽にジンクレエルは引かれて彼と出会います。ピストリウスも牧師の子で牧師になる道を歩んでいましたが脱線した口でした。ピストリウスの家で、ジンクレエルはじっと暖炉の炎を見る。心を見る。自分と向き合う。ピストリウスはそのように導く。彼はたくさんの知識も持っていた。こんな秘宝もある、あんな術もある。宗教っていいな。そんなピストリウスに救われたジンクレエルでしたが、ピストリウスが「古さ」から出てこないことを見抜いてしまう。
「ピストリウス。」とぼくは不意に言った——われながら意外な、おそろしい勢いで、悪意をほとばしらせながら。「また何か夢の話を、聞かせてほしいな。あなたがゆうべ見た、ほんとうの夢の話をね。今あなたの話していることは——じつにたまらなく古めかしいんでね」 213ページ15行〜214ページ2行
ピストリウスは反撃しなかった。そのことで、ジンクレエルは人を傷つけてしまったと悔やむ。
クナウエルはジンクレエルをつけてきた。そしてジンクレエルに期待していた。この人は知っていると。何を? 禁欲を。性的な欲求とどう向き合えばいいのか。
しかしクナウエルは失敗した。ジンクレエルから何かを得ることを。性的な欲求に身を任せること=豚という激しい思い込みから解き放たれることを。彼は死ぬことも失敗する。ジンクレエルは何が何だかわからないままに夜中歩くと、そこにクナウエルがいたのでした。
かれは細い両腕で、けいれんでも起こしたように、ぼくを抱きかかえた。
「そう。夜中だ。もうじき朝になるにちがいない。おお、ジンクレエル、よくぼくを忘れずにいてくれたねえ。ぼくを許す気になってくれるかい。」
「許すって、何をさ。」
「ああ、ぼくはほんとうにいやなやつだったなあ。」
この時ようやく、ぼくらの対話のことが記憶に浮かんできた。あれは四、五日前のことだったろうか。あれいらい、一生涯がたってしまったように、ぼくは思った。しかしそのとき突然、すべてがわかってきた。ぼくらのあいだに起こったことだけでなく、なぜぼくがここへ来たか、そして何をクナウエルがこんな町はずれでしようとしたか、ということも。
「じゃ、きみは自殺しようと思ったんだね、クナウエル。」
かれは寒さと不安で、身をふるわせた。
「うん、そう思ったんだ。できたかどうか、それはわからないがね。ぼくは待とうと思っていた——朝になるまでね。」
ぼくはかれを、屋外へひっぱりだした。朝の最初の水平な光のしまが、言いようもなく冷たく、味気なく、灰色の大気の中で、微光をはなっていた。
ぼくはわずかな距離だけ、この少年の腕をとって、引き立てるようにした。ぼくの胸の中から、何かがこう言った。「これからきみ、うちへ帰るんだよ。そうして誰にもひとことも言うなよ。きみは間違った道を歩いていたんだ。間違った道をね。ぼくたちだって、きみが思っているような豚じゃないさ。ぼくたちは人間なんだ。ぼくたちは神々をつくって、神々と一緒にたたかうんだ。そうすれば神々はぼくたちを祝福してくれるさ。」
無言でふたりは歩きつづけて、やがて別れた。ぼくが帰宅したときには、もう明るくなっていた。 207ページ3行〜208ページ10行
以上のようなピストリウスとクナウエルとの関わりがあって、ジンクレエルは一つの認識に至ります。もちろん、その前のクロオマア、作品を通してデミアン、象徴としてのベアトリイチェとの出会いと関与があってこそなのですが。少し長いですが、ここがこの作品の核だと思われるので、書き写しておきます。
そしてこのとき突然、激しい焔のように、つぎの認識がぼくの身を焼いた——どんな人間にも、なにかの「任務」はあるが、自分でえらんだり、限定したり、勝手に管理したりしていいような任務は、誰のためにも存在してはいない。新しい神々を欲するのは、間違っている。世界に対して何物かを与えようとするのは、まったく間違っている。めざめた人間にとっては、自分自身を探すこと、自分の心を堅固にすること、自分自身の道を、それがどこへ通じていようとも、手さぐりで前進すること、それ以外に決して決して、なんの義務もありはしないのだ。——これがぼくを深くゆすぶった。そしてこれが、ぼくにとって、この体験の成果であった。ぼくはこれまで何度も、未来の映像をもてあそんだことがある。自分にふりあてられそうな役割を、夢想した。あるいは詩人として、または予言者として、または画家として、または何なりとしての役割である。そんなものはみんな無意味だ。ぼくが存在しているのは、詩を作るためでも、説教をするためでも、画をかくためでもない。ぼくにしろ、ほかの人間にしろ、そんなことのために、存在してはいないのだ。そんなことはみんな、ついでに生じてくるだけである。どんな人間にとっても、真の天職とはただひとつ、自己自身に到達することだ。かれが詩人としてまたは狂人として、予言者としてまたは犯罪者として、終わろうと構わない——それはかれの本領ではない。それどころか、そんなことは結局どうでもいいのである。かれの本領は、任意の運命をではなく、自己独得の運命を見出すこと、そしてそれを自分の中で、完全に徹底的に生きつくすことだ。それ以外のいっさいは、いいかげんなものであり、逃れようとする試みであり、大衆の理想の中へ逃げもどることであり、順応であり、自己の内心をおそれることである。おそるべき、神聖なすがたで、この新しい映像は、ぼくの目前にのぼってきた。いくたびとなく予感され、おそらくはたびたびすでに口にも出されながら、それでも今はじめて体験された映像なのである。ぼくは自然の手で投げ出された者だ。新にむかってか、あるいは無にむかってか、漠然たる境へ投げ出されたのであって、この投げた力を、深い深いところから思うさま作用させること、その意志を自分の中に感じること、そしてそれを自分の意志とすること、それだけが、ぼくの天職なのだ。それだけが。
多くの孤独を、ぼくはすでに味わってきた。今ぼくは、もっと深い孤独があること、そしてそれが逃れがたいものなのを、おぼろげに感じた。 219ページ5行〜220ページ16行
最後にもう一つだけ。
ジンクレエルはデミアンと再会し、デミアンの母であるエヴァ夫人とも知り合いになります。デミアンの家でのひとときは、ジンクレエルにとってしあわせな時間でした。が、戦争が始まり、ジンクレエルとデミアンは戦地へ。
ジンクレエルの戦争体験で得たことには希望があります。
そして世界がいよいよ頑なに、戦争と武勇、名誉、そのほかの古い理想を、めざしているかに見えれば見えるほど、外見的な人間らしさの声という声が、いよいよはるかに、いよいよ嘘らしくひびけばひびくほど、それらはすべて表面だけのことにすぎなかったし、それと同様、戦争の外面的な政治的な目標というものも、表面だけのものにとどまっていた。深いところには、何かが生じかけていたのである。何か新しい人間らしさといったようなものが。なぜならぼくは、多くの人たちを見ることができたが——しかもかれらの中には、ぼくのかたわらで死んで行った者も、ずいぶんある——かれらには、憎しみと憤怒、殺害と破壊というものが、対象物にむすびつけられてはいない、という洞見が、感情をとおしてさずけられていたのである。そうだ。対象物は、目標と同じく、まったく偶然的なものだった。原始的な感情は、どんなに荒々しいものでも、敵をめざしてはいなかった。その感情の血なまぐさいしわざは、内的なもの、自己分裂を起こしたたましいの、放射にすぎなかった。たましいは、新しく誕生するために、荒れ狂ったり、人を殺したり、破壊したり、死んだりしようとしていたわけである。巨鳥がむりに卵からぬけ出ようとしていた。そして卵は世界であった。そして世界はくずれ去るほかはなかったのである。 280ページ13行〜281ページ11行
負傷したジンクレエルとデミアンは、いっとき横に並ばされます。デミアンは、おそらく死んでしまう。またしても一人になってしまうであろうジンクレエルにデミアンは語りかけます。
「ジンクレエル。」とかれはささやき声で言った。
ぼくは目で合図をして、かれの言うことがわかると知らせた。
かれはまたほほえんだ——ほとんどあわれむかのように。
「おい、坊や。」とかれはほほえみながら言った。
かれの口は、このときぼくの口のすぐそばに来ていた。小声で、かれは話しつづけた。
「きみ、フランツ・クロオマアのことを、まだおぼえているかい。」とかれは聞いた。
ぼくはかれにまばたきをしてみせた。そして同じくほほえむことができた。
「ねえ。小さなジンクレエル、しっかり聞くんだよ。ぼくはいずれここを出てゆくことになる。きみはたぶん、いつかまた、ぼくを必要とすることがあるだろうね——クロオマアやなんかに対してさ。そうなってぼくを呼んでも、ぼくはもうそんな時、そう手がるに、馬にのったり、または汽車にのったりして、来はしないよ。そんな時はね、きみ自身の心に耳をかたむけなければいけない。そうすればぼくがきみの心の中にいるのに、気がつくよ。わかるかい。——それから、まだ言うことがある。エヴァ夫人が言ったんだが、きみがいつか困るようなことがあったら、そのときは、夫人からのキスを、ぼくがきみにしてあげるようにってさ。そのキスを、ぼくは夫人から渡されてきたんだよ……目をつぶりたまえ、ジンクレエル。」
ぼくはおとなしく目をとじた。かるい接吻をくちびるに感じた。そのくちびるには、たえずすこし血が出ていて、それがいっこうに減ろうとしないのだった。 284ページ13行〜285ページ14行
そして、作品の冒頭に掲げられた言葉。
ぼくはもとより、自分の中からひとりでにほとばしり出ようとするものだけを、生きようとしてみたにすぎない。どうしてそれが、こんなに難しかったのだろう。 7ページ1行〜3行
この作品が書かれたのは1919年、第一次世界大戦の直後のこと。
いまだに、どうして、自分が自分として生きることがこんなにも難しいままなのでしょう?
一つ一つ、書かれていくしかないのかなと思います。地道に、コツコツと。
その仕事が、年を経てもこうして文庫本として残り、次の世代のヒントとなって生きている。
読んでよかった。本当に。
また読みたくなるのでしょうか?
読みたくなったら何度でも、読めばいい。それだけ価値がある本です。
ヘルマン・ヘッセ 作/実吉捷郎 訳/岩波文庫/1954