12月に入り、今年も雪の季節がやってきました。
毎年「雪が少ない年でありますように」と願っています。
冬は、乾燥の季節。
市内の小学校や中学校でも、インフルエンザに罹患している生徒が増えてきているようです。
乾燥と言えばもう一つ、火事!
4,5日前も会社の近くで火事がありました。
3か月ほど前には、自宅の近所でも家の小屋が火事になり、すごい数の消防車が来て消火活動をしたのを目の当たりにし、恐ろしい思いをしました。
世界遺産首里城の火事は日本中が驚きました。
首里城の火災は午前2時半ごろに発生。
熱を感知するセンサーが反応し、警備員が駆け付けたところ煙が充満していたそうです。
乾燥する季節! 自分の家は大丈夫と思わず、対策をとっておきましょう。
対策の一つとして、火災警報器の点検をしてみました。

取扱説明書は取ってあるものの、「読んだことがない」という人が多いのではないかと思います。
今回、皆様に変わって隅から隅まで熟読してみました。

火災警報器は
新築住宅は平成18年6月1日から、
既存の住宅も、平成20年5月31日までに設置が義務付けられました。

義務付けられてから10年以上経つのですが、点検はしていますか?

実は私、点検したことがありませんでした!
取扱説明書には「6か月に1回以上定期点検を行ってください」と書かれてあります。
ということで、早速点検!
まずは、ほこりがついていないか確認

警報停止ボタンを押すか

ひもを引く

赤いランプが点滅し「正常です」と言ったら大丈夫です。これで点検完了

 「電池切れです」「故障です」または音が鳴らない場合は取り換えが必要かもしれません。
「電池切れです」「故障です」または音が鳴らない場合は取り換えが必要かもしれません。
弊社で寝室や階段に取り付けている警報器は、けむりを検知するタイプで電池式のものです。
これは電池の寿命が10年で、かつ本体寿命も10年。電池切れになった警報器は、設置時期を確認して本体の交換が必要になります。
つまり
設置後10年経って電池切れの合図→機器ごと交換
設置後10年経過していないのに電池切れの合図→電池交換
ということです。
 注意
注意
ご年配の方は、いすや脚立に上がっての作業になるため、無理せず、ご連絡ください。
このような時にこそ、長身の社長がお助けに参ります。また、弊社のユーザー様の中には、
2階の寝室が勾配天井になっていて、高いところに設置されているため届かない場合があります。
そのような時もご連絡いただければ、 こちらの長身お助けマンが参上いたします。
こちらの長身お助けマンが参上いたします。















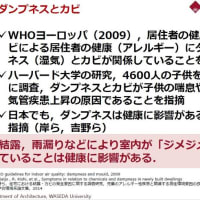
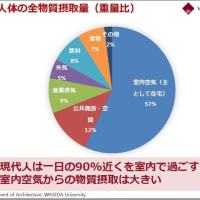
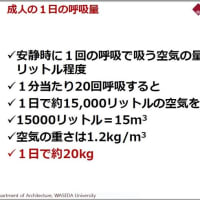



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます