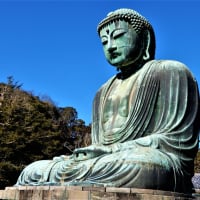満開に咲き誇る桜よりほろほろと散って花筏となって流れていく桜の方が好きだ。特に川崎市の二ヶ領用水がいい。
選挙と買い出しに出たついでに二ヶ領用水久地円筒分水へ。
東急田園都市線溝の口駅西口に出ればデープな溝の口。

 てきとーに大石橋を目指す。
てきとーに大石橋を目指す。 大石橋は、大山街道とニヶ領用水が交差するところに架かる橋。
大石橋は、大山街道とニヶ領用水が交差するところに架かる橋。

 江戸時代は秦野の煙草や厚木の麦などを扱った名主の丸屋・七右衛門の広大な屋敷があって大石橋は文字通りの大きな石橋だったようだ。
江戸時代は秦野の煙草や厚木の麦などを扱った名主の丸屋・七右衛門の広大な屋敷があって大石橋は文字通りの大きな石橋だったようだ。今では小石橋かな。

大石橋からニヶ領用水沿いに久地円筒分水へと歩く。





歩道橋で246を渡る。


あの桜綺麗だなぁ。
 ほどなく久地円筒分水。
ほどなく久地円筒分水。

この円筒分水ができたのは昭和16年。
サイフォンの原理を応用して、新平瀬川の下をくぐり再び吹き上がってきた水を、円筒の切り口の大きさで四つに分ける施設。
設計は神奈川県多摩川右岸農業水利改良事務所長だった平賀栄治。
国登録有形文化財。2012年土木学会選奨土木遺産。



 二ヶ領用水は多摩川の二か所から取水され久地で合流し田中休愚設計の久地分量樋へと導かれ、久地分量樋から久地二子堀・六ヶ村堀・川崎堀・根方堀に分けられた。
二ヶ領用水は多摩川の二か所から取水され久地で合流し田中休愚設計の久地分量樋へと導かれ、久地分量樋から久地二子堀・六ヶ村堀・川崎堀・根方堀に分けられた。が、江戸時代最先端技術だったとはいえこの方法では正確な分水ができずに、水量の分配をめぐっての紛争は江戸時代から昭和初期まで続いたのだった。
今の円筒分水が出来てからは紛争もなくなり、このモデルは今でも全国約30か所の農業用水に使用されてる。
 このあたりの農業はすっかり衰退したけど多摩川からの水は今でも流れてくる。
このあたりの農業はすっかり衰退したけど多摩川からの水は今でも流れてくる。
 久地神社さま。
久地神社さま。
裏手には地元の方々にお伺いしてもご存知の方に当たったことのない謎の水神さま。

 ここからの二ヶ領用水は散策にはいまひとつになる。
ここからの二ヶ領用水は散策にはいまひとつになる。花筏流れる桜の名所の二ヶ領用水は東名高速の下をくぐったところから始まり、多摩川の宿河原取入れ口へと続く。






花筏はこれからの桜満開の二ヶ領用水を引き返してJR宿河原駅へ。