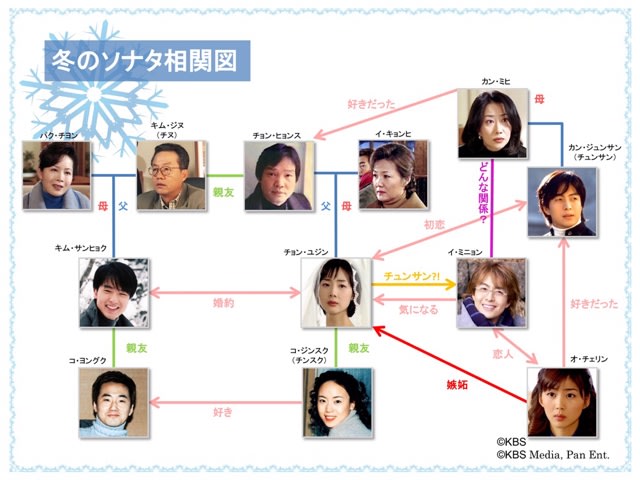
その夜、一人でバーで飲んだくれるチェリンを心配して、チンスクとヨングクが駆け付けた。
「何よ、あんたたち。どうせもう病院には行ったんでしょう?ユジンどうだった?記憶が戻ったって大喜びしてた?」

「チェリン、わたしたち病院にはまだ行ってないの。ユジンはあなたとサンヒョクには申し訳なくて言えないのよ。ユジンはそんな子じゃないし」
「はいはい、そうよね。天使のユジンだもの。」
「俺たち、お前が心配なんだよ。」
「私が心配?死ぬとでも思った?大丈夫よ。チュンサンとユジンがどれだけ幸せになれるか見届けてやるんだから。」

チェリンはそういうと、静かに涙を流しながら水割りを飲み干した。チンスクとヨングクは、いつもの勝ち気で自信満々のチェリンらしからぬ態度に驚いて、顔を見合わせてしまった。
「みんなミニョンさんを忘れちゃったの?チュンサンばかりを求めて。ミニョンさんを、ミニョンさんを返して。ミニョンさんを返して、、、。」そういうと、チェリンはテーブルに突っ伏して泣き始めた。チェリンにとっては、一度は相思相愛になったミニョンがチュンサンにとって変わられるのが、辛くてたまらないのだろう。チンスクとヨングクの二人も、そんなチェリンが気の毒すぎて、何も言えないまま静かに座り続けるしかないのだった。
サンヒョクはユジンのアパート前で車を止めて、ユジンを待っていた。ユジンは見違えるように明るい表情で電話をしながら出てきた。相手はチュンサンらしい。しかし、サンヒョクの顔を見ると、一瞬で表情がなくなった。二人は近くのカフェで静かに向き合った。

サンヒョクの顔は憔悴しきっており、青白く、無精ひげが生えていた。よれよれの襟のコートを羽織り、視線はあらぬ方を見ていた。ユジンはそんなサンヒョクを心配そうに見つめた。サンヒョクは静かにユジンに視線を合わせると話し始めた。
「ユジン、チュンサンの記憶が戻ったんだって。良かったね。」
「うん、完全ではないんだけど、あなたのことも覚えてるって。」
「、、、そうか。悪い記憶だろうけどな。」
「彼に会ってみる?」
「、、、どうかな。また今度にするよ。」
「わかったわ」
「ユジン、僕は君に彼がチュンサンだと隠していたことを後悔してないよ。また同じ状況になっても、同じことをする。だって、君に絶対知られたくなかったんだ。君を失いたくなかった。だって、君は僕にとっても初恋の人だから。」

「、、、サンヒョク」
「君を、、、君を彼のもとに行かせてあげる。チュンサンを2度も失わせられないから」
「サンヒョク、わたしきっと罰が当たるわ。あなたを傷つけて罰が当たる。」
「ユジン、そんなこと言うな。僕なら大丈夫だ。そんなこと言われたら辛くなるから、、、どうか泣かないで。辛くて耐えられなくなる。変だよなぁ。チュンサンは君との記憶を取り戻したくて必死なのに、僕は君との記憶を消す努力をしなくちゃならない。ああ、耐えられるかな、、、忘れられるかな、、、。ユジン、頼む、僕が夜電話をしても決して取らないで。僕が君を訪ねて助けてと言っても、受け入れたらだめだよ。優しく笑いかけないで。そんなふうに泣かないで。ごめんね、、、。本当にごめんね。これで君を泣かせるのは最後だから。君のそばにずっといると約束したのに、守れなくてごめんね。」そういうと、サンヒョクは静かに席を立って出ていくのだった。ユジンはそんなサンヒョクを泣きながら見送った。
いつも優しくて味方だったサンヒョク。みんなが責めてもわたしを庇ってくれた。

ずっと一途に思ってくれたサンヒョク。10年以上、そばにいて励ましてくれてありがとう。

つらいときに寄り添ってくれたサンヒョク。チュンサンの幻を見て落ち込むわたしを、必死で励ましてくれた。今思うと、わたし以上に揺れるわたしの側で、つらくて悲しかっただろうに。

謝らなければならないのは自分なのに、最後まで自分を責めなかったサンヒョク。
サンヒョク、今までありがとう、本当にごめんなさい、そしてさようなら。
サンヒョクは、ユジンと別れたあとも、涙を流しながら歩き続けた。この10年間、いや生まれてからほぼ一緒だった28年間は最高の日々だった。
高校時代、いつも二人で走ってやっと乗ることができたバス。君はいつも寝坊ばかりして、僕をハラハラさせたね。

合宿でやったゲームで大笑いしていたユジン。あのときはチュンサンとケンカして落ち込んでいて、見てられなかったから、ゲームの間だけでも、笑う君でいてくれて、嬉しかったよ。

一緒に担当した昼休みの校内放送。まるで二人だけの秘密を共有したみたいで、ワクワクしたなぁ。

帰り道はいつも一緒だった。きみの隣はいつだって僕だったのに。二人でよくトッポッキやホットックを食べたね。

そして婚約指輪を渡した夜。きみの眩しそうな恥ずかしそうな顔が忘れられない。

出来なかったキス。君はいつもキスしようとすると、はぐらかしたね。

握りしめた手。温かい君の手をずっと繋いでいたかった。婚約式をやり直した日のことは死ぬまで忘れないよ。

笑いあった日々。いつもたわいないことで、沢山笑ってくれたね。その笑顔を見るだけで幸せだったのに。

辛いこともあったけれど、すべてをひっくるめて思い出がいとおしくてならなかった。あとどれぐらいたてば、彼女を忘れられるのだろうか。本当に忘れられるのだろうか。サンヒョクは波間を漂う小舟のように当てもなくさまよい続けた。
さようなら、ユジン。
僕の思い出にはいつも君がいた。
さようなら。僕の初恋。
























