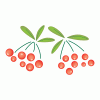テレビで宝塚歌劇の公演が、よく放送されている。私は宝塚ファンではないが、テレビ番組表で、知らない演目と知らない主演トップスターの名前を見ても、時々、録画しておく。最初だけ見て消去することが多いが、3本に1本ぐらいは最後まで観る。最近、観たのは、『星組公演 ハプスブルクの宝剣 -魂に宿る光-』(2010年1月29日 宝塚大劇場)(NHK BS)。主演は柚希礼音と夢咲ねね。原作は藤本ひとみ。脚本と演出は植田景子。主題歌はシルヴェスター・リーヴァイ。
18世紀のヨーロッパが舞台で、野心に燃えるユダヤ人美青年の、波乱に満ちた生涯が描かれる。男役トップスターの柚希礼音が、わりと素敵だった。叙情的でロマンティックな音楽も美しかった。衣装も髪型(カツラだが)も良かった。ユダヤ人美青年と王妃テレーゼのせつない感情が、よく伝わってきた。
私にとって、宝塚歌劇の魅力は、男役である。宝塚女優が男を演じて歌うのを観ることに、ワクワクするような期待と、ときめきを感じる。もしかしたら、少女マンガの世界が原点かもしれないと思ったりする。少女時代に夢中になって読んだマンガに描かれた、美しい貴公子、甘い顔立ちのりりしいプリンス、現実離れした夢の世界の王子様──が登場する世界に浸った時の楽しさや胸のときめきや感動に、通じるものがあるような気がする。王子様というのは、私にとっての抽象的な意味である。その少女マンガ世界と違って、歌と踊りの舞台が華麗に繰り広げられる宝塚歌劇は、紙に描かれた夢の世界の王子様より、当然、はるかにリアルでインパクトも迫力もある。
数年前、テレビで、宝塚女優たちのトーク番組を見た時、男役の歩き方の訓練についての話が興味深かった。男性と女性は歩き方が違う。肉体の違いによる、歩き方の相違、というような話をしていて、その訓練法に感心させられた。舞台上を歩く男役トップスターを見ると、そのことが頭をかすめたりする。男性独特の歩き方、しかも男性ではなく女性が歩く男性の歩き方、しかも美しくて魅力的でセクシーな歩き方と、りりしくも美しい立ち姿を見ると、もう、うっとりさせられるような気分になる。初めてテレビで宝塚公演を観た『ベルサイユのばら アンドレとオスカル編』(1989年・雪組公演)』のアンドレ役の杜けあきは、私が観た中で最も魅力的な、男性の歩き方と舞台上の立ち姿と、歌と演技で酔わせてくれた男役トップスターだった。
もちろん歩き方ばかり見ているわけではない。歌も、表情を含めた演技も、魅せられるのは、やはり男役である。テレビで宝塚歌劇を、多く観ているわけではないが、同じようなメイク、同じような声や歌い方になりがちな中で、魅力的な男役トップスターは、独特の美しい個性がにじみ出ているように感じられる。声量があればいいというものではなく、艶やかさと気品と豊かな感情表現が伝わってくる男役は素敵である。
今年は、テレビで、もう1本観た。演目は『炎にくちづけを -「イル・トロヴァトーレ」より-』で、2005年の宙組公演。(『宝塚ドリーミング・シアター』・TwellV)。原作はヴェルディのオペラ『イル・トロヴァトーレ』。脚本と演出は木村信司。作曲は甲斐正人。主演は和央ようか、花總まり。
原作がオペラの『イル・トロヴァトーレ』だったので、観たのだが、
(う~ん、何か、私のイメージと違うみたい)
という感じで、最後まで、のめり込めなかった。イメージが違うというのは、私が抱く『イル・トロヴァトーレ』という作品に対してであり、歌とオーケストラの演奏に対してで、出演者たちの演技については、よく、わからないけれど。当然、オペラと宝塚歌劇は違う。同じ演目でも、オペラとミュージカルの違いということだと思うが、やはりオペラの『イル・トロヴァトーレ』のほうが私の感性には合うと、あらためて思った。
『イル・トロヴァトーレ』は、ヴェルディの美しい旋律にも酔わされるが、三角関係の男女の愛と嫉妬、母と息子の愛、長年の憎しみと復讐心──それらが描かれるドラマティックなストーリー。タイトルのトロヴァトーレは吟遊詩人の意味だが、騎士の姿の登場で、名前はマンリーコ。15世紀、スペインのある地方の城が舞台。ジプシー(ロマ)が出てくる話を私は好きなのだが、母を火あぶり処刑されたアズチェーナというロマ女性は、死を前にした母に復讐を誓って、伯爵の弟である赤子をさらい、火に投げ入れたが、実は自分の赤子だった、という怖くなるような話。復讐心を秘めながら、その赤子を育てて、母と息子の愛の生活が続く。成長したマンリーコは公爵夫人の女官レオノーラと愛し合うように。レオノーラはルーナ伯爵から想いを寄せられていて、ラブ・ロマンスと男2人の嫉妬が描かれる三角関係。というようなストーリーで、最後は嫉妬と怒りからの伯爵の命令で、マンリーコは火刑に処せられ、それを見たアズチェーナが「あれこそ、お前の探していた弟だ! 母さん、復讐を果たしました!」と、両手を広げ天に向かって叫ぶドラマティックな幕切れ。
『イル・トロヴァトーレ』を初めて観たのは、新国立劇場の5階にあるビデオ・ブースでだった。午前10時発売の当日券を、早起きして2時間前から並んだのに買えなくて、ショックと落ち込んだ気分の中、オペラシティで早めの昼食のスパゲティを食べながら、
(そうだわ、ビデオ見て帰ろうっと)
と思いつき、5階の情報センターのビデオ・ブースで、午前11時ごろから『チェネレントラ』と『トスカ』と『イル・トロヴァトーレ』をたて続けに観て、午後6時の情報センター閉館時刻に帰りながら、
(オペラって、何て素晴らしいのかしら)
と、胸が熱く満たされた思いだった。テレビ画面の半分ぐらいのビデオ画面で、ヘッドホンで聴いたのに、予想外に楽しめて、当日券を買えなかったショックと落ち込んだ気分は、すっかり消えてしまった。
その後、『イル・トロヴァトーレ』をテレビで観て、DVDで観て、ようやく今年の10月に、新国立劇場の公演を生で観た。100%の満足とは言えなかったし、主要人物のマンリーコとレオノーラとルーナ伯爵とアズチェーナの4人共に素晴らしかったら、もっと感動的で酔わされたかもしれなかったけれど、好きなアリアがあるヴェルディの美しい旋律を、生で聴いた感動の余韻はあった。
また、昨年、テレビで観た宝塚歌劇で一番印象的なのは、『再会』(1999年・雪組公演)(宝塚ドリーミング・シアター)。主演に轟悠の名前があって観たのだが、モナコが舞台のラブ・ロマンスで、予想以上に楽しめた。
最近はトップスターの退団の時期が早くて、映画やテレビでの活躍を目指すスターが多いと聞いたことがある。轟悠は、そうではないと知った。轟悠の名前は、私が初めてテレビで観た宝塚歌劇『ベルサイユのばら』(雪組公演・1989年)で、衛兵アラン役で記憶があった。『wikipedia』によると、元雪組トップスター、専科に所属する男役スター、と書いてある。専科とは特定の組に所属しない団員のことらしい。昨年観た『再会』の轟悠は、モナコの一流ホテルの御曹司で、売れない小説家役だったが、とても魅力的だった。
『YouTube』でオペラのアリアをいろいろ聴いていると、あっという間に時間が経ってしまうが、宝塚歌劇は、歌を知っている『ベルサイユのばら』を時々。

18世紀のヨーロッパが舞台で、野心に燃えるユダヤ人美青年の、波乱に満ちた生涯が描かれる。男役トップスターの柚希礼音が、わりと素敵だった。叙情的でロマンティックな音楽も美しかった。衣装も髪型(カツラだが)も良かった。ユダヤ人美青年と王妃テレーゼのせつない感情が、よく伝わってきた。
私にとって、宝塚歌劇の魅力は、男役である。宝塚女優が男を演じて歌うのを観ることに、ワクワクするような期待と、ときめきを感じる。もしかしたら、少女マンガの世界が原点かもしれないと思ったりする。少女時代に夢中になって読んだマンガに描かれた、美しい貴公子、甘い顔立ちのりりしいプリンス、現実離れした夢の世界の王子様──が登場する世界に浸った時の楽しさや胸のときめきや感動に、通じるものがあるような気がする。王子様というのは、私にとっての抽象的な意味である。その少女マンガ世界と違って、歌と踊りの舞台が華麗に繰り広げられる宝塚歌劇は、紙に描かれた夢の世界の王子様より、当然、はるかにリアルでインパクトも迫力もある。
数年前、テレビで、宝塚女優たちのトーク番組を見た時、男役の歩き方の訓練についての話が興味深かった。男性と女性は歩き方が違う。肉体の違いによる、歩き方の相違、というような話をしていて、その訓練法に感心させられた。舞台上を歩く男役トップスターを見ると、そのことが頭をかすめたりする。男性独特の歩き方、しかも男性ではなく女性が歩く男性の歩き方、しかも美しくて魅力的でセクシーな歩き方と、りりしくも美しい立ち姿を見ると、もう、うっとりさせられるような気分になる。初めてテレビで宝塚公演を観た『ベルサイユのばら アンドレとオスカル編』(1989年・雪組公演)』のアンドレ役の杜けあきは、私が観た中で最も魅力的な、男性の歩き方と舞台上の立ち姿と、歌と演技で酔わせてくれた男役トップスターだった。
もちろん歩き方ばかり見ているわけではない。歌も、表情を含めた演技も、魅せられるのは、やはり男役である。テレビで宝塚歌劇を、多く観ているわけではないが、同じようなメイク、同じような声や歌い方になりがちな中で、魅力的な男役トップスターは、独特の美しい個性がにじみ出ているように感じられる。声量があればいいというものではなく、艶やかさと気品と豊かな感情表現が伝わってくる男役は素敵である。
今年は、テレビで、もう1本観た。演目は『炎にくちづけを -「イル・トロヴァトーレ」より-』で、2005年の宙組公演。(『宝塚ドリーミング・シアター』・TwellV)。原作はヴェルディのオペラ『イル・トロヴァトーレ』。脚本と演出は木村信司。作曲は甲斐正人。主演は和央ようか、花總まり。
原作がオペラの『イル・トロヴァトーレ』だったので、観たのだが、
(う~ん、何か、私のイメージと違うみたい)
という感じで、最後まで、のめり込めなかった。イメージが違うというのは、私が抱く『イル・トロヴァトーレ』という作品に対してであり、歌とオーケストラの演奏に対してで、出演者たちの演技については、よく、わからないけれど。当然、オペラと宝塚歌劇は違う。同じ演目でも、オペラとミュージカルの違いということだと思うが、やはりオペラの『イル・トロヴァトーレ』のほうが私の感性には合うと、あらためて思った。
『イル・トロヴァトーレ』は、ヴェルディの美しい旋律にも酔わされるが、三角関係の男女の愛と嫉妬、母と息子の愛、長年の憎しみと復讐心──それらが描かれるドラマティックなストーリー。タイトルのトロヴァトーレは吟遊詩人の意味だが、騎士の姿の登場で、名前はマンリーコ。15世紀、スペインのある地方の城が舞台。ジプシー(ロマ)が出てくる話を私は好きなのだが、母を火あぶり処刑されたアズチェーナというロマ女性は、死を前にした母に復讐を誓って、伯爵の弟である赤子をさらい、火に投げ入れたが、実は自分の赤子だった、という怖くなるような話。復讐心を秘めながら、その赤子を育てて、母と息子の愛の生活が続く。成長したマンリーコは公爵夫人の女官レオノーラと愛し合うように。レオノーラはルーナ伯爵から想いを寄せられていて、ラブ・ロマンスと男2人の嫉妬が描かれる三角関係。というようなストーリーで、最後は嫉妬と怒りからの伯爵の命令で、マンリーコは火刑に処せられ、それを見たアズチェーナが「あれこそ、お前の探していた弟だ! 母さん、復讐を果たしました!」と、両手を広げ天に向かって叫ぶドラマティックな幕切れ。
『イル・トロヴァトーレ』を初めて観たのは、新国立劇場の5階にあるビデオ・ブースでだった。午前10時発売の当日券を、早起きして2時間前から並んだのに買えなくて、ショックと落ち込んだ気分の中、オペラシティで早めの昼食のスパゲティを食べながら、
(そうだわ、ビデオ見て帰ろうっと)
と思いつき、5階の情報センターのビデオ・ブースで、午前11時ごろから『チェネレントラ』と『トスカ』と『イル・トロヴァトーレ』をたて続けに観て、午後6時の情報センター閉館時刻に帰りながら、
(オペラって、何て素晴らしいのかしら)
と、胸が熱く満たされた思いだった。テレビ画面の半分ぐらいのビデオ画面で、ヘッドホンで聴いたのに、予想外に楽しめて、当日券を買えなかったショックと落ち込んだ気分は、すっかり消えてしまった。
その後、『イル・トロヴァトーレ』をテレビで観て、DVDで観て、ようやく今年の10月に、新国立劇場の公演を生で観た。100%の満足とは言えなかったし、主要人物のマンリーコとレオノーラとルーナ伯爵とアズチェーナの4人共に素晴らしかったら、もっと感動的で酔わされたかもしれなかったけれど、好きなアリアがあるヴェルディの美しい旋律を、生で聴いた感動の余韻はあった。
また、昨年、テレビで観た宝塚歌劇で一番印象的なのは、『再会』(1999年・雪組公演)(宝塚ドリーミング・シアター)。主演に轟悠の名前があって観たのだが、モナコが舞台のラブ・ロマンスで、予想以上に楽しめた。
最近はトップスターの退団の時期が早くて、映画やテレビでの活躍を目指すスターが多いと聞いたことがある。轟悠は、そうではないと知った。轟悠の名前は、私が初めてテレビで観た宝塚歌劇『ベルサイユのばら』(雪組公演・1989年)で、衛兵アラン役で記憶があった。『wikipedia』によると、元雪組トップスター、専科に所属する男役スター、と書いてある。専科とは特定の組に所属しない団員のことらしい。昨年観た『再会』の轟悠は、モナコの一流ホテルの御曹司で、売れない小説家役だったが、とても魅力的だった。
『YouTube』でオペラのアリアをいろいろ聴いていると、あっという間に時間が経ってしまうが、宝塚歌劇は、歌を知っている『ベルサイユのばら』を時々。