他校から移動してきた40歳台の新しい男性教諭は、新しい学校と生徒たちに慣れるのに、いっぱいいっぱいの感じだった。
つい前年度の先生と比較してしまいがちで、前の先生は、優しさの中に軍隊のような規律を子供たちに規していたので、時間管理や言葉の使い方に厳しさがあった。
今回の新任先生は、優しさと子供との視線を合わせたコミュニケーションに力を入れているようで、時間もゆるく子供たちもダラダラしているように見えた。
授業参観が終わっても、懇談会の準備も声かけもしようとしない先生に対して、私はしびれを切らして、「懇談会の準備を始めてもよろしいでしょうかね?」と机を移動しながら声をかけた。
集まってくださったお母さんに5ヶ月の赤ちゃんを抱っこした方もいらして、早く始めて早く終わらせたかったからだ。
私の一声で、少々腰が引けた先生の様子を見ながら、懇談会がスタートした。
新任先生は、やはり、この春の移動に関して、すぐに新しい学校に慣れてがんばろうという強い意欲が感じられなかったが、それでも、時間が経てば慣れて自分らしい授業や学校生活が送れるような、少々マイペースさが見えて、それはそれで良いのかもという気持ちになれる先生だった。
子供たちもお母様たちにも一番の関心は、宿題の件だった。
今回の先生は、「宿題は、学校の授業で出来なかったら渡すだけで、学校で終わらせられるものは、宿題無し」と子供たちに宣言し、新学期が始まって2週間は、多くの子供たちは宿題が無い。
ただし、授業で課題を終えることができなかった子は、宿題となってやっているようだ。よって、その子供たちに標準を合わせて、宿題を考えているようだ。
子供たちは、2年生、3年生の時の毎日の宿題で、学校から帰って遊びに行く前にほんの10分で終えるプリントでも宿題をする、というリズム、習慣ができていたので、新学期から拍子抜けしていた。
うちの息子は、物足りなさで先生に意見をしに行ったようだ。
お母様方も、宿題が無いと、子供たちの学力低下の不安を持たれた方が多くて、新任の先生への不満の芽が出ているようだった。
そこで、なぜ宿題を出さない主義なのかの理由を聴いて、そして子供たち、父兄の思いを先生にお伝えした。
「2年生、3年生でやっと身につけた、毎日宿題をし続けるという習慣、そしてやり続ける達成感の芽を考え欲しい」と。
先生は、
「今は新しい子供たちの様子を見ていて、どのようにやっていくかを考えていますので、決して今後も宿題を出さないと決めたわけではない」と話してくださった。
ここでようやくチャイムが鳴って、父兄も先生も納得したようだ。
ここでお母様にも先生にも私が理解していただきたかったのは、お母様方が先生とのわだかまりをもたずに意見を伝え合い、子供たちの可能性を向上させるために心を開示しあうことが必要だという点だった。
先生は、お母様パワーに敏感だ。
影でいろいろ言われるとストレスとなる。
お互い、子供たちのことを思って協力体制でいくことが一番だ。
そうやっていくことが、未来の社会を創っていくのだと思いたい。
感謝
つい前年度の先生と比較してしまいがちで、前の先生は、優しさの中に軍隊のような規律を子供たちに規していたので、時間管理や言葉の使い方に厳しさがあった。
今回の新任先生は、優しさと子供との視線を合わせたコミュニケーションに力を入れているようで、時間もゆるく子供たちもダラダラしているように見えた。
授業参観が終わっても、懇談会の準備も声かけもしようとしない先生に対して、私はしびれを切らして、「懇談会の準備を始めてもよろしいでしょうかね?」と机を移動しながら声をかけた。
集まってくださったお母さんに5ヶ月の赤ちゃんを抱っこした方もいらして、早く始めて早く終わらせたかったからだ。
私の一声で、少々腰が引けた先生の様子を見ながら、懇談会がスタートした。
新任先生は、やはり、この春の移動に関して、すぐに新しい学校に慣れてがんばろうという強い意欲が感じられなかったが、それでも、時間が経てば慣れて自分らしい授業や学校生活が送れるような、少々マイペースさが見えて、それはそれで良いのかもという気持ちになれる先生だった。
子供たちもお母様たちにも一番の関心は、宿題の件だった。
今回の先生は、「宿題は、学校の授業で出来なかったら渡すだけで、学校で終わらせられるものは、宿題無し」と子供たちに宣言し、新学期が始まって2週間は、多くの子供たちは宿題が無い。
ただし、授業で課題を終えることができなかった子は、宿題となってやっているようだ。よって、その子供たちに標準を合わせて、宿題を考えているようだ。
子供たちは、2年生、3年生の時の毎日の宿題で、学校から帰って遊びに行く前にほんの10分で終えるプリントでも宿題をする、というリズム、習慣ができていたので、新学期から拍子抜けしていた。
うちの息子は、物足りなさで先生に意見をしに行ったようだ。
お母様方も、宿題が無いと、子供たちの学力低下の不安を持たれた方が多くて、新任の先生への不満の芽が出ているようだった。
そこで、なぜ宿題を出さない主義なのかの理由を聴いて、そして子供たち、父兄の思いを先生にお伝えした。
「2年生、3年生でやっと身につけた、毎日宿題をし続けるという習慣、そしてやり続ける達成感の芽を考え欲しい」と。
先生は、
「今は新しい子供たちの様子を見ていて、どのようにやっていくかを考えていますので、決して今後も宿題を出さないと決めたわけではない」と話してくださった。
ここでようやくチャイムが鳴って、父兄も先生も納得したようだ。
ここでお母様にも先生にも私が理解していただきたかったのは、お母様方が先生とのわだかまりをもたずに意見を伝え合い、子供たちの可能性を向上させるために心を開示しあうことが必要だという点だった。
先生は、お母様パワーに敏感だ。
影でいろいろ言われるとストレスとなる。
お互い、子供たちのことを思って協力体制でいくことが一番だ。
そうやっていくことが、未来の社会を創っていくのだと思いたい。
感謝










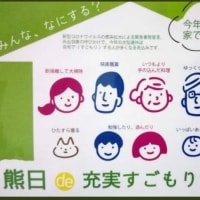









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます