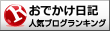今日は朝から全国的に雪模様です。休みで外出を計画されていた方には残念な週末になりそうです。さて、最近は江戸時代の旧街道に興味があり、特に三国街道はきちんと訪ねたことがなかったので、群馬県内の旧宿場町をいくつか回ってきました。本来は、きちんと自分の足で踏破すべきですが、車を利用し駆け足で行ってきました。もう少し余裕ができたら群馬県内だけでなく、全国の各街道を巡りたいと思います。さて、三国街道は、中山道の高崎宿から群馬県のほぼ中央を南から北へ貫き、三国峠を越えて新潟県の寺泊へ至る街道です。長岡藩などの参勤交代で利用されただけでなく佐渡金山から江戸まで金を運ぶ街道として江戸幕府からも重要視されました。群馬県内には金古宿、渋川宿、金井宿、北牧宿、横堀宿、中山宿、塚原宿、下新田宿、布施宿、今宿、須川宿、相俣宿、猿ヶ京宿、吹路宿、永井宿の15宿がありました。今回まず訪ねたのは、金井宿と北牧宿の間にある杢ヶ橋関所です。ここは吾妻川右岸にあり当時の上州(群馬)では重要な場所でした。江戸幕府は、江戸方面への鉄砲の持ち込みや、人質として江戸にいる各大名の正室が逃げないように、関所を各地において「入り鉄砲に出女」を厳しく取り締まりました。現在でも関守の子孫である田中家の役宅が現存しており、当時の面影を伝えています。このあと、吾妻川の渡しを渡った対岸の北牧宿に行きました。ここは、越後から来た人でにぎわい、8軒の旅籠を含め160余軒の家屋が軒を連ねていました。当時の水路も復元されわずかながら当時の町並みをとどめています。この北牧宿から北に上ると興福寺があります。ここの入り口には、振貸感恩碑(しんたいかんおんひ)があります。これは、天明3年(1783年)の浅間山の大噴火による吾妻川の氾濫で大きな被害が出た北牧宿の悲惨さと復興に尽力した代官への感謝をわすれないように村人を戒めたものだそうです。このように地域に残された文化財は1つ1つに理由や経緯があるということが改めて感じます。当時の人々の生活、文化、思いが分かる文化財は後生の人々にとっても必ず教訓やヒントを与えてくれると思います。
杢ヶ橋関所跡、現在も関守の子孫の方が住んでいます。
杢ヶ橋関所と北牧宿の間を流れる吾妻川。1783年、上流にある浅間山の噴火の際は氾濫し、多くの被害をもたらしました。
北牧宿の町並み。この宿は、芝宿・古宿・新田宿・中宿・道場宿に分かれ多くの旅人でにぎわいました。
興福寺の振貸感恩碑(しんたいかんおんひ)