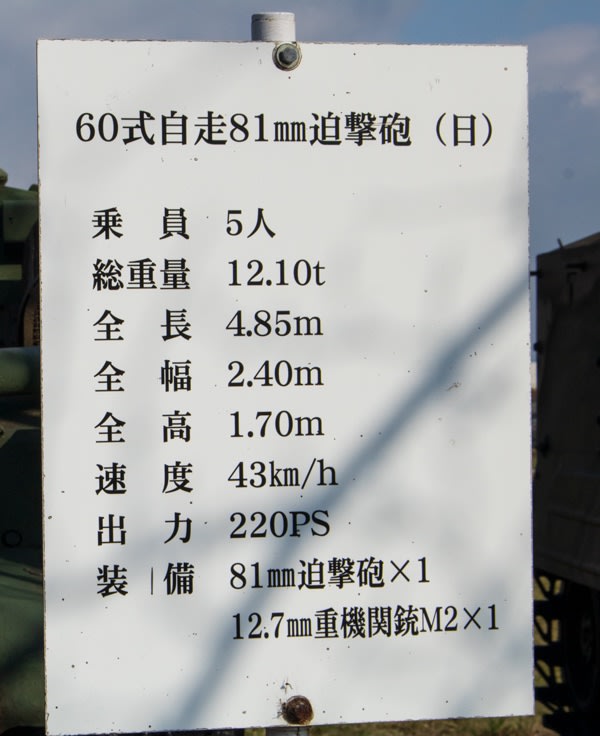さて〜〜ようやく戦車の出番でございます〜〜〜
まずは74式戦車から〜
74式戦車
74式戦車(ななよんしきせんしゃ)は、陸上自衛隊が61式戦車の後継として開発、
配備された国産二代目の主力戦車である。部隊内での愛称は「ナナヨン」。
第2.5世代主力戦車に分類される戦車。三菱重工業が開発を担当した。
105mmライフル砲を装備し、
油気圧サスペンションにより
車体を前後左右に傾ける姿勢制御機能を備え、←これはほんとにすごい!と思う
射撃管制装置にレーザー測距儀や弾道計算コンピューターを搭載するなど、
61式の開発された時点では実現できなかった内部機器の電子化も行われている。
軽量化のため内部容積を減らして小型化している。
配備開始から装甲増加などの大幅な改修は行われていないが、
新たな砲弾への対応能力が付与され戦闘力を向上させている。
後継車輌として第3世代主力戦車である90式戦車が開発・生産されたが、
こちらは北部方面隊以外では富士教導団など教育部隊にしか配備されていないため、
全国的に配備された74式が数の上では主力であった。
それでも年40輌程度の早さで退役が進んでおり、
74式の更新をも考慮した10式戦車の採用や、
同じ口径の砲をもつ16式機動戦闘車の採用など代替がすすんでいる。




続きまして90式戦車
ごろんたは74式にハマる前は90式の大ファンでした。
が、しかし〜〜イベントでもあまり登場してくれず
よく目にする74式にいつしか心を奪われた次第。
さらには、10式の登場が結構衝撃的であり、90式のことを
忘れていた時期もございます…90式、本当にすまない。
さて、それではその90式とはどんな戦車か?
90式戦車
90式戦車(きゅうまるしきせんしゃ)は、
日本の戦車。第二次世界大戦後に日本国内で開発生産された
自衛隊の主力戦車としては61式戦車、74式戦車に続く三代目にあたり、
第3世代主力戦車に分類される。
着上陸侵攻してくるソ連軍の機甲部隊に対抗することを開発目標としており、
世界の第3世代戦車トップクラスに比肩する性能を有する。
製造は、車体と砲塔を三菱重工業、120mm滑腔砲を日本製鋼所が担当し、
1990年(平成2年)度から2009年(平成21年)度までに61式戦車の全てと
74式戦車の一部を更新するために341輌が調達された。価格は1輌あたり約8億円である。
120mm滑腔砲と高度な射撃管制装置により高い射撃能力を持つ。
西側諸国の第3世代主力戦車では初となる自動装填装置を採用しており、
乗員は装填手が削減され3名となっている。装甲には複合素材が用いられ、
正面防御力は世界最高水準と評価されている。
北海道の北部方面隊以外では教育部隊の
富士教導団・第1機甲教育隊・武器学校にしか配備されておらず、
本州以南の機甲部隊は74式を主力とする。
平成23年度以降は冷戦の終結、防衛方針の変化や防衛費の削減、
東アジアの軍事バランスの変化など、世界、国内の情勢変化を受けて、
全国的な配備を目指した後継の10式戦車が配備される。一方で、
平成23年度以降に係る防衛計画の大綱で示された動的防衛力の方針から、
90式戦車も北海道以外の地域で活動を行えるよう、訓練が実施されるようになっている。



戦車で忘れられない出来事があった東千歳駐屯地
一度当ブログに掲載したことありますが、再掲載。



74式の乗り方 ↑ なるほどな〜〜〜
さて、次回からは!第二次大戦時、またはそれ以前の兵器をご紹介いたします。
どんなものが出てきますか、お楽しみに〜〜〜
まずは74式戦車から〜
74式戦車
74式戦車(ななよんしきせんしゃ)は、陸上自衛隊が61式戦車の後継として開発、
配備された国産二代目の主力戦車である。部隊内での愛称は「ナナヨン」。
第2.5世代主力戦車に分類される戦車。三菱重工業が開発を担当した。
105mmライフル砲を装備し、
油気圧サスペンションにより
車体を前後左右に傾ける姿勢制御機能を備え、←これはほんとにすごい!と思う
射撃管制装置にレーザー測距儀や弾道計算コンピューターを搭載するなど、
61式の開発された時点では実現できなかった内部機器の電子化も行われている。
軽量化のため内部容積を減らして小型化している。
配備開始から装甲増加などの大幅な改修は行われていないが、
新たな砲弾への対応能力が付与され戦闘力を向上させている。
後継車輌として第3世代主力戦車である90式戦車が開発・生産されたが、
こちらは北部方面隊以外では富士教導団など教育部隊にしか配備されていないため、
全国的に配備された74式が数の上では主力であった。
それでも年40輌程度の早さで退役が進んでおり、
74式の更新をも考慮した10式戦車の採用や、
同じ口径の砲をもつ16式機動戦闘車の採用など代替がすすんでいる。




続きまして90式戦車
ごろんたは74式にハマる前は90式の大ファンでした。
が、しかし〜〜イベントでもあまり登場してくれず
よく目にする74式にいつしか心を奪われた次第。
さらには、10式の登場が結構衝撃的であり、90式のことを
忘れていた時期もございます…90式、本当にすまない。
さて、それではその90式とはどんな戦車か?
90式戦車
90式戦車(きゅうまるしきせんしゃ)は、
日本の戦車。第二次世界大戦後に日本国内で開発生産された
自衛隊の主力戦車としては61式戦車、74式戦車に続く三代目にあたり、
第3世代主力戦車に分類される。
着上陸侵攻してくるソ連軍の機甲部隊に対抗することを開発目標としており、
世界の第3世代戦車トップクラスに比肩する性能を有する。
製造は、車体と砲塔を三菱重工業、120mm滑腔砲を日本製鋼所が担当し、
1990年(平成2年)度から2009年(平成21年)度までに61式戦車の全てと
74式戦車の一部を更新するために341輌が調達された。価格は1輌あたり約8億円である。
120mm滑腔砲と高度な射撃管制装置により高い射撃能力を持つ。
西側諸国の第3世代主力戦車では初となる自動装填装置を採用しており、
乗員は装填手が削減され3名となっている。装甲には複合素材が用いられ、
正面防御力は世界最高水準と評価されている。
北海道の北部方面隊以外では教育部隊の
富士教導団・第1機甲教育隊・武器学校にしか配備されておらず、
本州以南の機甲部隊は74式を主力とする。
平成23年度以降は冷戦の終結、防衛方針の変化や防衛費の削減、
東アジアの軍事バランスの変化など、世界、国内の情勢変化を受けて、
全国的な配備を目指した後継の10式戦車が配備される。一方で、
平成23年度以降に係る防衛計画の大綱で示された動的防衛力の方針から、
90式戦車も北海道以外の地域で活動を行えるよう、訓練が実施されるようになっている。



戦車で忘れられない出来事があった東千歳駐屯地
一度当ブログに掲載したことありますが、再掲載。



74式の乗り方 ↑ なるほどな〜〜〜
さて、次回からは!第二次大戦時、またはそれ以前の兵器をご紹介いたします。
どんなものが出てきますか、お楽しみに〜〜〜