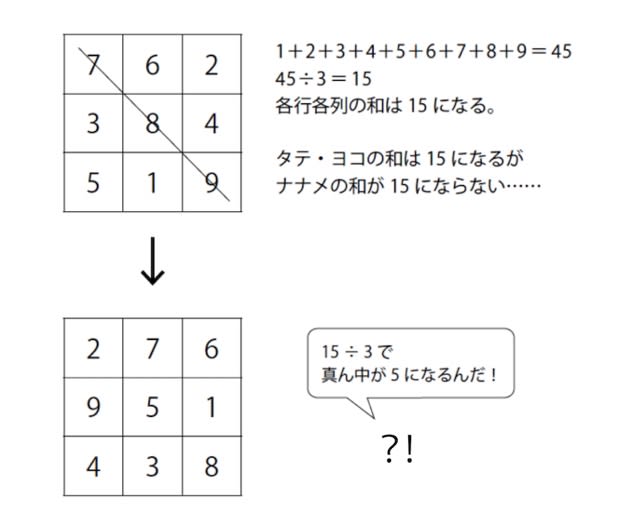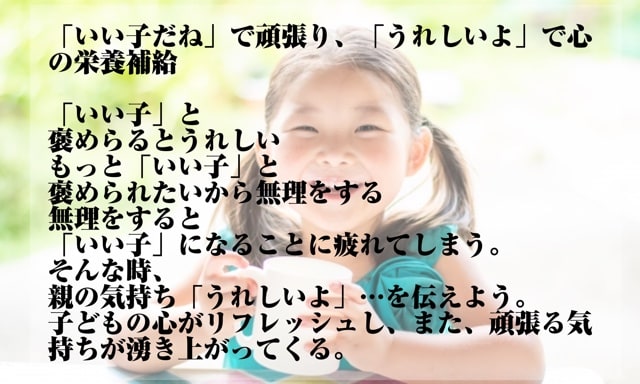こんにちは、学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、ご家庭での国語の勉強について書きます。
❤︎音読を重視しましょう。
音読には、
記憶力、
コミュニケーション能力、
思考力、
発想力
などをアップさせる力があると言われています。
まだまだ沢山の効果があります。
❤︎音読は難しい
子どもにとって音読は、
最初は難しいです。
読み飛ばしてしまったり、
句読点がついているのにそこで区切らずに、
変なところで切ってしまったり、
自分の言葉で読み替えてしまったりして、
音読がきちんと出来ず、
物語を理解することができません。
これでは、音読はきらいになります。
❤︎おうむ返し
そこで、
"親が先に読んでお手本を示し、
その後子どもがマネをして読む"
おうむ返し読みします。
小さい子どもは、
目で読むことにまだ慣れていません。
耳から入った言葉であれば、
読みやすいです。
❤︎「マネして読んでごらん」
「お母さんが、
少しずつ区切って読んであげるから、
その後マネして読んでごらん」
と優しく声を掛けてあげれば、
音読が自然に自力で読めるようになっていきます。
❤︎作文も難しい
作文を書くには5W1Hが必要です。
最初は難しいです。
「何でもいいから自分の好きなように作文しよう」
と言われても子どもは困ってしまいます。
出来事を時系列にだらだらと書いてしまいます。
まず、
書く題材を決めてあげましょう。
❤︎"時"を限定して
そして、
「今日、公園で鉄棒をしたことを書いてごらん」
「図工で工作をしたことを書いてごらん」……
"時"を限定して書かせるよう誘導すれば、
ぐんと書きやすくなります。
❤︎より深く話が展開できる
また、
短い"時"に限定すると、
出来事の中で
思ったことや、
感じたことを入れていかなければ、
文字数を稼げませんから、
自然とよい作文が書けるようになります。
一つの出来事について、
より深く話を展開できるようになります。
❤︎まとめ。音読はおうむ返し、作文は"時"を限定して
読むこと、書くことが好きになると、
子どもたちは、
いろいろな言葉を聞き、
いろいろな本を読み、
聞いたこと読んだことを考えて、
それについて自分の思ったことを
言葉で表現ができるようになります。
生きるために必要で大切な力
思考力・表現力を
自然と身につけるようになります。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、ご家庭での国語の勉強について書きます。
❤︎音読を重視しましょう。
音読には、
記憶力、
コミュニケーション能力、
思考力、
発想力
などをアップさせる力があると言われています。
まだまだ沢山の効果があります。
❤︎音読は難しい
子どもにとって音読は、
最初は難しいです。
読み飛ばしてしまったり、
句読点がついているのにそこで区切らずに、
変なところで切ってしまったり、
自分の言葉で読み替えてしまったりして、
音読がきちんと出来ず、
物語を理解することができません。
これでは、音読はきらいになります。
❤︎おうむ返し
そこで、
"親が先に読んでお手本を示し、
その後子どもがマネをして読む"
おうむ返し読みします。
小さい子どもは、
目で読むことにまだ慣れていません。
耳から入った言葉であれば、
読みやすいです。
❤︎「マネして読んでごらん」
「お母さんが、
少しずつ区切って読んであげるから、
その後マネして読んでごらん」
と優しく声を掛けてあげれば、
音読が自然に自力で読めるようになっていきます。
❤︎作文も難しい
作文を書くには5W1Hが必要です。
最初は難しいです。
「何でもいいから自分の好きなように作文しよう」
と言われても子どもは困ってしまいます。
出来事を時系列にだらだらと書いてしまいます。
まず、
書く題材を決めてあげましょう。
❤︎"時"を限定して
そして、
「今日、公園で鉄棒をしたことを書いてごらん」
「図工で工作をしたことを書いてごらん」……
"時"を限定して書かせるよう誘導すれば、
ぐんと書きやすくなります。
❤︎より深く話が展開できる
また、
短い"時"に限定すると、
出来事の中で
思ったことや、
感じたことを入れていかなければ、
文字数を稼げませんから、
自然とよい作文が書けるようになります。
一つの出来事について、
より深く話を展開できるようになります。
❤︎まとめ。音読はおうむ返し、作文は"時"を限定して
読むこと、書くことが好きになると、
子どもたちは、
いろいろな言葉を聞き、
いろいろな本を読み、
聞いたこと読んだことを考えて、
それについて自分の思ったことを
言葉で表現ができるようになります。
生きるために必要で大切な力
思考力・表現力を
自然と身につけるようになります。